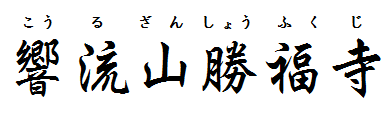釈尊の生涯 (誕生~出家)

釈尊は今から2500年ほど前にお生まれになられました。その教えはアジア一帯に広がり、2500年たった今も、人々に生きる指針を与え続けてくださっています。釈尊のように、時代を超え民族を超えて人々を導いていくような偉大な思想家や宗教家は、決して個人の力でなったものではありません。あえて言えば、人々の深奥に埋もれていた解きがたい課題を、人間のいとなみの中からあふれでてくる苦しみや悲しみを通して感じ取り、その解決を人々と共に苦悩しながら発見されたのです。それが、釈尊をはじめとする偉大な宗教家や思想家であります。つまり、釈尊がかかえた課題は釈尊個人だけの課題でなく、人類すべての課題であり、釈尊が覚り説かれた法(真理)は、釈尊個人の覚りでなく、人類全体に通じる法(真理)であったのです。
そういう意味で、釈尊の教えに入る前に、釈尊が生まれ出てきたその背景を、尋ねてみておきたいと思います。
四大文明
我々の祖先、すなわち現生人類(ホモ・サピエンス)は10万年ほど前にアフリカで誕生し、世界中に広がったと言われています。その現生人類が紀元前3000年頃から文字を生み都市を創り出しました。昔はそれを世界四大文明と言っておりました。それは、メソポタミア文明、エジプト文明、インダス文明、黄河文明です。遠く離れていながらも同時的に起こったのは、なぜでしょうか? 人類史の不思議です。
枢軸時代
同じようなことが、また起きます。今度は紀元前500年前後のことです。世界で同時的に新しい思想が起こりました。それは、それまでの神話的世界を出て、自己の限界を自覚的に把握するとともに、「自分とは何か」「人間いかに生きるべきか」を考える人が出てきたのです。つまり、人類がはじめて「自己」を問題にした、のです。
中国では孔子をはじめとする諸子百家が出ました。インドでは六師外道の中から仏陀が出現しました。ギリシャではソフィストたちの中からソクラテスやプラトンが出てきました。そこには、生産力の飛躍的な向上によって富が蓄積され、農耕社会に基づく村落共同体を超えた新しい都市国家ができ、そこに住む自由人が生まれてきたということがあります。ヤスパースは世界同時的に発生したこの時代を「枢軸時代」と名づけました。それというのも、それ以降、様々に展開していった思想の根幹がこのときに出そろった、からです。
プラトン、孔子、釈尊、―― 彼らは、創造神を中心にした神話的な世界観の中で人間を了解することをやめました。神話的世界を一歩踏み出て、主体的に人間とは何かを問い、人間の生きる道を尋ねました。釈尊の言説に一番近いと言われている原始仏典を見ると、人間を超越した神仏への帰依や、宗教儀礼は出て来ないそうです。そこで説かれているのは、人間を苦悩から解脱する法を明らかにすることと、それを実践していく生活態度です。そういう点では仏教はギリシャ哲学や儒教とよく似ており、三者とも、宗教的というより哲学的であり、倫理的であります。ただし、仏教だけはインドの地で次第に宗教的なよそおいを身につけて、アジア全体へ広がっていきました。それはなぜか? そこには、釈尊が亡くなってから何百年たっても、「如是我聞」で始まるお経が生まれ続けたことと深く関係しているような気がしますが、はっきりしたことは言えません。みなさんは、どうお考えになられますか。
ともかく、仏教は、その出発点において、創造神を離れて人間に真向かいました。その点で、世界三代宗教と並べて呼ばれていますが、キリスト教とイスラム教とは大いに異なるところです。
仏教前史 ― インドという国 ―
中国では孔子をはじめとする諸子百家が出ました。インドでは六師外道の中から仏陀が出現しました。ギリシャではソフィストたちの中からソクラテスやプラトンが出てきました。そこには、生産力の飛躍的な向上によって富が蓄積され、農耕社会に基づく村落共同体を超えた新しい都市国家ができ、そこに住む自由人が生まれてきたということがあります。ヤスパースは世界同時的に発生したこの時代を「枢軸時代」と名づけました。それというのも、それ以降、様々に展開していった思想の根幹がこのときに出そろった、からです。
プラトン、孔子、釈尊、―― 彼らは、創造神を中心にした神話的な世界観の中で人間を了解することをやめました。神話的世界を一歩踏み出て、主体的に人間とは何かを問い、人間の生きる道を尋ねました。釈尊の言説に一番近いと言われている原始仏典を見ると、人間を超越した神仏への帰依や、宗教儀礼は出て来ないそうです。そこで説かれているのは、人間を苦悩から解脱する法を明らかにすることと、それを実践していく生活態度です。そういう点では仏教はギリシャ哲学や儒教とよく似ており、三者とも、宗教的というより哲学的であり、倫理的であります。ただし、仏教だけはインドの地で次第に宗教的なよそおいを身につけて、アジア全体へ広がっていきました。それはなぜか? そこには、釈尊が亡くなってから何百年たっても、「如是我聞」で始まるお経が生まれ続けたことと深く関係しているような気がしますが、はっきりしたことは言えません。みなさんは、どうお考えになられますか。
ともかく、仏教は、その出発点において、創造神を離れて人間に真向かいました。その点で、世界三代宗教と並べて呼ばれていますが、キリスト教とイスラム教とは大いに異なるところです。
仏教前史 ― インドという国 ―
以上は、人類全般を見て話してきましたが、今度は仏教に絞って考えてみたいと思います。まずは、釈尊を生み出したインドとはどういう国なのか、ということです。というのは、釈尊は中国やギリシャでは生まれなかった、インドだからこそ釈尊は生まれて、と思うからです。
インドの地図を見ると、北には人間を寄せつけない8000㍍のヒマラヤが連なっており、南には広大なデカン高原がひかえていて、その真ん中をガンジス川が一切を飲み込みながら滔々と流れています。そうした大自然を前にした時、人間は自己の狭小さを思い知らされ、個を超えた大いなる世界、―― 普遍的で永遠なる世界を思慕させられるのではないでしょうか。
インドにあっては、ヴェーダの時代から、個(人間)を超えた普遍的な世界が尊ばれてきました。こうした土壌があってはじめて仏教は芽生えたのだと思います。
次に、インドの歴史を見てみましょう。紀元前1500年頃、インド・アーリア人がインダス川中流域(パンジャーブ)に進入してきまた。紀元前1000年頃になると、先住していたドラヴィダ人を追いやって、ガンジス川の中流域まで達しました。肥沃の地を得たアーリア人は、紀元前500年頃までに膨大なヴェーダ聖典を編纂し、バラモン階級を頂点とする四姓制度を造り上げたのでした。
また、その教えはウパニシャッドと言われ、宇宙の根源であるブラフマン(梵)と人間の本質であるアートマン(我)とが究極的に同一であることを認識すること(梵我一如)が真理の把握であり、その真理を知覚することによって輪廻の業(ごう)、すなわち一切の苦悩を逃れて解脱に達することができると考えました。釈尊はそうした宗教状況の中に生まれ出たのです。
インドの地図を見ると、北には人間を寄せつけない8000㍍のヒマラヤが連なっており、南には広大なデカン高原がひかえていて、その真ん中をガンジス川が一切を飲み込みながら滔々と流れています。そうした大自然を前にした時、人間は自己の狭小さを思い知らされ、個を超えた大いなる世界、―― 普遍的で永遠なる世界を思慕させられるのではないでしょうか。
インドにあっては、ヴェーダの時代から、個(人間)を超えた普遍的な世界が尊ばれてきました。こうした土壌があってはじめて仏教は芽生えたのだと思います。
次に、インドの歴史を見てみましょう。紀元前1500年頃、インド・アーリア人がインダス川中流域(パンジャーブ)に進入してきまた。紀元前1000年頃になると、先住していたドラヴィダ人を追いやって、ガンジス川の中流域まで達しました。肥沃の地を得たアーリア人は、紀元前500年頃までに膨大なヴェーダ聖典を編纂し、バラモン階級を頂点とする四姓制度を造り上げたのでした。
また、その教えはウパニシャッドと言われ、宇宙の根源であるブラフマン(梵)と人間の本質であるアートマン(我)とが究極的に同一であることを認識すること(梵我一如)が真理の把握であり、その真理を知覚することによって輪廻の業(ごう)、すなわち一切の苦悩を逃れて解脱に達することができると考えました。釈尊はそうした宗教状況の中に生まれ出たのです。
釈尊の誕生
釈尊の幼名はゴータマ・シッダールタと言います。父はシャカ族の王、シュッドーダナ(浄飯王)です。シャカ族はコーサラ国とマガタ国に挟まれた小国であり、王といっても、共和制の下で選ばれたリーダのようなものであったようです。母は 隣国コーリヤの執政アヌシャーキの子マーヤー(摩耶)でした。
なお、覚りを開いてのちは「目覚めた人」を意味する「仏陀」と呼ばれました。「釈迦」の呼称はシャカ族出身にちなんだ呼び名です。世に貴き人ということで「釈迦牟尼世尊」(略して「釈尊」)とも呼ばれています。
釈尊、誕生の地は、摩耶夫人がお産のため故郷に帰る途中に立ち寄ったルンビニー園でした。それは今から約2500年前の紀元前463年の4月8日のことです。(南伝仏教では、誕生を紀元前563年とする)
仏伝では、生まれてすぐ七歩、歩いて、右手で天を指し、左手で地を指して、「天上天下唯我独尊」と唱えたと言われています。この故事は何を意味しているのでしょうか。それは釈尊の成道の内容と深く関係しています。みなさんも一度考えてみてください。
ところで、釈尊の誕生において忘れてならぬのは、母マーヤが誕生の七日目に死に、母の妹、マハープラジャーパティに育てられたということです。母の死は釈尊の心にどんな影を落としたでありましょう。後世、四門出遊の物語で語られるように、「死」の問題は釈尊出家の根本動機となりました。
仏伝では、過剰なまでに、釈尊は何不自由なく過ごした、と伝えられている。それは、釈尊の出家が「貧・病・争」の解決を求めるものでなかったということを言わんがためでありましょ。では何が問題で、釈尊は、家族を捨て、名誉を捨て、わざわざ難行苦行の道を選ばれたのでありましょうか。増谷文雄師は釈尊の出家を「大いなる放棄」と賛嘆されていますが、釈尊をして出家に向かわしめた理由を二つのエピソ-ドから考えてみたいと思います。
なお、覚りを開いてのちは「目覚めた人」を意味する「仏陀」と呼ばれました。「釈迦」の呼称はシャカ族出身にちなんだ呼び名です。世に貴き人ということで「釈迦牟尼世尊」(略して「釈尊」)とも呼ばれています。
釈尊、誕生の地は、摩耶夫人がお産のため故郷に帰る途中に立ち寄ったルンビニー園でした。それは今から約2500年前の紀元前463年の4月8日のことです。(南伝仏教では、誕生を紀元前563年とする)
仏伝では、生まれてすぐ七歩、歩いて、右手で天を指し、左手で地を指して、「天上天下唯我独尊」と唱えたと言われています。この故事は何を意味しているのでしょうか。それは釈尊の成道の内容と深く関係しています。みなさんも一度考えてみてください。
ところで、釈尊の誕生において忘れてならぬのは、母マーヤが誕生の七日目に死に、母の妹、マハープラジャーパティに育てられたということです。母の死は釈尊の心にどんな影を落としたでありましょう。後世、四門出遊の物語で語られるように、「死」の問題は釈尊出家の根本動機となりました。
仏伝では、過剰なまでに、釈尊は何不自由なく過ごした、と伝えられている。それは、釈尊の出家が「貧・病・争」の解決を求めるものでなかったということを言わんがためでありましょ。では何が問題で、釈尊は、家族を捨て、名誉を捨て、わざわざ難行苦行の道を選ばれたのでありましょうか。増谷文雄師は釈尊の出家を「大いなる放棄」と賛嘆されていますが、釈尊をして出家に向かわしめた理由を二つのエピソ-ドから考えてみたいと思います。
農耕祭の逸話 -「生⇔殺」の矛盾-
一つは、少年時代の農耕祭の逸話です。農夫が牛を鞭うって田を鋤いていきました。虫たちは地上に放り出され、急いで土の中にもぐりこもうとしますが、それを見ていた小鳥がさっと飛んできて虫をついばんでいきました。あっと思っていたら、今度は鷹が飛んできて、その小鳥を捕まえたのです。その様子に、少年釈迦は、「あわれ生き物は、互いに食みあう」と悲しんで、閻浮樹の下でひとり寂かに瞑想した、という話です。
少年釈迦は、農夫-牛-虫-小鳥-鷹の間で演じられた「互いに食みあう」相を他人事としないで、人間に引きかけ、さらには自分の上に引きかけて、「あわれ」と叫ばれたのだと思います。そこに垣間見えた問題は、命を生きるものがかかえている根源的な矛盾、つまり自己が生き延びるためには他を殺さずにはおれないという「生-殺」の問題ではないでしょうか。これが少年釈迦が抱え込んだ課題の一つだったと思います。
少年釈迦は、農夫-牛-虫-小鳥-鷹の間で演じられた「互いに食みあう」相を他人事としないで、人間に引きかけ、さらには自分の上に引きかけて、「あわれ」と叫ばれたのだと思います。そこに垣間見えた問題は、命を生きるものがかかえている根源的な矛盾、つまり自己が生き延びるためには他を殺さずにはおれないという「生-殺」の問題ではないでしょうか。これが少年釈迦が抱え込んだ課題の一つだったと思います。
四門出遊の物語 -「生⇔死」の矛盾-
もう一つは、四門出遊の物語として親しまれてきた逸話です。幼い時から物思いにふける釈尊を慰めようと、父王がカピラ城の外に遊びに行かせます。ところが、東の門から出たら老人に会い、南の門から出たら病人に会い、西の門から出たら死人に会って、いよいよ物思いに沈んだという物語であります。
後に四門出遊の物語となっていくその原型の話をひとつ紹介しておきます。
後に四門出遊の物語となっていくその原型の話をひとつ紹介しておきます。
比丘たちよ、私はこのように裕福で、このようにきわめて優しく柔軟であったけれども、次のような思いが起こった、―― 愚かな凡夫は、自分が老いゆくものであった、また、老いるのを免れないのに、他人が老衰したのを見ると、考えこんで、悩み、恥じ、嫌悪している。―― 自分のことを看過して。実は、私もまた老いゆくものであって、老いるのを免れないのに、他人が老衰したのを見ては、考えこんで、悩み、恥じ、嫌悪するであろう、――このことは私にふさわしくないであろう、と思って。―― 比丘たちよ、私はこのように考察したとき、私の青春の憍逸(たかぶり)はことごとく断たれてしまった。
中阿含経第29『柔軟経(じゅうなんぎょう)』
中阿含経第29『柔軟経(じゅうなんぎょう)』
この内省は「病」についても「死」についても同じように繰り返されます。釈尊はここにおいても、たまたま出遇った「老」「病」「死」を他人事とせず、自己のこととして受けとておられます。
「自分のこととして受けとめる」ということは簡単なことのように思えるかもしれませんが、「言うに易く、行うに難し」であります。私に即して言えば、四門出遊の物語は私にとって当たり前の話であって、「それで悩んだ釈尊は、ちょっと、おかしいんじゃないの」というようなぐらいでした。そんな私だからこれまでのほほんと過ごしこれたのでしょう。尻の下に火がついているのも知らず、宴をしているようなものです。
それが70にもなり身体に不調が来すようになってようやく「生・老・病・死」の方から問われることになりました。「今頃になって、何だ」と言われても仕方ありません。どうしようもないほど、遅いのです。本当はもう間に合わないはずです。
なのに私は、それほど慌てていません。なぜなら、釈尊はそんなとぼけた私のために、「生・老・病・死」を問題にし、「生・老・病・死」を超える道を尋ね、目覚めたところを包み隠さずに教えてくださっているからであります。
「自分のこととして受けとめる」ということは簡単なことのように思えるかもしれませんが、「言うに易く、行うに難し」であります。私に即して言えば、四門出遊の物語は私にとって当たり前の話であって、「それで悩んだ釈尊は、ちょっと、おかしいんじゃないの」というようなぐらいでした。そんな私だからこれまでのほほんと過ごしこれたのでしょう。尻の下に火がついているのも知らず、宴をしているようなものです。
それが70にもなり身体に不調が来すようになってようやく「生・老・病・死」の方から問われることになりました。「今頃になって、何だ」と言われても仕方ありません。どうしようもないほど、遅いのです。本当はもう間に合わないはずです。
なのに私は、それほど慌てていません。なぜなら、釈尊はそんなとぼけた私のために、「生・老・病・死」を問題にし、「生・老・病・死」を超える道を尋ね、目覚めたところを包み隠さずに教えてくださっているからであります。
釈尊の出家
話が横にそれましたが、こうした四門出遊の物語において問題になっていることは、「生」は永遠でなく、必ず「死」によって終わるということです。「生」にとっての「死」は根源的な矛盾であります。
先にあげた農耕祭で見てしまった、いのちがかかえている「生⇔殺」の矛盾。それから四門出遊の物語で見てしまった、いのちがかかえている「生⇔死」の矛盾。この二つの根源的な矛盾を内にかかえている人生は、いかにそれを忘れ、いかにそれから目をそらそうとも、その本質において「苦」であるというのが、釈尊が気づかれた人間の根本課題であったと思います。
それでは、解くに解けない課題をかけた釈尊は、どうしたのでしょうか。そのことが四門出遊の物語の最後、北の門に出ております。
釈尊は憂いに沈んだまま北の門から出た時、柿の衣をつけ、髭をそり落とし、手に鉢をもって厳かに歩む人に出会いました。その厳かな姿に驚いた釈尊は従者に「あれは何者ぞ」と尋ねますと、従者は「真理を求めて出家した沙門です」と答えられたのです。ここに釈尊の歩むべき道が決まりました。釈尊は家族の嘆きを振り捨てて、「苦」からの解脱を求めて出家しました。それは釈尊の29歳の時でした。
出家した釈尊はどうなったのでしょうか。そのことは次回、尋ねてみたいと思います。
先にあげた農耕祭で見てしまった、いのちがかかえている「生⇔殺」の矛盾。それから四門出遊の物語で見てしまった、いのちがかかえている「生⇔死」の矛盾。この二つの根源的な矛盾を内にかかえている人生は、いかにそれを忘れ、いかにそれから目をそらそうとも、その本質において「苦」であるというのが、釈尊が気づかれた人間の根本課題であったと思います。
それでは、解くに解けない課題をかけた釈尊は、どうしたのでしょうか。そのことが四門出遊の物語の最後、北の門に出ております。
釈尊は憂いに沈んだまま北の門から出た時、柿の衣をつけ、髭をそり落とし、手に鉢をもって厳かに歩む人に出会いました。その厳かな姿に驚いた釈尊は従者に「あれは何者ぞ」と尋ねますと、従者は「真理を求めて出家した沙門です」と答えられたのです。ここに釈尊の歩むべき道が決まりました。釈尊は家族の嘆きを振り捨てて、「苦」からの解脱を求めて出家しました。それは釈尊の29歳の時でした。
出家した釈尊はどうなったのでしょうか。そのことは次回、尋ねてみたいと思います。