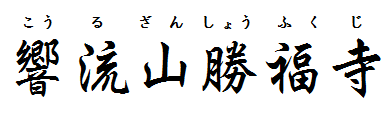悲 の 時 代
─── 「 オウム」の人々と共に ────
藤 谷 知 道
目 次
序 章 宗教の時代
第一章 「出家」ということ
第二章 現代はどんな時代か
第三章 錯覚された解脱
第四章 「オウム」の軌跡
第五章 「善」と「悪」とのドッキング
第六章 神なき時代の苦悩
第七章 「オウム」の物語
第八章 いのちの物語
第九章 回心
付 記
序章 宗教の時代
「オウム」の課題を我が課題として
今回、こうしたご縁をいただき、あらためてオウム真理教について考えてみましたが、整理がつかないまま今日の日となりました。「オウム」が突きつけた課題はとてつもなく大きく、これをどう受け止めたらいいのか、今もなお手探りしている状態です。そういう意味では、余りふさわしくない者の発表となりますが、お許し頂きたいと思います。
『別冊宝島』の「オウム」の特集号(注一)のなかに、日本にある一二六の宗教団体に出したアンケートがのっていました。アンケートの内容は次の三つです。「①社会はオウム真理教の信者をどう扱ったらいいと思うか?」、「②貴団体は、オウム真理教の信者もしくは元信者の心的ケアをする自信はあるか? YES NO 不明」、「③上記②でYESの場合、心的ケアをするとしたら、どのような方法が最適だと考えるか?」 これに対し新興宗教を中心に二十の団体が回答を寄せておりました。旧仏教からも三つ出ていましたが、残念ながら大谷派からの回答はありませんでした。教団はこういう問題に対して積極的に応えていかなければならないのではないでしょうか。そこに問われていることを誠実に受け止めていかなければ、教団は時代社会から置き去られた存在になってしまうのではないかと思っています。
さて、これは私の資質の問題なんでしょうが、「オウム」の事件があってから、本屋に行くと「オウム」という字が目に飛び込んでくるということがあります。「オウム」以前には、連合赤軍の人たちの本とか、文化大革命を引き起こした毛沢東の暴露本のようなものとか、北朝鮮を脱出した人たちのレポートとか、そういうものなんかも気になって手に取っておりました。多分それらに、自分の分身を感じるからでありましょう。
「オウム」も同じです。「オウム」の人々が抱えた課題、あるいはその解決を試みる中で起こした数々の悲劇は、とても他人事に思えません。それはそのまま私の課題でもあり悲劇でもあるように感じています。
ですから、これから述べることは、そういう資質をもった私が、「オウム」関連の本を読み進むうちに私の胸に響いてきたことを基にして、拙い頭であれこれ考えてみたことである、ということをはじめにお断りしておきたいと思います。
『別冊宝島』の「オウム」の特集号(注一)のなかに、日本にある一二六の宗教団体に出したアンケートがのっていました。アンケートの内容は次の三つです。「①社会はオウム真理教の信者をどう扱ったらいいと思うか?」、「②貴団体は、オウム真理教の信者もしくは元信者の心的ケアをする自信はあるか? YES NO 不明」、「③上記②でYESの場合、心的ケアをするとしたら、どのような方法が最適だと考えるか?」 これに対し新興宗教を中心に二十の団体が回答を寄せておりました。旧仏教からも三つ出ていましたが、残念ながら大谷派からの回答はありませんでした。教団はこういう問題に対して積極的に応えていかなければならないのではないでしょうか。そこに問われていることを誠実に受け止めていかなければ、教団は時代社会から置き去られた存在になってしまうのではないかと思っています。
さて、これは私の資質の問題なんでしょうが、「オウム」の事件があってから、本屋に行くと「オウム」という字が目に飛び込んでくるということがあります。「オウム」以前には、連合赤軍の人たちの本とか、文化大革命を引き起こした毛沢東の暴露本のようなものとか、北朝鮮を脱出した人たちのレポートとか、そういうものなんかも気になって手に取っておりました。多分それらに、自分の分身を感じるからでありましょう。
「オウム」も同じです。「オウム」の人々が抱えた課題、あるいはその解決を試みる中で起こした数々の悲劇は、とても他人事に思えません。それはそのまま私の課題でもあり悲劇でもあるように感じています。
ですから、これから述べることは、そういう資質をもった私が、「オウム」関連の本を読み進むうちに私の胸に響いてきたことを基にして、拙い頭であれこれ考えてみたことである、ということをはじめにお断りしておきたいと思います。
「オウム」は宗教である
まずはじめに、私の「オウム」に対する基本的了解を纏めてきましたので、それを読んでみたいと思います。
オウム真理教の名のもとに集まった一万とも二万とも言われる人々が、太平の世に逆らって繰り広げたエネルギッシュでデモニッシュな運動(以下「オウム」と略す)は、まず何よりも宗教的な運動であり、同時に先鋭的な形で「時代」を問おうとした一種の革命運動であったと思います。それ故、この運動に学ぶことは同時代を生きる者の責任であるし、この運動が提起した課題やその悲劇を乗り越えることを自己の課題とした者の中からしか、新しい時代は築かれないのではないかと思っています。
学問上「宗教」がどう定義されているか、私はよく知りません。また「真宗」の立場から、「宗教」なるものを論じてみようという気もありません。あえていえば一人の人間として、自己の内深くにうごめく衝動に言葉を与えてみたとき、「宗教」とは次のように定義づけられるのではないかと思っています。
「宗教」とは、「いつでもない今、どこでもないここに、だれでもない私が、生きている」という原事実の意味を、時空を超えた「超越者」との関係において確認する「物語」である。言い換えれば、自己のアイデンティティーを確立するための「超越者と私の物語」、それを「宗教」というのではなかろうか。
宗教なき時代状況の中で、いつしか人々の魂は疲れ果て、今では地下のマグマのように、人々の心の奥深くで自己のアイデンティティーを確立できる「超越者と私の物語」が求められているのではないでしょうか。「オウム」は人々のそうした宗教的な要求に応えようとしたのでした。
「オウム」には実に様々な物語が用意されており、外部の者には噴飯物のような物語が人々をしてエネルギッシュな、また時にはデモニッシュな営みに駆り立てていきました。それは他の新興宗教にも見られるし、ひるがえってみるに、法然上人や親鸞聖人のお言葉にも生き生きとした息づかいで如来の御物語が語られています。もし宗教から「物語」をとってしまえば、宗教といってもそれはもう、宗教という名の遺物になるのではないでしょうか。「オウム」の人々から投げかけられた「お寺といっても単なる風景に過ぎなかった」という弾劾は、人々を生き生きと活かす「物語」を我々がなくしてしまっていることを指摘したものだと、思っています。
学問上「宗教」がどう定義されているか、私はよく知りません。また「真宗」の立場から、「宗教」なるものを論じてみようという気もありません。あえていえば一人の人間として、自己の内深くにうごめく衝動に言葉を与えてみたとき、「宗教」とは次のように定義づけられるのではないかと思っています。
「宗教」とは、「いつでもない今、どこでもないここに、だれでもない私が、生きている」という原事実の意味を、時空を超えた「超越者」との関係において確認する「物語」である。言い換えれば、自己のアイデンティティーを確立するための「超越者と私の物語」、それを「宗教」というのではなかろうか。
宗教なき時代状況の中で、いつしか人々の魂は疲れ果て、今では地下のマグマのように、人々の心の奥深くで自己のアイデンティティーを確立できる「超越者と私の物語」が求められているのではないでしょうか。「オウム」は人々のそうした宗教的な要求に応えようとしたのでした。
「オウム」には実に様々な物語が用意されており、外部の者には噴飯物のような物語が人々をしてエネルギッシュな、また時にはデモニッシュな営みに駆り立てていきました。それは他の新興宗教にも見られるし、ひるがえってみるに、法然上人や親鸞聖人のお言葉にも生き生きとした息づかいで如来の御物語が語られています。もし宗教から「物語」をとってしまえば、宗教といってもそれはもう、宗教という名の遺物になるのではないでしょうか。「オウム」の人々から投げかけられた「お寺といっても単なる風景に過ぎなかった」という弾劾は、人々を生き生きと活かす「物語」を我々がなくしてしまっていることを指摘したものだと、思っています。
「オウム」は新しい時代を模索した革命運動であった
二十一世紀を目前にした今は、いかなる時代でありましょうか。二十世紀は、富の分配をめぐって資本主義と社会主義とが対決した時代でした。二十一世紀はそれに代わって、富の獲得をもって人間の幸福とする思想と精神性に幸福の根拠を置こうとする思想つまり宗教などとが対決する時代に入った、と見るべきでないでしょうか。
イランやイラクあるいはパレスチナなどに見られる、我々には不可解な一途な闘争は、かつての社会主義運動にみられたような、ナショナリズムを超えた熱狂があります。こうしたイスラム世界の運動を、アメリカの言うように、一国の指導者(たとえばフセイン大統領)の資質の問題に置き換えることは危険です。そこには、資本主義に変わる価値基準を模索する人間の深い願いが流れている、と受けとめるべきだと思います。
資本主義と宗教の対立は国家間同士の対立だけでなく、先進諸国の内部においても、アメリカにおけるニュー・エイジ・ムーブメントや、日本における新々宗教の興隆という形で現れてきています。今や先進諸国において追求されてきた物質的豊かさは飽和状態になり、これ以上の追求は自然界の摂理を壊す罪深いものになってきています。なのに「もういい」と言い切れる思想を、人類が共有することに成功していません。逆に、止まるところを知らぬ欲望は、坂道を転げ落ちる車のようにスピードを上げるばかりです。
資本主義には「適度」という文字はないようです。この世の一切をわが(金の)ために利用しつくそうとするモンスターであります。親子、夫婦の繋がりを絶ち切り、その人を育んだ歴史を切り捨てさせる。それも「自由」という心地よい美名のもと、本人も気づかぬうちに、人々を追い込んでいきます。
資本主義は本質的にインターナショナルであり、そのため人々が自由であることを必要とします。リンカーンが黒人解放を行ったのも、アメリカが多くの移民を受け入れたのも、人権を大切にする優しい国家だからではなく、資本にとっては思い通りに使える安い労働力が必要だったからでありましょう。資本主義は封建制の下での様々な制約や、宗教の下での非合理な制度を邪魔者として打ち壊し、「金」の前には何らの制約のない「自由」な人間を要求するシステムなのです。
それ故、高度に発達した資本主義社会にあっては、「人間」は血縁的な絆や制度的な束縛や宗教的な制約から解放された「個人」に成り下がり、お金への忠誠以外は何をやってもいいし何をやらなくってもいい自由な身になるのです。しかしその代償は大きい。気づけばいつしか人間は、寄る辺なき浮き草となり、死ぬまでの一時を、空しさをごまかすための気晴らしに駆り立てられることになってしまう他ないのです。老いも若きも、グルメに温泉に旅行であります。国を挙げての刹那主義、享楽主義に、いつしか人々は人間の魂を失った醜いモンスターになってしまっていないでしょうか。美しいもの、真理なるもの、いのちを優しく包みとる愛、そんなことを念ずる気力さえ喪失したニヒリズムの時代、これが高度に発達した資本主義社会の実態でありましょう。
そうした中にあって人々の「いのち」の奥深くでは、「自由」という美名のもとでの「孤独」より、たとえ「私」にとって「不自由」であっても「いのち」にとって歓びあふれる「関係」はないか、と模索が続いているように思います。新しい人間像はどこにあるか? 物質的豊かさに変わる真の豊かさとは何か? 旧来の社会(人間関係)に代わる新しい社会(人間関係)をどう築いたらいいのか? 深く傷ついたいのち自身が安らぎの世界を求めて、新しい旅を始めているのです。
「オウム」もまた、こうした歴史的なうねりの中から生まれ出たのでした。「オウム」は先駆者の一人として突っ走り、矛盾を拡大して自己崩壊していきました。しかしいつの時代にあっても、こうして積み重ねた悲しみの重みによってしか、時代と社会とを貫く普遍的な世界像は生まれて来ないと思います。
「オウム」の問題は、麻原彰晃という個人の資質に立ち帰って考えねばならぬことも多いのですが、オウム真理教の名の下に集まった一万数千人のエネルギッシュな運動は、何よりもまず「時代」の問題に応えようとした一つの実験だった、と思うのです。
イランやイラクあるいはパレスチナなどに見られる、我々には不可解な一途な闘争は、かつての社会主義運動にみられたような、ナショナリズムを超えた熱狂があります。こうしたイスラム世界の運動を、アメリカの言うように、一国の指導者(たとえばフセイン大統領)の資質の問題に置き換えることは危険です。そこには、資本主義に変わる価値基準を模索する人間の深い願いが流れている、と受けとめるべきだと思います。
資本主義と宗教の対立は国家間同士の対立だけでなく、先進諸国の内部においても、アメリカにおけるニュー・エイジ・ムーブメントや、日本における新々宗教の興隆という形で現れてきています。今や先進諸国において追求されてきた物質的豊かさは飽和状態になり、これ以上の追求は自然界の摂理を壊す罪深いものになってきています。なのに「もういい」と言い切れる思想を、人類が共有することに成功していません。逆に、止まるところを知らぬ欲望は、坂道を転げ落ちる車のようにスピードを上げるばかりです。
資本主義には「適度」という文字はないようです。この世の一切をわが(金の)ために利用しつくそうとするモンスターであります。親子、夫婦の繋がりを絶ち切り、その人を育んだ歴史を切り捨てさせる。それも「自由」という心地よい美名のもと、本人も気づかぬうちに、人々を追い込んでいきます。
資本主義は本質的にインターナショナルであり、そのため人々が自由であることを必要とします。リンカーンが黒人解放を行ったのも、アメリカが多くの移民を受け入れたのも、人権を大切にする優しい国家だからではなく、資本にとっては思い通りに使える安い労働力が必要だったからでありましょう。資本主義は封建制の下での様々な制約や、宗教の下での非合理な制度を邪魔者として打ち壊し、「金」の前には何らの制約のない「自由」な人間を要求するシステムなのです。
それ故、高度に発達した資本主義社会にあっては、「人間」は血縁的な絆や制度的な束縛や宗教的な制約から解放された「個人」に成り下がり、お金への忠誠以外は何をやってもいいし何をやらなくってもいい自由な身になるのです。しかしその代償は大きい。気づけばいつしか人間は、寄る辺なき浮き草となり、死ぬまでの一時を、空しさをごまかすための気晴らしに駆り立てられることになってしまう他ないのです。老いも若きも、グルメに温泉に旅行であります。国を挙げての刹那主義、享楽主義に、いつしか人々は人間の魂を失った醜いモンスターになってしまっていないでしょうか。美しいもの、真理なるもの、いのちを優しく包みとる愛、そんなことを念ずる気力さえ喪失したニヒリズムの時代、これが高度に発達した資本主義社会の実態でありましょう。
そうした中にあって人々の「いのち」の奥深くでは、「自由」という美名のもとでの「孤独」より、たとえ「私」にとって「不自由」であっても「いのち」にとって歓びあふれる「関係」はないか、と模索が続いているように思います。新しい人間像はどこにあるか? 物質的豊かさに変わる真の豊かさとは何か? 旧来の社会(人間関係)に代わる新しい社会(人間関係)をどう築いたらいいのか? 深く傷ついたいのち自身が安らぎの世界を求めて、新しい旅を始めているのです。
「オウム」もまた、こうした歴史的なうねりの中から生まれ出たのでした。「オウム」は先駆者の一人として突っ走り、矛盾を拡大して自己崩壊していきました。しかしいつの時代にあっても、こうして積み重ねた悲しみの重みによってしか、時代と社会とを貫く普遍的な世界像は生まれて来ないと思います。
「オウム」の問題は、麻原彰晃という個人の資質に立ち帰って考えねばならぬことも多いのですが、オウム真理教の名の下に集まった一万数千人のエネルギッシュな運動は、何よりもまず「時代」の問題に応えようとした一つの実験だった、と思うのです。
新しき時代は新しき思想を生み出す
「オウム」は新しい時代を生み出そうとする試みだったという理由を、人類の歴史を俯瞰しながら、もう少し考えてみたいと思います。
人類は類人猿から分かれてからも永いあいだ、自然の恵みに依存する狩猟採取生活を行ってきました。それが今から一万年ぐらい前より、自らの意志で自然をコントロールすることを考えつきました。つまり農耕・牧畜の開始です。これによって人類は生産性を飛躍的に伸ばし、食べることから自由になった人々が生まれました。食べることから自由になった人々は、その時間を使って自分の心に浮かぶものを次々と現実化させていきました。世界の四大文明の発祥です。
文明の象徴は都市です。都市とは何を意味しているのでしょうか。都市とは自然界にはないもの、つまり人為的世界です。家を建て、水道を造り、法律をもつ。これらは皆、人間が考えて作ったものです。つまり意識の外化です。意識(知性)は魔法の杖です。次から次ぎに、自然界にないものを生み出していきます。ここに人間は自然を対象にすることから一歩進んで、自己自身、特に意識存在としての自己自身を対象に、その意味を究明することが始まりました。
本当に不思議なことですが、世界の四大文明がほぼ同時期に始まったように、人類の教師ともいうべき人々が紀元前五世紀ごろに同時に出ています。釈迦、ソクラテス、孔子であり、少し遅れますがイエス・キリストもまた人類の教師となりました。この四人の出現には共通の背景があります。都市国家の存在であり、そこに出現したあまたの思想家による論争です。
釈尊の前には六師外道がいます。孔子が出てくるときには百家争鳴という背景があります。ソクラテスが出てくるときにはソフィストたちの終わりなき戯論があります。
新しい時代が始まり、それにふさわしい新しい思想が必要になった時、必ずたくさんの思想家が出て来ていろんな運動を起こし、その多くが傷つき倒れる中から、真に普遍的な思想がただ一つ残っていくのだろうと思います。
人類は類人猿から分かれてからも永いあいだ、自然の恵みに依存する狩猟採取生活を行ってきました。それが今から一万年ぐらい前より、自らの意志で自然をコントロールすることを考えつきました。つまり農耕・牧畜の開始です。これによって人類は生産性を飛躍的に伸ばし、食べることから自由になった人々が生まれました。食べることから自由になった人々は、その時間を使って自分の心に浮かぶものを次々と現実化させていきました。世界の四大文明の発祥です。
文明の象徴は都市です。都市とは何を意味しているのでしょうか。都市とは自然界にはないもの、つまり人為的世界です。家を建て、水道を造り、法律をもつ。これらは皆、人間が考えて作ったものです。つまり意識の外化です。意識(知性)は魔法の杖です。次から次ぎに、自然界にないものを生み出していきます。ここに人間は自然を対象にすることから一歩進んで、自己自身、特に意識存在としての自己自身を対象に、その意味を究明することが始まりました。
本当に不思議なことですが、世界の四大文明がほぼ同時期に始まったように、人類の教師ともいうべき人々が紀元前五世紀ごろに同時に出ています。釈迦、ソクラテス、孔子であり、少し遅れますがイエス・キリストもまた人類の教師となりました。この四人の出現には共通の背景があります。都市国家の存在であり、そこに出現したあまたの思想家による論争です。
釈尊の前には六師外道がいます。孔子が出てくるときには百家争鳴という背景があります。ソクラテスが出てくるときにはソフィストたちの終わりなき戯論があります。
新しい時代が始まり、それにふさわしい新しい思想が必要になった時、必ずたくさんの思想家が出て来ていろんな運動を起こし、その多くが傷つき倒れる中から、真に普遍的な思想がただ一つ残っていくのだろうと思います。
「オウム」のもつ歴史的意味
人類は今、これまでとは違った新しい領域に入ろうとしているのかもしれません。これまでの人類は、釈迦、ソクラテス、孔子、キリストたちの思想や宗教によって知性の暴走にブレーキをかけてきました。ところが今では、知性に掛けていた歯止めがなくなり、高度情報化社会が出現しました。肉体を持って生きることから遠く離れて、意識(頭)で生きる人々が増えてきました。彼らは、漱石が『行人』の中で言わずにおれなかったように、「死ぬか、気が違うか、それでなければ宗教にはいるか。僕の前途にはこの三つのものしかない」(注二)ところに追いつめられていると思います。そういう息苦しい時代のなかで、あらためて「人間とは何か」「私とは何か」と問わずにはいられなくなったのではないでしょうか。
「オウム」もまた、こうしたいのちの切実な問いから出発しました。結果的には大変な悲劇となってしまったのですが、こういう悲劇の中からいつの日か新しい思想が生まれるのだと思います。「オウム」のサマナであった人に、高橋英利という人がいます。彼のことは後で触れていきますが、地下鉄サリン事件の直後にテレビに出て、「オウム」における科学技術省の長官だった村井秀夫と対決したことがあります。その時から彼の姿が目に焼きついているのですが、彼の本や発言に出会うと、新しい可能性を秘めた人が出てきたなと思います。
「オウム」の事件以降、多くの人が「オウム」について語ってきました。それらのものを読んでみると、若手の思想家の言葉の方が私に響いてきました。世間でその道の権威としてもてはやされている大家の意見は、何か遠くに感じられたものです。それには深い理由があると思います。彼らの思惟方法は、理性への揺るぎなき信頼の上にあります。たぶん彼らには「オウム」が分からないのではないでしょうか。なぜなら「オウム」には、近代の理性で抑圧された人間の無意識の逆襲という面があるからです。それをまた、人間の理性で批判してみても、まったく見当はずれの議論になるばかりです。
長いこと人間は理性を頼りにして社会を作ろうとしてきました。そのため人間が抱える反社会的な心は全て悪として押さえ込まれてきました。二十一世紀は人間の抱える悪をどう解決したらよいのかが問われてくると思います。「オウム」は失敗しましたが、かといって理性で押さえ込むのはもうできません。「オウム」と同世代の人々が、「オウム」の悲しみを無駄にせず、悪をも包み込める思想を必死に探し出そうとしていると思います。
以上が「オウム」が単なる一過性の出来事でなく、また「オウム」内部の人だけの問題でなく、新しい時代の思想を生み出そうとする一つの運動だったという理由であります。
では、それなら、オウムは新しい時代を生み出す思想を獲得できたのでしょうか? 詳しく検討してみたいと思います。
「オウム」もまた、こうしたいのちの切実な問いから出発しました。結果的には大変な悲劇となってしまったのですが、こういう悲劇の中からいつの日か新しい思想が生まれるのだと思います。「オウム」のサマナであった人に、高橋英利という人がいます。彼のことは後で触れていきますが、地下鉄サリン事件の直後にテレビに出て、「オウム」における科学技術省の長官だった村井秀夫と対決したことがあります。その時から彼の姿が目に焼きついているのですが、彼の本や発言に出会うと、新しい可能性を秘めた人が出てきたなと思います。
「オウム」の事件以降、多くの人が「オウム」について語ってきました。それらのものを読んでみると、若手の思想家の言葉の方が私に響いてきました。世間でその道の権威としてもてはやされている大家の意見は、何か遠くに感じられたものです。それには深い理由があると思います。彼らの思惟方法は、理性への揺るぎなき信頼の上にあります。たぶん彼らには「オウム」が分からないのではないでしょうか。なぜなら「オウム」には、近代の理性で抑圧された人間の無意識の逆襲という面があるからです。それをまた、人間の理性で批判してみても、まったく見当はずれの議論になるばかりです。
長いこと人間は理性を頼りにして社会を作ろうとしてきました。そのため人間が抱える反社会的な心は全て悪として押さえ込まれてきました。二十一世紀は人間の抱える悪をどう解決したらよいのかが問われてくると思います。「オウム」は失敗しましたが、かといって理性で押さえ込むのはもうできません。「オウム」と同世代の人々が、「オウム」の悲しみを無駄にせず、悪をも包み込める思想を必死に探し出そうとしていると思います。
以上が「オウム」が単なる一過性の出来事でなく、また「オウム」内部の人だけの問題でなく、新しい時代の思想を生み出そうとする一つの運動だったという理由であります。
では、それなら、オウムは新しい時代を生み出す思想を獲得できたのでしょうか? 詳しく検討してみたいと思います。
第一章 「出家」ということ
麻原彰晃「絶対のものを求めて」
これから「オウム」に即して具体的に考えてみたいと思います。
「オウム」の若い人たちは基本的に出家という形をとっていきました。在家信者であっても、その精神においては世間を捨て、自己を捨てています。出家というところに「オウム」の大きな特徴があります。なぜ彼らは、世間を捨て、自己を捨てなければならなかったのか。麻原彰晃は次のように語っています。
「そのとき初めて私は立ち止まって考えてみたのである。自分は何をするために生きているのだろうか。この無常観を乗り越えるに何が必要なのだろうか。こういう感じを皆さんも時折は味わっているはずなのだが、強烈なものではない。人によっては転職をしたり、ふっと蒸発してしまうこともある。私はまったく別の方向へ歩みだしたのである。絶対のもの、動じないものを求めようという気持ちが芽生え、模索が始まったのである。それはいやおうなしにすべてのものを捨てなければならないということを意味していた。そう、いままでのことすべてを。これは大変な勇気と信念とそして覚悟を必要とすることであった」。(注三)
麻原という人はデモニッシュな人で、その発言を文字通り受け止める訳にはいきません。事実、この発言の背景には、東大受験の挫折、薬事法違反での逮捕等の行き詰まりがあります。その意味で麻原の発言はいつも眉唾ものです。しかし、「オウム」の問題は麻原個人の問題ではない。麻原が投げかける言葉に揺さぶられ、次第に共鳴し、最後には吸い取られていった人々の魂の問題です。麻原の言う「絶対のもの、動じないものを求めようという気持ち」、ーこれが「オウム」の人々の原点になっていると思います。世間を否定し自己を否定するという極端な出家の思想も、この「絶対のも、動じないものを求めようという気持ち」から起こってきたと思います。
「オウム」の若い人たちは基本的に出家という形をとっていきました。在家信者であっても、その精神においては世間を捨て、自己を捨てています。出家というところに「オウム」の大きな特徴があります。なぜ彼らは、世間を捨て、自己を捨てなければならなかったのか。麻原彰晃は次のように語っています。
「そのとき初めて私は立ち止まって考えてみたのである。自分は何をするために生きているのだろうか。この無常観を乗り越えるに何が必要なのだろうか。こういう感じを皆さんも時折は味わっているはずなのだが、強烈なものではない。人によっては転職をしたり、ふっと蒸発してしまうこともある。私はまったく別の方向へ歩みだしたのである。絶対のもの、動じないものを求めようという気持ちが芽生え、模索が始まったのである。それはいやおうなしにすべてのものを捨てなければならないということを意味していた。そう、いままでのことすべてを。これは大変な勇気と信念とそして覚悟を必要とすることであった」。(注三)
麻原という人はデモニッシュな人で、その発言を文字通り受け止める訳にはいきません。事実、この発言の背景には、東大受験の挫折、薬事法違反での逮捕等の行き詰まりがあります。その意味で麻原の発言はいつも眉唾ものです。しかし、「オウム」の問題は麻原個人の問題ではない。麻原が投げかける言葉に揺さぶられ、次第に共鳴し、最後には吸い取られていった人々の魂の問題です。麻原の言う「絶対のもの、動じないものを求めようという気持ち」、ーこれが「オウム」の人々の原点になっていると思います。世間を否定し自己を否定するという極端な出家の思想も、この「絶対のも、動じないものを求めようという気持ち」から起こってきたと思います。
鈴木大拙「仏の手だぞ」
私は諜報省長官だった井上嘉浩という人が気になってしかたありません。たぶん井上さんに自分がオーバーラップして見えるからだと思います。その井上さんについてこんなことを思ったことがあります。それは数年前、鈴木大拙先生の秘書であった岡村美穂子さんが、先生との出遇いを語った文章に出会ったときのことです。
「人が信じられなくなりました。生きていることが空しいのです」
おさげ髪の一少女のこの訴えを聞いて、先生はただ「そうか」と頷かれた。否定でも肯定でも、どちらでもない言葉だと思いました。が、その一言から感じられる深い響きは、私のかたよっていた心に、新たな衝撃を与えたのではないかと、いまにして鮮明に想い出されます。先生は私の手をとり、その手のひらをひろげながら、
「きれいな手ではないか。よく見てごらん。佛の手だぞ」
そういわれる先生の瞳は潤いをたたえていたのです。(注四)
鈴木大拙先生は十五歳の少女が発した「生きていることが空しいのです」という叫びに対し、手をとり「これは仏の手だぞ」とおっしゃったというのです。岡村さんはこの出遇いによって、鈴木先生に生涯師事することになりました。
私も十五歳の頃、およそ一年間、自己嫌悪の泥沼に陥って息をすることも苦しいということがありました。だからこの文章を読んだ時、私も鈴木大拙先生より手を取られ、「仏の手だぞ」と言われたような気がしました。同時にそのとき思ったのは、井上さんもぜひ一緒にこれを聞いてくれたらなあ、ということでした。
おさげ髪の一少女のこの訴えを聞いて、先生はただ「そうか」と頷かれた。否定でも肯定でも、どちらでもない言葉だと思いました。が、その一言から感じられる深い響きは、私のかたよっていた心に、新たな衝撃を与えたのではないかと、いまにして鮮明に想い出されます。先生は私の手をとり、その手のひらをひろげながら、
「きれいな手ではないか。よく見てごらん。佛の手だぞ」
そういわれる先生の瞳は潤いをたたえていたのです。(注四)
鈴木大拙先生は十五歳の少女が発した「生きていることが空しいのです」という叫びに対し、手をとり「これは仏の手だぞ」とおっしゃったというのです。岡村さんはこの出遇いによって、鈴木先生に生涯師事することになりました。
私も十五歳の頃、およそ一年間、自己嫌悪の泥沼に陥って息をすることも苦しいということがありました。だからこの文章を読んだ時、私も鈴木大拙先生より手を取られ、「仏の手だぞ」と言われたような気がしました。同時にそのとき思ったのは、井上さんもぜひ一緒にこれを聞いてくれたらなあ、ということでした。
井上嘉浩「自分自身を破壊したい」
なぜそんなことを思ったかというと、井上さんにこんな詩があるからです。それは中学三年のときに書いた「願望」という四コマ漫画につけた詩です。(注五)
朝夕のラッシュアワー
時につながれた中年達
夢を失い
ちっぽけな金にしがみつき
ぶら下がっているだけの大人達
工場の排水が
川を汚していくように
金が人の心をよごし
大衆どもをクレージーにさす
時間に追いかけられて
歩き回る一日が終わると
すぐ、次の朝
日の出とともに
逃げ出せない人の渦がやってくる
救われないぜ
これがおれたちの明日ならば
逃げ出したいぜ
金と欲だけがある
このきたない人波の群れから
夜行列車に乗って……
時につながれた中年達
夢を失い
ちっぽけな金にしがみつき
ぶら下がっているだけの大人達
工場の排水が
川を汚していくように
金が人の心をよごし
大衆どもをクレージーにさす
時間に追いかけられて
歩き回る一日が終わると
すぐ、次の朝
日の出とともに
逃げ出せない人の渦がやってくる
救われないぜ
これがおれたちの明日ならば
逃げ出したいぜ
金と欲だけがある
このきたない人波の群れから
夜行列車に乗って……
ここには、身体が子供から大人に変化していくのに続いて起こってくる自我意識の暴走があります。これまで事あるごとに「お前はまだ子供なんだから」と押さえつけられていた自我意識が、身体の成長とともに一気に肥大して、逆に大人を見下して快哉を叫ぶ、そんな青年期特有の病んだヒーロー意識が蠢いています。
これは尾崎豊の詩をベースにしているそうです。今の若者の心に言葉を与えたならば、きっとこうなるのでしょう。しかし、大人を見下す自分の意識を問い直すことのないまま、どこどこまでも舞い上がってしまったならば、はたして現実の大地に降り立つことができるでしょうか。尾崎豊は薬物に身を崩しながら事故死しました。井上さんや「オウム」の人々は狂気の暴走をしてしまいました。なぜでしょうか。
この詩を書いた頃の井上さんは、それでもまだ楽だったと思います。簡単に言えば「汚いのは社会だ」と、憎悪の眼を外に向けておればいい。しかしまもなく、眼を自分自身に向けねばならぬ日が来る。十六歳になった井上さんは麻原彰晃に向かって、声を震わせながらこう言ったというのです。
「先生、私は自分自身を破壊したい、自分自身を木端微塵に破壊したい。それはどういうふうにすればよろしいんですか」。「私は自我が自分の中で蠢くのが嫌いでたまりません」。「自分自身が恨みや嫉みいろいろなものを感じてふるまっているのが僕は嫌いでたまりません。自分自身が穢れていることを自分で十分認識して、自分のそういうものを木端微塵に壊したい」と。(注六)
人間は成長の過程で、大なり小なりこういう衝動に駆られることがあります。問題は、その時、これを受け止めてくれる大人が身の回りにいるかということです。ほとんどの場合、父も母も学校の先生も、ただ戸惑うばかりであります。麻原はこういう問いを真正面から受け止めて見せたのでしょう。だから井上さんは、また多くの若者が、すべてを捨てて出家したのです。
これは尾崎豊の詩をベースにしているそうです。今の若者の心に言葉を与えたならば、きっとこうなるのでしょう。しかし、大人を見下す自分の意識を問い直すことのないまま、どこどこまでも舞い上がってしまったならば、はたして現実の大地に降り立つことができるでしょうか。尾崎豊は薬物に身を崩しながら事故死しました。井上さんや「オウム」の人々は狂気の暴走をしてしまいました。なぜでしょうか。
この詩を書いた頃の井上さんは、それでもまだ楽だったと思います。簡単に言えば「汚いのは社会だ」と、憎悪の眼を外に向けておればいい。しかしまもなく、眼を自分自身に向けねばならぬ日が来る。十六歳になった井上さんは麻原彰晃に向かって、声を震わせながらこう言ったというのです。
「先生、私は自分自身を破壊したい、自分自身を木端微塵に破壊したい。それはどういうふうにすればよろしいんですか」。「私は自我が自分の中で蠢くのが嫌いでたまりません」。「自分自身が恨みや嫉みいろいろなものを感じてふるまっているのが僕は嫌いでたまりません。自分自身が穢れていることを自分で十分認識して、自分のそういうものを木端微塵に壊したい」と。(注六)
人間は成長の過程で、大なり小なりこういう衝動に駆られることがあります。問題は、その時、これを受け止めてくれる大人が身の回りにいるかということです。ほとんどの場合、父も母も学校の先生も、ただ戸惑うばかりであります。麻原はこういう問いを真正面から受け止めて見せたのでしょう。だから井上さんは、また多くの若者が、すべてを捨てて出家したのです。
幼きいのちに救われて
私も思い返せば、十五から十六にかけての一年間、学校に行くのも辛かった。父に「もう学校を辞める。どこか山奥の禅寺の小僧にでも出してくれ」と泣いてお願いしたことがあります。もちろん父は「何を言っているか全然わからない」といった顔でした。今だったら田舎にいてもいろんな情報が入ってくるでしょうから、不登校とか退学とか家出とか、何かアクションを起こせたと思います。しかし当時の私には、学校をやめてから後の自分をイメージできなかったし、イメージできぬまま故郷を飛び出る勇気もありませんでした。
それではどうしたかというと、嫌な学校から帰ったら、小学校の一年生か二年生だった三番目の妹を自転車の後ろに乗せて、二キロほど離れたところにある大きな川に毎日のように遊びに行きました。そして妹と無邪気に石を投げたり、自転車のまま川を渡ったりして遊んだのでした。妹はまだ小学校の一、二年ですから単純で、私の心を覗き込もうとしません。ただ、暑ければ暑いと、おもしろければおもしろいと言うだけです。そういう存在、まだ意識が未発達の、それこそいのちそのものと一つになって生きている幼い魂が、私を救ってくれたのでした。そして高校三年になる頃には、学校にいることも苦痛でなくなったし、友達と人生を語り合うこともそれなりに楽しくなりました。
思えば身体が急激に成長していく時、ちょっと遅れて意識の成長も起こってくる。そういう自意識の爆発的な成長の中で、社会との対立、自分自身との対立が起こってくるのだと思います。ところが一時代前までは、いろいろ偉そうなことを言っても、隣で妹がギャーギャー泣いているとか、待ったなしで田植えがあるとか、ふと眼を上げれば夕焼け空にトンボが飛んでいるとか、そんな確かな生活があって、それが、社会や自己自身から遊離していこうとする自意識を現実に引き戻してくれていたのだと思います。ところが現代では、そうした生活がなくなってきている。糸の切れた凧のように、いのちの大地から遊離してしまった自意識が、着地点が見つからぬままさまよっている。若い人々にとって、実につらい時代になっていると思います。
それではどうしたかというと、嫌な学校から帰ったら、小学校の一年生か二年生だった三番目の妹を自転車の後ろに乗せて、二キロほど離れたところにある大きな川に毎日のように遊びに行きました。そして妹と無邪気に石を投げたり、自転車のまま川を渡ったりして遊んだのでした。妹はまだ小学校の一、二年ですから単純で、私の心を覗き込もうとしません。ただ、暑ければ暑いと、おもしろければおもしろいと言うだけです。そういう存在、まだ意識が未発達の、それこそいのちそのものと一つになって生きている幼い魂が、私を救ってくれたのでした。そして高校三年になる頃には、学校にいることも苦痛でなくなったし、友達と人生を語り合うこともそれなりに楽しくなりました。
思えば身体が急激に成長していく時、ちょっと遅れて意識の成長も起こってくる。そういう自意識の爆発的な成長の中で、社会との対立、自分自身との対立が起こってくるのだと思います。ところが一時代前までは、いろいろ偉そうなことを言っても、隣で妹がギャーギャー泣いているとか、待ったなしで田植えがあるとか、ふと眼を上げれば夕焼け空にトンボが飛んでいるとか、そんな確かな生活があって、それが、社会や自己自身から遊離していこうとする自意識を現実に引き戻してくれていたのだと思います。ところが現代では、そうした生活がなくなってきている。糸の切れた凧のように、いのちの大地から遊離してしまった自意識が、着地点が見つからぬままさまよっている。若い人々にとって、実につらい時代になっていると思います。
林郁夫「完璧な円にしたい」
出家ということで考えさせられるのは、治療省長官だった林郁夫さんの話です。彼は「大学卒業後の生活の中で、自分に欠けている部分、欠点を補いたい、完璧な円にしたいと思っていたんです。それで原始仏教の本をいろいろ読んだ時、解脱やさとりができる」と聞いて、このときは阿含宗に入っております。それから「オウム」に出会い、病院をやめて家族ともども出家する時には、「一日も早く悟りと解脱を得て、偏りのない心を持って社会に還元できるよう努力する所存です」という挨拶状を出しています。(注七)
ここにある「自分に欠けている部分を補い、完璧な円になりたい」という意識は、「オウム」の人々に通ずるものです。「オウム」の人たちは白いサマナ服を着ていました。これは、薄汚れた自分をもう一度真っ白にしたい、という願望の表現だそうです。一見まじめそうに見えるこうした考えは、実は病んだ意識なんだと気づくことができるか? ここに「オウム」の問題が凝縮していると思います。「オウム」に残った人も「オウム」から離れた人も、その多くは今でも、自分たちが取った方向性は正しいと思っています。スタートの最初にある、完璧を求め醜さを憎むその意識そのものを問えないでいます。そうした中で、少数の人がそのことに気づき始めているようです。その一人に、村井秀夫の下にいた高橋英利という人がいます。
ここにある「自分に欠けている部分を補い、完璧な円になりたい」という意識は、「オウム」の人々に通ずるものです。「オウム」の人たちは白いサマナ服を着ていました。これは、薄汚れた自分をもう一度真っ白にしたい、という願望の表現だそうです。一見まじめそうに見えるこうした考えは、実は病んだ意識なんだと気づくことができるか? ここに「オウム」の問題が凝縮していると思います。「オウム」に残った人も「オウム」から離れた人も、その多くは今でも、自分たちが取った方向性は正しいと思っています。スタートの最初にある、完璧を求め醜さを憎むその意識そのものを問えないでいます。そうした中で、少数の人がそのことに気づき始めているようです。その一人に、村井秀夫の下にいた高橋英利という人がいます。
高橋英利「存在の不安をかかえて」
彼は「オウム」の中にあって、自分を見失わずにすんだ希な人だと思います。それというのも、彼は幼い時から自分自身とは何かを、必死に考え続けてきた歴史があったからです。
彼は小学校に入る前、買ってもらった自転車で団地の中をぐるぐる回っているうちに、自分の居場所がわからなくなるという経験をしております。自転車に乗って団地の壁に書かれている数字を1、2、3、4と数えていくうちに、なぜだか自分の住むアパートの棟数がなくなってしまった。いつしか道をはさんだ向かいの団地に迷い込んでしまっていたのです。とうとう夕暮れになって、なんとか自分の住むアパーと同じ棟数を見つけだし、必死の思いで戸を開けて「おかあさん」と呼んだら、知らぬおばさんが出てきて「あなたはだれ?」と言われたというのです。そういう中で、おかあさんといっても何時おかあさんでなくなるか分からない、単なる偶然で必然性は何もないのではないか、つまり「自分という存在は偶然の存在である」という不安にとらわれたと、こんな話をしておりました。(注八)
彼はその後、スポーツや芸術に打ち込んだり、宇宙物理学を学んでいくことになりますが、そうした選択を彼にさせたのは、幼い時から抱え込んだ漠然とした存在の不安であったと言えると思います。彼の歩みには仏典に説かれている「善財童子の物語」が連想されます。
彼は小学校に入る前、買ってもらった自転車で団地の中をぐるぐる回っているうちに、自分の居場所がわからなくなるという経験をしております。自転車に乗って団地の壁に書かれている数字を1、2、3、4と数えていくうちに、なぜだか自分の住むアパートの棟数がなくなってしまった。いつしか道をはさんだ向かいの団地に迷い込んでしまっていたのです。とうとう夕暮れになって、なんとか自分の住むアパーと同じ棟数を見つけだし、必死の思いで戸を開けて「おかあさん」と呼んだら、知らぬおばさんが出てきて「あなたはだれ?」と言われたというのです。そういう中で、おかあさんといっても何時おかあさんでなくなるか分からない、単なる偶然で必然性は何もないのではないか、つまり「自分という存在は偶然の存在である」という不安にとらわれたと、こんな話をしておりました。(注八)
彼はその後、スポーツや芸術に打ち込んだり、宇宙物理学を学んでいくことになりますが、そうした選択を彼にさせたのは、幼い時から抱え込んだ漠然とした存在の不安であったと言えると思います。彼の歩みには仏典に説かれている「善財童子の物語」が連想されます。
神田美由紀「夢と現実との逆転」
高橋さんは幼い時から、押入れの中に入るとか、眠るとき布団を頭からかぶるとかして、いろいろな夢想を楽しんでいたと言っています。(注九)「オウム」にはそれよりさらに進んで、幼い時から意識と現実とが逆転してしまっていたような人がおります。
たとえば『約束された場所で』のなかに出てくる神田みゆきという人なんかもそうです。彼女は兄二人に続いて十六歳で入信し、さらに高校を中退して出家してしまいます。どうしてそんな若さで出家できたのかというと、彼女は幼い時から、夢の中で神秘体験をしたり、幽体離脱とかの経験を繰り返していた、というのです。すると夢の方が現実よりもリアルになる。楽しいことも、戦争みたいなことも、親しい人の死も、夢の中で経験してしまう。この世界は無常なんだということも、夢で気づいたというのです。だから「真の幸福を得るためには解脱をしなくてはならない」と説く麻原の本を読んだ時、「ああ、私がこれまで求めていたのはこれだったんだ」と思ってしまったと言います。(注一〇)あまりにストーレートに直結してしまうことに、どこか病的なものを感じるのですが、本人たちは全くそんなふうに思っていません。だから十六歳ながら進んで出家できたのでしょう。
神田さんから聞き書きした村上春樹氏は、「彼女と話していると、この人にとってオウム真理教というのは、理想的な容れものであったのだなと納得してしまう。たしかに現世で生きているよりは、教団に入って修行をしている方が、この人にとっては遥かに幸福であったに違いない」と言っています。(注一一)彼らのことを聞くと、時代はいよいよ病を深くしているなと思わずにおれません。
たとえば『約束された場所で』のなかに出てくる神田みゆきという人なんかもそうです。彼女は兄二人に続いて十六歳で入信し、さらに高校を中退して出家してしまいます。どうしてそんな若さで出家できたのかというと、彼女は幼い時から、夢の中で神秘体験をしたり、幽体離脱とかの経験を繰り返していた、というのです。すると夢の方が現実よりもリアルになる。楽しいことも、戦争みたいなことも、親しい人の死も、夢の中で経験してしまう。この世界は無常なんだということも、夢で気づいたというのです。だから「真の幸福を得るためには解脱をしなくてはならない」と説く麻原の本を読んだ時、「ああ、私がこれまで求めていたのはこれだったんだ」と思ってしまったと言います。(注一〇)あまりにストーレートに直結してしまうことに、どこか病的なものを感じるのですが、本人たちは全くそんなふうに思っていません。だから十六歳ながら進んで出家できたのでしょう。
神田さんから聞き書きした村上春樹氏は、「彼女と話していると、この人にとってオウム真理教というのは、理想的な容れものであったのだなと納得してしまう。たしかに現世で生きているよりは、教団に入って修行をしている方が、この人にとっては遥かに幸福であったに違いない」と言っています。(注一一)彼らのことを聞くと、時代はいよいよ病を深くしているなと思わずにおれません。
世界の終わりへの恐れ
「オウム」の人たちを出家に駆り立てた要因の一つに、世界の終わりへの恐れ、つまり終末観があります。「オウム」世代の若者は、「風の谷のナウシカ」や「宇宙戦艦ヤマト」や「未来少年コナン」とかを見て育ちました。これらは私たちが育った時の「鉄人二十八号」とは決定的に違います。「鉄人二十八号」は輝かしき未来の象徴です。科学は発達し清潔で便利な生活が始まり、この世は人々の善意が溢れる社会になる、という人間賛歌でした。
それからわずか三十年、輝かしき未来は姿を引っ込めて、科学の暴走による世界の終わりが予見されるようになったのです。大人は自己のエゴに囚われて愛を失い、愚かな争いの後についに核戦争を起こしてしまう。まだ穢れていないが故に神から未来を託された若き戦士たちが、悲しみに覆われたその焼け野原に、新しい世界を築き始めると。こうしたストーリーを、今の若い魂はリアルに感じておるのです。
「オウム」の人々の超能力への憧れは、人類がかって経験したことがないような怖ろしい課題を、若き魂が抱え込んでいることを物語っているのだと思います。
それからわずか三十年、輝かしき未来は姿を引っ込めて、科学の暴走による世界の終わりが予見されるようになったのです。大人は自己のエゴに囚われて愛を失い、愚かな争いの後についに核戦争を起こしてしまう。まだ穢れていないが故に神から未来を託された若き戦士たちが、悲しみに覆われたその焼け野原に、新しい世界を築き始めると。こうしたストーリーを、今の若い魂はリアルに感じておるのです。
「オウム」の人々の超能力への憧れは、人類がかって経験したことがないような怖ろしい課題を、若き魂が抱え込んでいることを物語っているのだと思います。
全てを捨てた
「オウム」における出家において大切だと思うことを、もう一つ言っておきたいと思います。「オウム」は何事にも徹底していました。高橋英利さんの場合でいえば、出家するにあたってアルバムや日記を焼き捨てています。もちろん親も捨てております。これらは過去を捨てたことを意味していると思います。彼は最先端の天文学をやっていましたが、その学問や夢を捨てています。これは自分の未来を捨てたことを意味しておると思います。さらには彼女と別れています。これは人間の自然的身体性を切り捨てたことを意味しておると思います。
林郁夫さんは心臓外科医としての名声はもちろん、全財産を処分して八千万円を越すお金を寄付しています。村井秀夫さんは夫婦そろって出家するのですが、その際わざわざ離婚しています。家族の関係もまた捨て去る対象だったのです。また出家に際しての誓約書には、修行の過程で死んでも文句を言わないと誓うだけでなく、もし死んだら生命保険の給付金は教団に寄付するとまで誓約しております。
こうなると言葉は同じ出家であっても、仏教やキリスト教にあった出家主義とは違っておることに気づきます。本来の出家主義は、個人ばかりでなく教団も世俗を超えようとして、迷いの元となる世俗のものを捨てようとします。ところが「オウム」にあっては、個人に一切を捨てさせながら、教団はそれをどん欲に吸い取っていきました。個々人に要求した出家は、教団(麻原)が一切合切を収奪するための都合のいい論理だったという側面があります。リムジンを乗りまわす麻原、食べることにも性についても何でもありだった麻原、こんなでたらめな事実がありながらも、知的な人ほど「出家」という言葉に引っかかってしまったのです。逆から言えば、知的でない人は「オウム」に引っかからなかったはずです。
「オウム」における出家において大切だと思うことを、もう一つ言っておきたいと思います。「オウム」は何事にも徹底していました。高橋英利さんの場合でいえば、出家するにあたってアルバムや日記を焼き捨てています。もちろん親も捨てております。これらは過去を捨てたことを意味していると思います。彼は最先端の天文学をやっていましたが、その学問や夢を捨てています。これは自分の未来を捨てたことを意味しておると思います。さらには彼女と別れています。これは人間の自然的身体性を切り捨てたことを意味しておると思います。
林郁夫さんは心臓外科医としての名声はもちろん、全財産を処分して八千万円を越すお金を寄付しています。村井秀夫さんは夫婦そろって出家するのですが、その際わざわざ離婚しています。家族の関係もまた捨て去る対象だったのです。また出家に際しての誓約書には、修行の過程で死んでも文句を言わないと誓うだけでなく、もし死んだら生命保険の給付金は教団に寄付するとまで誓約しております。
こうなると言葉は同じ出家であっても、仏教やキリスト教にあった出家主義とは違っておることに気づきます。本来の出家主義は、個人ばかりでなく教団も世俗を超えようとして、迷いの元となる世俗のものを捨てようとします。ところが「オウム」にあっては、個人に一切を捨てさせながら、教団はそれをどん欲に吸い取っていきました。個々人に要求した出家は、教団(麻原)が一切合切を収奪するための都合のいい論理だったという側面があります。リムジンを乗りまわす麻原、食べることにも性についても何でもありだった麻原、こんなでたらめな事実がありながらも、知的な人ほど「出家」という言葉に引っかかってしまったのです。逆から言えば、知的でない人は「オウム」に引っかからなかったはずです。
終わりからの出発
高橋さんは出家について、「オウム」の出家信者というのは、要するに一人ひとりが自分の中に終末を受け入れているようなものなんです。出家するときに自分をすべて投げ捨てることによって、現世のものをすべて終わりにしてしまっている。つまり終わりを一度受け入れてしまった人たちだけがそこに集まっている」(注一六)と言っています。
こうした「全て」ということを要求するところは、連合赤軍事件の悲劇にも共通するとことでもあります。身体性から乖離して純粋意識になってしまっているから、こんな非現実的なことを人間に要求してしまうのでしょう。
この全てを捨てたという事実の重さが、人々をして「オウム」から立ち返れなくさせる罠になってしまったといいます。高橋さんは、「オウム」に出家した早い段階から疑問を持つようになるんですね。「オウム」の最後の一年間はほとんど戦争モードに突入した状態でした。内部から崩壊しないよう、見えないところでスパイチェックやリンチが行われています。内部にいると何となく肌でそれが分かってくる。それで疑問を出したりしています。うやむやな回答しかかえってきませんので、不信は募っていきます。でも、「オウム」をやめられなかった。なぜかと聞かれると、やはり私は最初に捨てているからだ、自分の人生をかけた、青春をかけた、実存をかけたからだと言っています。簡単に言えば「オウム」は終わりからの出発なんですね。
全てを捨てたということは自分の退路を断ったというばかりでなく、自分と世間との間が遮断されたということでもあります。そうすると音が外に出ない。内部で反響しあうことになる。内部の人数が増えれば増えるほど、音はいよいよ増幅して、最後にはいのちが本来もっている感覚まで押しつぶしてしまったのではないでしょうか。ここにカルト集団が起こす破滅に向けての暴走の構図があるように思います。
こうした「全て」ということを要求するところは、連合赤軍事件の悲劇にも共通するとことでもあります。身体性から乖離して純粋意識になってしまっているから、こんな非現実的なことを人間に要求してしまうのでしょう。
この全てを捨てたという事実の重さが、人々をして「オウム」から立ち返れなくさせる罠になってしまったといいます。高橋さんは、「オウム」に出家した早い段階から疑問を持つようになるんですね。「オウム」の最後の一年間はほとんど戦争モードに突入した状態でした。内部から崩壊しないよう、見えないところでスパイチェックやリンチが行われています。内部にいると何となく肌でそれが分かってくる。それで疑問を出したりしています。うやむやな回答しかかえってきませんので、不信は募っていきます。でも、「オウム」をやめられなかった。なぜかと聞かれると、やはり私は最初に捨てているからだ、自分の人生をかけた、青春をかけた、実存をかけたからだと言っています。簡単に言えば「オウム」は終わりからの出発なんですね。
全てを捨てたということは自分の退路を断ったというばかりでなく、自分と世間との間が遮断されたということでもあります。そうすると音が外に出ない。内部で反響しあうことになる。内部の人数が増えれば増えるほど、音はいよいよ増幅して、最後にはいのちが本来もっている感覚まで押しつぶしてしまったのではないでしょうか。ここにカルト集団が起こす破滅に向けての暴走の構図があるように思います。
第二章 現代はどんな時代なのか
自分自身が息苦しい
こうした「オウム」世代の人たちが抱え込んでしまった課題をよく整理していると思ったのが、芹沢俊介さんの『「オウム」現象の解読』という本です。これは地下鉄サリン事件が起こってからすぐに出ました。私にとっては大変、示唆に富んだ本でしたのでしばらくこの本にしたがいながら考えてみたいと思います。
なるほどなあと思ったのは、今の時代の若い人たちは、社会に対してだけでなく自分自身に対しても「いきどまり感」をもっているという指摘です。かっては今ほど心を病む人はいなかった。なぜなら、我が身に迫ってくる苦しみの原因を社会の側に置くことができた。悪いのはいつでも社会の側であって、個人の努力ではどうしようもなかった。社会そのもののあり方を変革しない限り、人間に幸せは来ないんだと。ことにこの百年間は、全ての人に平等に文明の恩恵が行き渡るよう社会の仕組みを作り替えようとしてきました。その結果、多くの人々が文明の恩恵を享受できるようになったと思います。そうした時代が到来した時、人間はもう「いきどまり感」がなくなったかというと、それを自分自身の身体や意識に対し感じるようになってきたというのです。
芹沢さんに依れば、「我々の感性が消費社会に移っていく中で、自分に対する関心が非常に強くなってきている。その強まりの動機は「わたし」の浮遊感と同時に「わたし」の欠如感とか不全感とかいきどまり感にあったといえるでしょう」(注一二)とあります。だから「自分自身の身体をいきどまり感の正体とみなす感受性、これらの病んだ感受性が、生活や人間関係における新しい構築の可能性の場を求めてあがいている」(注一三)のです。そして「こうした世紀末的、終末的飢餓感に積極的に答えようとしたのが新新宗教である。なかでも最もラディカルなのがオウム真理教であった」(注一四)と言われています。
私は団塊の世代に属するのですが、私たちの幼い頃の生活は単純なものでした。朝起きたら家族の一員としてご飯の準備をしたり、牛のえさを採りにいったり、学校から帰ってきても、家の手伝いをしなければ遊べないとか。遊ぶことも働くことも全て身体を使ってやりました。だから夜になると、疲れですぐに眠りにつけた。今では、このような身体をもってする生活に決別して、なにからなにまで意識でする生活となっています。これはどういうことを意味するのかというと、非常に鋭利な人、たとえば釈尊とか夏目漱石とか、そういう一部の人しかぶつからなかった「わたし」という問題に、ごく普通の人間までもがぶち当たらざるを得なくなったということです。
昔の人は、月夜の下で自分の影をオバケと勘違いしました。現代人は、過剰になった自意識の下で自己自身を卑小で醜悪な存在と見て、怯えています。まさにムンクの絵であります。こうした病んだ意識による自分自身に対する不全感、無力感がこうずれば、妄想の中に逃避したり、変身願望となったりするのではないでしょうか。整形手術をする人。拒食症の人、過食症の人。潔癖症の人。朝シャンだとか、おならのにおいを消すために薬を飲む人までいる。そういう意識にあっては自分自身の存在を、尊いもの、有り難きもの、豊かなもの、懐かしいものと見ることができない。自分というものは、逆に自分を苦しめる基になっている。社会が息苦しいだけではなく、自分自身が何よりもまず第一に息苦しいものなっている、それが二一世紀を目前にして人類がたどり着いた中身なのです。
なるほどなあと思ったのは、今の時代の若い人たちは、社会に対してだけでなく自分自身に対しても「いきどまり感」をもっているという指摘です。かっては今ほど心を病む人はいなかった。なぜなら、我が身に迫ってくる苦しみの原因を社会の側に置くことができた。悪いのはいつでも社会の側であって、個人の努力ではどうしようもなかった。社会そのもののあり方を変革しない限り、人間に幸せは来ないんだと。ことにこの百年間は、全ての人に平等に文明の恩恵が行き渡るよう社会の仕組みを作り替えようとしてきました。その結果、多くの人々が文明の恩恵を享受できるようになったと思います。そうした時代が到来した時、人間はもう「いきどまり感」がなくなったかというと、それを自分自身の身体や意識に対し感じるようになってきたというのです。
芹沢さんに依れば、「我々の感性が消費社会に移っていく中で、自分に対する関心が非常に強くなってきている。その強まりの動機は「わたし」の浮遊感と同時に「わたし」の欠如感とか不全感とかいきどまり感にあったといえるでしょう」(注一二)とあります。だから「自分自身の身体をいきどまり感の正体とみなす感受性、これらの病んだ感受性が、生活や人間関係における新しい構築の可能性の場を求めてあがいている」(注一三)のです。そして「こうした世紀末的、終末的飢餓感に積極的に答えようとしたのが新新宗教である。なかでも最もラディカルなのがオウム真理教であった」(注一四)と言われています。
私は団塊の世代に属するのですが、私たちの幼い頃の生活は単純なものでした。朝起きたら家族の一員としてご飯の準備をしたり、牛のえさを採りにいったり、学校から帰ってきても、家の手伝いをしなければ遊べないとか。遊ぶことも働くことも全て身体を使ってやりました。だから夜になると、疲れですぐに眠りにつけた。今では、このような身体をもってする生活に決別して、なにからなにまで意識でする生活となっています。これはどういうことを意味するのかというと、非常に鋭利な人、たとえば釈尊とか夏目漱石とか、そういう一部の人しかぶつからなかった「わたし」という問題に、ごく普通の人間までもがぶち当たらざるを得なくなったということです。
昔の人は、月夜の下で自分の影をオバケと勘違いしました。現代人は、過剰になった自意識の下で自己自身を卑小で醜悪な存在と見て、怯えています。まさにムンクの絵であります。こうした病んだ意識による自分自身に対する不全感、無力感がこうずれば、妄想の中に逃避したり、変身願望となったりするのではないでしょうか。整形手術をする人。拒食症の人、過食症の人。潔癖症の人。朝シャンだとか、おならのにおいを消すために薬を飲む人までいる。そういう意識にあっては自分自身の存在を、尊いもの、有り難きもの、豊かなもの、懐かしいものと見ることができない。自分というものは、逆に自分を苦しめる基になっている。社会が息苦しいだけではなく、自分自身が何よりもまず第一に息苦しいものなっている、それが二一世紀を目前にして人類がたどり着いた中身なのです。
個別同居型核家族
芹沢さんは家族の問題を通して時代の課題に取り組んでいる方なのですが、彼の『イエスの方舟論』を印象深く読んだことがあります。その彼が家族の形態を通しながら「イエスの方舟」事件と「オウム」の事件を比較して論じています。(注一五)
日本の家庭はながいこと多世代同居型でした。合計特殊出生率は4・5で、人口はどんどん増えていきました。それが、一九五五年ぐらいから団地ができだし、いわゆる核家族化が進みます。ただし、この頃の核家族は、お父さんは働きに出て、お母さんは子どもの面倒を見たり家事をするというふうに、夫婦で役割分担する核家族でした。芹沢さんはこうした核家族のあり方を、単世代同居型といっております。この間、出生率は2・1ぐらいまで下がって、そこで落ち着きました。2・1という数字は人口を維持するギリギリの数だそうです。
それが一九七五年以降、パートナーとしての夫婦がもてはやされだします。それぞれ独立した人間同士が、約束事の上で共同生活をするという考えです。同じ家にいながら、部屋には鍵をかける。夫婦であっても財布や部屋は別にする。芹沢さんはこれを個別同居型の核家族といっております。ここから出生率は一気に下がり始めます。いまでは1.3ぐらいまで下がりましたが、まだ止まる気配はありません。なぜでしょうか。
私には、世上よく言われるような経済的な理由とか女性の地位の問題とかではないように思われます。子供を産むということはいのちにとって最も原初的なこと、それこそ身体そのものの出来事です。ところが意識と身体の関係が逆転してしまった人間には、身体的なことは不気味な事、避けたい事になってしまうのでありましょう。不登校も、フリーターも、結婚しない事も、子供を欲しがらない事も、その原因は同じところにあるのではないでしょうか。
日本の家庭はながいこと多世代同居型でした。合計特殊出生率は4・5で、人口はどんどん増えていきました。それが、一九五五年ぐらいから団地ができだし、いわゆる核家族化が進みます。ただし、この頃の核家族は、お父さんは働きに出て、お母さんは子どもの面倒を見たり家事をするというふうに、夫婦で役割分担する核家族でした。芹沢さんはこうした核家族のあり方を、単世代同居型といっております。この間、出生率は2・1ぐらいまで下がって、そこで落ち着きました。2・1という数字は人口を維持するギリギリの数だそうです。
それが一九七五年以降、パートナーとしての夫婦がもてはやされだします。それぞれ独立した人間同士が、約束事の上で共同生活をするという考えです。同じ家にいながら、部屋には鍵をかける。夫婦であっても財布や部屋は別にする。芹沢さんはこれを個別同居型の核家族といっております。ここから出生率は一気に下がり始めます。いまでは1.3ぐらいまで下がりましたが、まだ止まる気配はありません。なぜでしょうか。
私には、世上よく言われるような経済的な理由とか女性の地位の問題とかではないように思われます。子供を産むということはいのちにとって最も原初的なこと、それこそ身体そのものの出来事です。ところが意識と身体の関係が逆転してしまった人間には、身体的なことは不気味な事、避けたい事になってしまうのでありましょう。不登校も、フリーターも、結婚しない事も、子供を欲しがらない事も、その原因は同じところにあるのではないでしょうか。
ミーイズムの出現 ー私探しの旅ー
もう一度、芹沢さんにかえります。一九七五年以降の家族形態つまり個別同居型が出現した頃からミーイズム・自分中心主義というものがでてきました。それは他の何ものによっても自分の満足は得られないという意識です。今までだったら家族の一員として生活する事で満足を得られた。子育てで十分、満足だった。ところが今では、子どもの犠牲になりたくない、夫の犠牲になりたくない、夫のために私は生きているのではない、私を満たすものは私しかないと。象徴的に言えば、「母として」生きるより、「女として」生きることに関心が移ったということです。
「母として」というときは、親子という関係性を生きるということがある。「妻として」というときは、夫婦という関係性を生きるということがある。言い換えるなら、そこには、自分に満足を与えてくれる大切な存在としての他者がいる。ところがミーイズムにあっては、私を満たすものは私しかない。そのときから日本人は「私探しの旅」に出なければならなくなったのです。
今テレビをつけると朝から晩まで「旅だ、旅だ」と言っています。「旅」ということがこれだけもてはやされるのにはこうした隠された理由があるからかもしれません。フリーターというのも、結婚しないというのも、皆そうだと思います。まだ自分探しが終わってない。旅の途中なんだと思います。
さらに言えば、一九七五年くらいから出生率が下がりだし、まだその傾向が続いているという事実は、我々の社会全体が「私探し」の答えを見つけだせてない、ということを意味していると思います。現代人は「私探し」の旅をしなければならないところに追い詰められたままになっているのではないでしょうか。こういうところに、人びとが「オウム」に吸い取られた原因の根っこがあると思います。
「母として」というときは、親子という関係性を生きるということがある。「妻として」というときは、夫婦という関係性を生きるということがある。言い換えるなら、そこには、自分に満足を与えてくれる大切な存在としての他者がいる。ところがミーイズムにあっては、私を満たすものは私しかない。そのときから日本人は「私探しの旅」に出なければならなくなったのです。
今テレビをつけると朝から晩まで「旅だ、旅だ」と言っています。「旅」ということがこれだけもてはやされるのにはこうした隠された理由があるからかもしれません。フリーターというのも、結婚しないというのも、皆そうだと思います。まだ自分探しが終わってない。旅の途中なんだと思います。
さらに言えば、一九七五年くらいから出生率が下がりだし、まだその傾向が続いているという事実は、我々の社会全体が「私探し」の答えを見つけだせてない、ということを意味していると思います。現代人は「私探し」の旅をしなければならないところに追い詰められたままになっているのではないでしょうか。こういうところに、人びとが「オウム」に吸い取られた原因の根っこがあると思います。
王子さま、王女さま
私は今、小学校のPTAの役員をしていますが、先生がある時、「今の子どもたちはみんな王子さま、王女さまで育てられている」と嘆かれたことがあります。「王子さま、王女さま」、これがミーイズムということをよく示していると思います。
我が家の一番下の娘が二年程前からピアノを習い始めました。一年に一、二回、発表会があります。私も一度だけ見に行きました。そして、びっくりしたんです。まだドレミファソラシドぐらいしか弾けない子でも、すばらしい服を着て、終わるとお母さんが花束を持っていく。難しい曲が弾けるようになった、そろそろそれにふさわしい服を作ってもよかろう、うまく弾けたら花束を持っていこう、これならわかります。ところがまだドレミファぐらいしか弾けてないのに、ドレスを作って、写真をとって、花束をあげてと、それこそ王子さま、王女さまをつくっているとしか言いようがない。
はっきり思い出せませんが、三〇年ぐらい前に「二人のため世界はあるの」という歌がはやりました。相良直美が透き通った声で幸せそうに歌いました。今から思えば、これがミーイズムのはじまりを象徴していたと思います。児玉先生がすぐ、「二人のために世界はあるのではない、世界のために二人はあるのだ」ということを言われましたが、その指摘の意味するところが今ようやく分かるようになりました。
私のために世界がある、私を中心に世界が回っている、これが「王子さま、王女さま」の身に染みついた感覚です。大きくなったら、ただの人に戻れるだろうか、この後どうなるんだろう、と思います。いよいよもって本当に辛い時代が始まったんでしょう。いつの日にか、わがままということが人間をどれだけ辛くするのかということに気づくのでしょうが、そのためには悲しみの涙をどれだけ流さねばならぬのか、気の遠くなる話です。
でもこれが、人々が長いことかけて求めてきたことなんです。国家のため、社会のため、家のため、こういうことで自分を犠牲にすることを強いられてきた歴史があります。だから、ようやく獲得した民主主義は、「国家のために自分があるのではなく、自分のために国家はあるんだ」となるのでしょう。これが革新的とか、進歩的といわれるもののスタンスです。朝日新聞などもずーとこの論調です。
私も戦前のような国家論がいいと思っていませんから、「国家のために自分があるのではなく、自分のために国家はあるんだ」という考え方に共感してきました。しかし、「国家のために自分があるのではなく、自分のために国家はあるんだ」という考え方と、「母として生きるよりも、女として生きたい」という考え方と、大差がないのではないでしょうか。芹沢さんの家族論などを通してみると、戦後大切にしてきた価値観を根本から検証し直さなければならない時が来たと思います。
我が家の一番下の娘が二年程前からピアノを習い始めました。一年に一、二回、発表会があります。私も一度だけ見に行きました。そして、びっくりしたんです。まだドレミファソラシドぐらいしか弾けない子でも、すばらしい服を着て、終わるとお母さんが花束を持っていく。難しい曲が弾けるようになった、そろそろそれにふさわしい服を作ってもよかろう、うまく弾けたら花束を持っていこう、これならわかります。ところがまだドレミファぐらいしか弾けてないのに、ドレスを作って、写真をとって、花束をあげてと、それこそ王子さま、王女さまをつくっているとしか言いようがない。
はっきり思い出せませんが、三〇年ぐらい前に「二人のため世界はあるの」という歌がはやりました。相良直美が透き通った声で幸せそうに歌いました。今から思えば、これがミーイズムのはじまりを象徴していたと思います。児玉先生がすぐ、「二人のために世界はあるのではない、世界のために二人はあるのだ」ということを言われましたが、その指摘の意味するところが今ようやく分かるようになりました。
私のために世界がある、私を中心に世界が回っている、これが「王子さま、王女さま」の身に染みついた感覚です。大きくなったら、ただの人に戻れるだろうか、この後どうなるんだろう、と思います。いよいよもって本当に辛い時代が始まったんでしょう。いつの日にか、わがままということが人間をどれだけ辛くするのかということに気づくのでしょうが、そのためには悲しみの涙をどれだけ流さねばならぬのか、気の遠くなる話です。
でもこれが、人々が長いことかけて求めてきたことなんです。国家のため、社会のため、家のため、こういうことで自分を犠牲にすることを強いられてきた歴史があります。だから、ようやく獲得した民主主義は、「国家のために自分があるのではなく、自分のために国家はあるんだ」となるのでしょう。これが革新的とか、進歩的といわれるもののスタンスです。朝日新聞などもずーとこの論調です。
私も戦前のような国家論がいいと思っていませんから、「国家のために自分があるのではなく、自分のために国家はあるんだ」という考え方に共感してきました。しかし、「国家のために自分があるのではなく、自分のために国家はあるんだ」という考え方と、「母として生きるよりも、女として生きたい」という考え方と、大差がないのではないでしょうか。芹沢さんの家族論などを通してみると、戦後大切にしてきた価値観を根本から検証し直さなければならない時が来たと思います。
はてしなき私探しの旅
人間の生き方には、いのちの促しに順って生きる身体的な側面と、意識を通して世界や自分自身を経験していく意識的側面があると思います。身体は必ず「何時でもない今、何処でもないここ、誰でもない私」としてあります。それに対し意識はなんの限定も受けていません。だから人間の意識は往々にして身体を束縛と感じ、そこから離れていこうとします。しかしいくら乖離しても、人間は結局、身体的・社会的存在ですから、それによって意識で生きることの誤りを知らされ、最後には身の事実に帰っていくといういう構造があると思います。
ところが現代になって、人間に備わっていたそういう構造が機能しなくなった。私たちを取り巻くものは今では、養老猛司さんがいうように、ほとんど人間の意識によって作られたものになっております。
朝は目覚ましで起き、テレビを見ながらパンを食べ、電車に乗ってオフィスにつけば、同僚に気を遣いながらパソコンに向かって一日過ごす。帰りにはカラオケ歌って気晴らししても、緊張してしまった意識はなかなか安まらず、しかたないので明日のため睡眠薬を飲んで眠りにつく。だんだんこんな生活になっていっているのではないでしょうか。
何十億年と自然の中にあったいのちにとって、実につらい時代です。私を優しく包んでくれる自然な世界がない。極端に言えば、一日中意識が作り出した世界の中にいるのだから、意識が破れて現実に帰っていくことが難しくなっている。今では、浮遊する自己による果てしなき「私探しの旅」が宿命づけられてしまったのではないでしょうか。
ところが現代になって、人間に備わっていたそういう構造が機能しなくなった。私たちを取り巻くものは今では、養老猛司さんがいうように、ほとんど人間の意識によって作られたものになっております。
朝は目覚ましで起き、テレビを見ながらパンを食べ、電車に乗ってオフィスにつけば、同僚に気を遣いながらパソコンに向かって一日過ごす。帰りにはカラオケ歌って気晴らししても、緊張してしまった意識はなかなか安まらず、しかたないので明日のため睡眠薬を飲んで眠りにつく。だんだんこんな生活になっていっているのではないでしょうか。
何十億年と自然の中にあったいのちにとって、実につらい時代です。私を優しく包んでくれる自然な世界がない。極端に言えば、一日中意識が作り出した世界の中にいるのだから、意識が破れて現実に帰っていくことが難しくなっている。今では、浮遊する自己による果てしなき「私探しの旅」が宿命づけられてしまったのではないでしょうか。
旅のはてで出会った親鸞聖人
今、思い出しましたが、僕自身にもそういう経験があるんです。高校二年の終わり頃になると、みんなといることがそんなに苦痛ではなくなって、学校生活も淡々とできるようになりました。その頃は、よく同級生と山に登ったり川に行ったり、夏休みなどは一緒に学校に行って、勉強するぞといいながら、とりとめもなくいろんな話しをしました。そういう中で、あるとき「大きくなったら何になりたいか」という話になりました。友人たちはさまざまな夢を語ったのですが、私の番になったとき、今でも忘れられないんですが、「僕は人間らしい人間になりたい」と答えたんです。
このことについてはたった今まで、お寺の跡取りということが自由に未来を描くことをさせなかったと思っていましたが、それだけではなかったようです。一年程前から始まっていた「私探し」のこころが、私にそういう発言をさせていたのに違いありません。
私における「私探しの旅」は大学に行っても続いたのだと思います。象牙の塔は肌に合いませんでした。大学を離れ酪農したり土方をしたり、漁師の家に居候をしたこともあります。南の島にテントをもって旅もしました。どれも楽しかったけど、仮の姿でありました。燃え盛る学生運動に興奮もしましたが、論理と論理を戦わす程、憎悪と憎悪がぶつかりあう世界となり、私には耐えられぬものでした。
大学を二回留年し、ともかく卒業しましたが、就職しようという発想はありませんでした。市民運動みたいな事をしてみましたが、結局それとも一つになれず、それから一年半落ちるところまで落ちて、ようやく大谷専修学院にたどり着きました。そこではじめて親鸞聖人の教えに触れ、世間や自分自身を偉そうに裁きたてている私の意識の方こそ病んでいるのだということに気づきました。「私」という意識は、生身のいのちから遠く乖離したところで「全知全能の神たらん」とするオバケのような意識になっていたのです。これが、私を苦しめていた正体です。何のことはない、自縄自縛のひとり芝居でした。
誠実であろうとすればする程、生身の自分から離れていき、ひとり舞い上がった高見から逆に生身の自分を裁きたてる、このアリ地獄から私を救い出してくれたのは、自力作善の虚偽なることを教えてくださる親鸞聖人でした。ものごころついた頃より嫌悪し逃げようとした世界から、逆に助けられるとは、人生には実に不思議なところがあります。
私はお寺に生まれたご縁から、何とかいのちの世界に帰ることができましたが、今のフリーターの人たちはどこで現実に帰っていくのだろうかと心配になります。「オウム」によって宗教も怪しいとなると、一体どうなるのでしょうか。原因が分からぬまま苛立ちを募らせながら、はてしなき「私探しの旅」を続けていくよりほかないのかも知れません。
このことについてはたった今まで、お寺の跡取りということが自由に未来を描くことをさせなかったと思っていましたが、それだけではなかったようです。一年程前から始まっていた「私探し」のこころが、私にそういう発言をさせていたのに違いありません。
私における「私探しの旅」は大学に行っても続いたのだと思います。象牙の塔は肌に合いませんでした。大学を離れ酪農したり土方をしたり、漁師の家に居候をしたこともあります。南の島にテントをもって旅もしました。どれも楽しかったけど、仮の姿でありました。燃え盛る学生運動に興奮もしましたが、論理と論理を戦わす程、憎悪と憎悪がぶつかりあう世界となり、私には耐えられぬものでした。
大学を二回留年し、ともかく卒業しましたが、就職しようという発想はありませんでした。市民運動みたいな事をしてみましたが、結局それとも一つになれず、それから一年半落ちるところまで落ちて、ようやく大谷専修学院にたどり着きました。そこではじめて親鸞聖人の教えに触れ、世間や自分自身を偉そうに裁きたてている私の意識の方こそ病んでいるのだということに気づきました。「私」という意識は、生身のいのちから遠く乖離したところで「全知全能の神たらん」とするオバケのような意識になっていたのです。これが、私を苦しめていた正体です。何のことはない、自縄自縛のひとり芝居でした。
誠実であろうとすればする程、生身の自分から離れていき、ひとり舞い上がった高見から逆に生身の自分を裁きたてる、このアリ地獄から私を救い出してくれたのは、自力作善の虚偽なることを教えてくださる親鸞聖人でした。ものごころついた頃より嫌悪し逃げようとした世界から、逆に助けられるとは、人生には実に不思議なところがあります。
私はお寺に生まれたご縁から、何とかいのちの世界に帰ることができましたが、今のフリーターの人たちはどこで現実に帰っていくのだろうかと心配になります。「オウム」によって宗教も怪しいとなると、一体どうなるのでしょうか。原因が分からぬまま苛立ちを募らせながら、はてしなき「私探しの旅」を続けていくよりほかないのかも知れません。
第三章 錯覚された解脱
身体への回帰
もう一度、「オウム」に帰ります。
「オウム」の人々は特別な人ではありません。ある意味では現代人の典型でもありましょう。優しい親と恵まれた環境、知的で真面目な性格、そうした「いい子」の頭の中でいつしか意識はとめどもなく肥大し、ついには自分自身(身体)から乖離して浮遊を始める。そうした不安定な意識ゆえに、自分の着地点として、あるいは回帰すべき場所として、身体ということが鍵になったようです。
身体は人間に備わる「自然」でありますから、身体に気づいたということまでは正しいと思います。ところが「オウム」は、身体(いのち)に帰らんとすることを、また意識でやろうとしました。身体といっても、それは自然的身体でなく、意識的身体でありました。ここに「オウム」の悲劇があると思います。それは、自身を愚者と肯き、身を自然法爾の世界に委ねた親鸞聖人に比べたらよく分かります。
「オウム」の人たちは身体へ回帰を意識的にやろうとしてます。それが「オウム」のヨガであります。ヨガは解脱を獲得する入口と位置づけています。ヨガということに関してはよく分からないのですが、「オウム」の人たちの報告を読むと、単なるへんてこなポーズなどではない。「オウム」の人たちはヨガによって未知の世界に踏み入れたように感じております。それは激しい呼吸法やポーズによって肉体を限界まで追い込むうちに、肉体の深奥で突然起こってくる、生エネルーギの噴出と光明に包まれる神秘体験のようです。
解脱か生理現象か
大泉実成という人がおります。この人は、「オウム」に強制捜査が入り、「オウム」が地下鉄にサリンを撒いたということが明らかになっても、多くのサマナがなぜ脱会せずにいるのかという疑問から、「オウム」の杉並道場に通いだし一緒にヨガを始めました。そして『宝島30』誌上にその報告書をリアルタイムで書いたのでした。それによると大泉さんも、本格的ではないながらも「オウム」の人たちと同じ経験をしています。しかし、彼は「オウム」には入りませんでした。なぜか。それは大泉さんが、その経験を麻原の説く物語(意味世界)に即して了解しなかったからであります。彼は精神科医の分析を受けたり、東洋医学の先生に説明を受けたりして、ヨガによって起こったエネルーギの噴出や光明体験は、無理な呼吸法によって引き起こされた大脳の生理現象だ、と頷きます。同じ経験でも、それを受け取る文脈によって、解脱ともなれば錯覚ともなるのです。(注一七)
ついでですが、サリンをまいて死刑を求刑されている人に広瀬健一という人がいます。彼は早稲田大学で素粒子論や超伝導の研究をして将来を嘱望された科学者でした。この人は今、牢獄の中で必死に自分の過ちを総括しております。その彼が「そうした神秘体験は、実は修行やワークによってほとんど睡眠をとらないほど肉体を酷使したり、無理な呼吸法をとったりしたために起きた大脳生理学上の現象だったのではないか」と言っています。(注一八)
ついでですが、サリンをまいて死刑を求刑されている人に広瀬健一という人がいます。彼は早稲田大学で素粒子論や超伝導の研究をして将来を嘱望された科学者でした。この人は今、牢獄の中で必死に自分の過ちを総括しております。その彼が「そうした神秘体験は、実は修行やワークによってほとんど睡眠をとらないほど肉体を酷使したり、無理な呼吸法をとったりしたために起きた大脳生理学上の現象だったのではないか」と言っています。(注一八)
「オウム」、 ─── 抑圧された無意識の逆襲
大泉さんには『マレーバクは悪夢を見ないー夢をコントロールする民族セノイへの旅』(注一九)というおもしろい本があります。彼はその中で、人間の見る夢とか妖怪の話とかは、人間が社会生活を営む上で「悪」として抑圧してしまったものを陰でこっそり復活させる、一種の代償行為である、とそんなようなことを言っていたと思います。
たしかに科学が発達し、表社会は合理一辺倒になったのに、テレビをつければ、占いだの超能力だの祟りだのと、魑魅魍魎が跋扈した中世に戻ってしまったような感であります。正しいこと、合理的なことだけでは、人間は息苦しいのです。戦後をリードしてきた知性はそうしたことをバカバカしいと一言のもとに切り捨てますが、切り捨てただけでは人びとの息苦しさは解消されない。後で詳しく触れますが、「オウム」は現代が生んだモンスターであると思います。現代は人類がかって経験したことのない程の「超合理社会」「超建前社会」になっていると思います。そうした中で抑圧され行き場を失った人間の憎悪や有象無象の非合理な感情が、「オウム」となって噴出した、とも言えそうです。
夢と妖怪と宗教、一見関係なく見えそうな事柄ですが、そこには通底するものがあります。それは人間の理性から否定された無意識だということです。宗教とは、「理性によって抑圧された無意識を解放し、全的ないのちを回復しようとする運動」とも言えるのではないでしょうか。
大泉さんは新しき時代の思想家だと思います。人間が抱える無意識を(仏教でいう煩悩のことです)「悪」として理性で押さえ込むのでもなく、また「オウム」のようにデモニッシュに解き放つのでもなく、真に正しい解放の道を探しています。戦後五〇年が経ち、「東大」や「岩波」で象徴された理性第一主義の限界がハッキリしてきました。人間の非合理な感情を、理性によって「悪」として押さえ込むのが正しい方法ではない。人間の非合理な感情には、いのちが全的になろうとするシグナルが隠されている。医療においても、病気を悪としてそれに打ち勝とうとする西洋医学から、病気は健康を回復しようとするいのちの行為だと受けとめる東洋医学へ、関心が移ってきていると思います。大泉さんもそういうことに気づいた新しい世代の思想家だと思います。
なぜ、彼が人間の無意識、特に宗教の問題に眼を向けるようになったかというと、実は彼には「エホバの証人」の研究生であった、という原体験があるからです。彼は小学校四年から中学二年まで、ハルマゲドンが近いんだからと学校を放って、親と一緒に布教についてまわっています。ところが地球最後の日であるはずの一九七五年がきても、何も起こらなかった。それで「エホバの証人」は分裂するんです。来なかったのは予言が嘘だったからだという人々と、もう一つの人々は別に理由があるといって、地球の最後を一九九九年に置きなおす人と。大泉さんはこの時「エホバの証人」を離れるのですが、「エホバの証人」とは何だったのか、それにこだわり続けております。そのこだわりの中で、「オウム」もまた新しい課題となったのだと思います。
たしかに科学が発達し、表社会は合理一辺倒になったのに、テレビをつければ、占いだの超能力だの祟りだのと、魑魅魍魎が跋扈した中世に戻ってしまったような感であります。正しいこと、合理的なことだけでは、人間は息苦しいのです。戦後をリードしてきた知性はそうしたことをバカバカしいと一言のもとに切り捨てますが、切り捨てただけでは人びとの息苦しさは解消されない。後で詳しく触れますが、「オウム」は現代が生んだモンスターであると思います。現代は人類がかって経験したことのない程の「超合理社会」「超建前社会」になっていると思います。そうした中で抑圧され行き場を失った人間の憎悪や有象無象の非合理な感情が、「オウム」となって噴出した、とも言えそうです。
夢と妖怪と宗教、一見関係なく見えそうな事柄ですが、そこには通底するものがあります。それは人間の理性から否定された無意識だということです。宗教とは、「理性によって抑圧された無意識を解放し、全的ないのちを回復しようとする運動」とも言えるのではないでしょうか。
大泉さんは新しき時代の思想家だと思います。人間が抱える無意識を(仏教でいう煩悩のことです)「悪」として理性で押さえ込むのでもなく、また「オウム」のようにデモニッシュに解き放つのでもなく、真に正しい解放の道を探しています。戦後五〇年が経ち、「東大」や「岩波」で象徴された理性第一主義の限界がハッキリしてきました。人間の非合理な感情を、理性によって「悪」として押さえ込むのが正しい方法ではない。人間の非合理な感情には、いのちが全的になろうとするシグナルが隠されている。医療においても、病気を悪としてそれに打ち勝とうとする西洋医学から、病気は健康を回復しようとするいのちの行為だと受けとめる東洋医学へ、関心が移ってきていると思います。大泉さんもそういうことに気づいた新しい世代の思想家だと思います。
なぜ、彼が人間の無意識、特に宗教の問題に眼を向けるようになったかというと、実は彼には「エホバの証人」の研究生であった、という原体験があるからです。彼は小学校四年から中学二年まで、ハルマゲドンが近いんだからと学校を放って、親と一緒に布教についてまわっています。ところが地球最後の日であるはずの一九七五年がきても、何も起こらなかった。それで「エホバの証人」は分裂するんです。来なかったのは予言が嘘だったからだという人々と、もう一つの人々は別に理由があるといって、地球の最後を一九九九年に置きなおす人と。大泉さんはこの時「エホバの証人」を離れるのですが、「エホバの証人」とは何だったのか、それにこだわり続けております。そのこだわりの中で、「オウム」もまた新しい課題となったのだと思います。
ヨガ ー 病める身体 ー
さて、「オウム」が行ったヨガはどんなものであったか、加納秀一という人の本によってみます。(注二〇)まず呼吸法というのがあります。十五回ぐらい普通の深呼吸を繰り返した後、スーッと全ての息を吐き出して、そこで息をそのまま止めてしまう。加納さんによると、脂汗を流しながら三分ぐらい耐えに耐えて、最後に息を吸うんだそうです。今度は力一杯吸って、それを吐かずに脂汗を流す。こういう事を一日何時間もするわけです。それから逆さになったり、いろんなポーズをするそうです。
だいたい呼吸法というのは、肉体が生きていることの原初的な確認だと、高橋さんは言っております。高橋さんは、野辺山の宇宙電波観測所で、今から一五〇億年前のビッグバンの時に生じた電波の痕跡を見て、自分の存在は宇宙のはじめに繋がっていることに気づき深い感動を覚えたそうです。それは、「宗教的な言葉ですと、すべてのものは祝福されているんですよというのに通じるような感覚」だと言われています。ほとんど回心に近い経験だと思います。この時の電波も、ピクン、ピクンと脈打っているんですね。(注二一)
また、「いのち」という日本語は「息」を意味する「い」と「勢い」を意味する「ち」とそれを繋ぐ「の」で出来ているそうです。いのちの原点に「息をする」ということがあるのでしょう。
彼らはこうした呼吸法などを激しく繰り返すうちに、彼らのいうクンダリニー覚醒なるものを経験します。それは自分の身体の中を熱エネルギーが駆け抜けたり、恍惚となってしまう程の光を全身に浴びる神秘体験のようです。これは「オウム」の人たちにとって圧倒的な出来事なんで、これによって自分は解脱に一歩近づいたと了解してしまうのです。これがなければ、次の段階に進むことはなかったと思うんです。
だいたい呼吸法というのは、肉体が生きていることの原初的な確認だと、高橋さんは言っております。高橋さんは、野辺山の宇宙電波観測所で、今から一五〇億年前のビッグバンの時に生じた電波の痕跡を見て、自分の存在は宇宙のはじめに繋がっていることに気づき深い感動を覚えたそうです。それは、「宗教的な言葉ですと、すべてのものは祝福されているんですよというのに通じるような感覚」だと言われています。ほとんど回心に近い経験だと思います。この時の電波も、ピクン、ピクンと脈打っているんですね。(注二一)
また、「いのち」という日本語は「息」を意味する「い」と「勢い」を意味する「ち」とそれを繋ぐ「の」で出来ているそうです。いのちの原点に「息をする」ということがあるのでしょう。
彼らはこうした呼吸法などを激しく繰り返すうちに、彼らのいうクンダリニー覚醒なるものを経験します。それは自分の身体の中を熱エネルギーが駆け抜けたり、恍惚となってしまう程の光を全身に浴びる神秘体験のようです。これは「オウム」の人たちにとって圧倒的な出来事なんで、これによって自分は解脱に一歩近づいたと了解してしまうのです。これがなければ、次の段階に進むことはなかったと思うんです。
極限修行
こうした強烈な経験が起こるのは、「極限修行」とか「狂気の集中修行」とか「死の修行」とか「独房修行」とか、常軌を逸した苦行によってであります。たとえば加納さんが経験した極限修行というと、基本的に睡眠時間がない。先の呼吸法やヨガのポーズや瞑想や教典読誦を何ヶ月も続ける。その間、食事は「オウム」食一食で、彼の場合二ヶ月の修行で五六㌔の体重が四三㌔になったといってます。(注二二)
こうした激しさは「オウム」に一貫することで、身体性を蔑視した観念社会の病理だと思います。たとえば「オウム」には、全員が一斉に眠るという意味での「夜」はなかった。年中、二十四時間営業です。修行でもワークでも、疲れた時にその場でごろっと寝るだけです。だから「オウム」の人は睡眠不足による交通事故を度々起こしています。
激しさは入信のときから始まります。入信の義務は「オウム」のビデオを九十七本見る、「オウム」の本を七十七冊読む、それから七千回マントラを称える。出家になるとまず最初に延べ六百時間の五体投地をする。六百時間の五体投地とは一日三~四時間の睡眠で十六時間、延べつ間くなく「オーム、グルとシヴァ神に帰依します。わたくし何某をすみやかに解脱に導いてください」と言って、五体投地をする。それを四、五十日かけないと六百時間に行き着かないのです。その間、「オウム」食と野菜をちょっと食べるだけです。
こうした常軌を逸した苦行に耐えた者にしてはじめて、クンダリニー覚醒なるものが起こります。少数の者だけしかできないということも、「オウム」の教えを深遠なるものと錯覚させる要因になったようです。
こうした激しさは「オウム」に一貫することで、身体性を蔑視した観念社会の病理だと思います。たとえば「オウム」には、全員が一斉に眠るという意味での「夜」はなかった。年中、二十四時間営業です。修行でもワークでも、疲れた時にその場でごろっと寝るだけです。だから「オウム」の人は睡眠不足による交通事故を度々起こしています。
激しさは入信のときから始まります。入信の義務は「オウム」のビデオを九十七本見る、「オウム」の本を七十七冊読む、それから七千回マントラを称える。出家になるとまず最初に延べ六百時間の五体投地をする。六百時間の五体投地とは一日三~四時間の睡眠で十六時間、延べつ間くなく「オーム、グルとシヴァ神に帰依します。わたくし何某をすみやかに解脱に導いてください」と言って、五体投地をする。それを四、五十日かけないと六百時間に行き着かないのです。その間、「オウム」食と野菜をちょっと食べるだけです。
こうした常軌を逸した苦行に耐えた者にしてはじめて、クンダリニー覚醒なるものが起こります。少数の者だけしかできないということも、「オウム」の教えを深遠なるものと錯覚させる要因になったようです。
第四章 「オウム」の軌跡
ヨガ道場「オウム神仙の会」
よくよく考えてみると、「オウム」というのは実にわずかな時間の出来事なんですね。麻原が「オウム神仙の会」を設立したのが一九八四年。地下鉄にサリンを撒いたのが一九九五年。十年ちょっとの出来事です。たったこれだけの時間で、あれだけのことをやってのけたとは、驚き入るばかりです。なぜでしょうか? しばらく島薗進氏の『オウム真理教の奇跡』(注二三)や滝本太郎氏の年表(注二四)によって「オウム」の足跡をたどってみることにします。
麻原彰晃が宗教に関心を寄せだしたのは【一九七七年】、二十二歳頃と言われています。桐山靖雄の『阿含宗』に入信し、千日間に亘る千座行というものによってクンダリニー覚醒なるものを体験したそうです。
【一九八四年】二十九歳で、阿含宗から離れて、渋谷にヨガの道場「オウム神仙の会」を開きます。この頃はヨガによる健康法が中心だったようです。
【一九八五年】「空中浮揚」を体験。その[四月]か[五月]に三浦海岸で「アブラケツノミコトを任ずる」というシヴァ神のお告げを受けたと言います。それは超能力を得た民による理想世界すなわちシャンバラ王国を築けとの命令だというのです。
[十月]、「空中浮揚」の写真とともに、『ムー』や『トワイライトゾーン』というオカルト雑誌に華々しく登場し、連載を始めます。この頃から自分を救世主と見立てた言辞が増えていきます。
【一九八六年】[三月]に『超能力秘密の開発法』を出版。[夏]、ヒマラヤで「最終解脱」を得たと宣言します。教説も次第に自己の解脱から他者の救済に、つまり小乗から大乗へと力点を移していっております。
【一九八七年】「オウム真理教」と名前を変更、信者数九〇〇人。機関誌『マハーヤーナ』を創刊。
麻原彰晃が宗教に関心を寄せだしたのは【一九七七年】、二十二歳頃と言われています。桐山靖雄の『阿含宗』に入信し、千日間に亘る千座行というものによってクンダリニー覚醒なるものを体験したそうです。
【一九八四年】二十九歳で、阿含宗から離れて、渋谷にヨガの道場「オウム神仙の会」を開きます。この頃はヨガによる健康法が中心だったようです。
【一九八五年】「空中浮揚」を体験。その[四月]か[五月]に三浦海岸で「アブラケツノミコトを任ずる」というシヴァ神のお告げを受けたと言います。それは超能力を得た民による理想世界すなわちシャンバラ王国を築けとの命令だというのです。
[十月]、「空中浮揚」の写真とともに、『ムー』や『トワイライトゾーン』というオカルト雑誌に華々しく登場し、連載を始めます。この頃から自分を救世主と見立てた言辞が増えていきます。
【一九八六年】[三月]に『超能力秘密の開発法』を出版。[夏]、ヒマラヤで「最終解脱」を得たと宣言します。教説も次第に自己の解脱から他者の救済に、つまり小乗から大乗へと力点を移していっております。
【一九八七年】「オウム真理教」と名前を変更、信者数九〇〇人。機関誌『マハーヤーナ』を創刊。
最初の殺人 ーポアの思想の誕生ー
【一九八八年】[八月]、富士山総本部が落成。[九月]、精神に異常をきたした真島照之という人を水につけて殺してしまいます。
【一九八九年】[二月]、田口修治という人が教団批判をして出家をとりやめると言いだします。これを聞いた麻原は、「このまま帰らせたら去年人を殺したことを話してしまう。それでは田口が悪業を積むことになる。悪業を積んで地獄落ちになるから田口をポアしろ」と命じます。真鍋さんの時は事故死的な面もありましたが、田口さんは明確な意志による殺人です。
この頃より、「タントラヴァジラヤーナ=秘密金剛乗」ということが言われだしました。また『ノストラダムスの予言』や『ヨハネ黙示録』の解読などが熱っぽく語られだし、ハルマゲドンというおどろおどろしい物語が登場してきます。それにあわせて、自分たちは人類を救うために立ちあがった真理の戦士だから、何をやっても許されるという感覚が広がっていきます。殺人さえも、その人を悪業から救うポアだと、話がどんどんエスカレートしていきます。
小乗から大乗、大乗から秘密金剛乗、こうした進展は論理的必然性があって出て来たかというと、必ずしもそうではない、というのが大方の見方です。実は、解脱とか人類救済とかの心地よい言葉の下に隠されていた憎悪が本能のままに牙を剥いてしまって、つい殺人事件を起こしてしまった、それを取り繕うためにタントラヴァジラヤーナなる教説が出て来たと、こう考えてみるべきだと思います。
田口さんを殺してから歯止めがなくなりました。[十一月]には坂本堤弁護士一家三人を殺しています。
【一九九〇年】[二月]、真理党を結成し衆議院選に二五人が立候補するも全員、落選します。麻原が二〇代の前半にもっていた東大→政治家→総理大臣の夢が、まだ払拭されていなかったようです。客観的に見れば当選できるはずがないのですが、麻原は国家の陰謀で落とされたと言い訳します。
[四月]、オースチン彗星の接近で日本が危ないと信者二千人余りを連れて石垣島に避難。そこで在家信者に出家を迫っています。またその間、国会周辺にポツリヌス菌を噴霧しております。恐ろしいまでの身勝手な論理です。この時はまだ科学力が弱く失敗しておりますが、サリンを思いつくのは時間の問題です。
[十月]、波野村に建設を始めていた教団施設に熊本県警が強制捜査に入ります。
【一九八九年】[二月]、田口修治という人が教団批判をして出家をとりやめると言いだします。これを聞いた麻原は、「このまま帰らせたら去年人を殺したことを話してしまう。それでは田口が悪業を積むことになる。悪業を積んで地獄落ちになるから田口をポアしろ」と命じます。真鍋さんの時は事故死的な面もありましたが、田口さんは明確な意志による殺人です。
この頃より、「タントラヴァジラヤーナ=秘密金剛乗」ということが言われだしました。また『ノストラダムスの予言』や『ヨハネ黙示録』の解読などが熱っぽく語られだし、ハルマゲドンというおどろおどろしい物語が登場してきます。それにあわせて、自分たちは人類を救うために立ちあがった真理の戦士だから、何をやっても許されるという感覚が広がっていきます。殺人さえも、その人を悪業から救うポアだと、話がどんどんエスカレートしていきます。
小乗から大乗、大乗から秘密金剛乗、こうした進展は論理的必然性があって出て来たかというと、必ずしもそうではない、というのが大方の見方です。実は、解脱とか人類救済とかの心地よい言葉の下に隠されていた憎悪が本能のままに牙を剥いてしまって、つい殺人事件を起こしてしまった、それを取り繕うためにタントラヴァジラヤーナなる教説が出て来たと、こう考えてみるべきだと思います。
田口さんを殺してから歯止めがなくなりました。[十一月]には坂本堤弁護士一家三人を殺しています。
【一九九〇年】[二月]、真理党を結成し衆議院選に二五人が立候補するも全員、落選します。麻原が二〇代の前半にもっていた東大→政治家→総理大臣の夢が、まだ払拭されていなかったようです。客観的に見れば当選できるはずがないのですが、麻原は国家の陰謀で落とされたと言い訳します。
[四月]、オースチン彗星の接近で日本が危ないと信者二千人余りを連れて石垣島に避難。そこで在家信者に出家を迫っています。またその間、国会周辺にポツリヌス菌を噴霧しております。恐ろしいまでの身勝手な論理です。この時はまだ科学力が弱く失敗しておりますが、サリンを思いつくのは時間の問題です。
[十月]、波野村に建設を始めていた教団施設に熊本県警が強制捜査に入ります。
地球最終戦争へ
【一九九一年】、だんだんと「毒ガス攻撃をされている」とか「ハルマゲドンは近い」とか、理想郷をつくることより地球最終戦争へとトーンが変わっていきます。
【一九九二年】[三月]、信者三〇〇人を連れてロシア救済ツアー。ソビエト崩壊後の混乱したロシアにコネクションを作り、最高会議議長や副大統領まで接近しています。そのかげで、MIー17という三〇人乗りの軍事ヘリコプターを買ったり、自動小銃を買ったりしています。建設省長官だった早川紀代秀の手帳には原爆はいくら、船はいくら、戦車一輌はいくらというメモまであったといいます。
[夏]、炭素菌の培養を指示。
【一九九三年】[三月]、毒ガスの研究と自動小銃千丁の製造を指示。
[七月]、亀戸本部で炭素菌を噴霧するも失敗。炭素菌というのは食中毒や下痢を起こさせるというようなしろものではなくて、純粋に殺人のための細菌兵器です。これにはとうとう逮捕を逃れきった法王官房の長官だった石川公一や外報部長の上祐史浩も関係しております。
[十一月]、サリンが完成。[十二月]、サリンでの池田大作氏の殺害を図るも、噴霧器がお粗末で失敗します。
【一九九四年】[一月]落田さん殺害。
[二月]、麻原は幹部を連れて中国に行き、「一九九七年に日本の王になるヴィジョンを見た、これは神の示唆である。二〇〇〇年には世界の王になる。」と秘密の説法をしております。九七年という具体的な日時が設定され、いよいよ教団の中が戦争に向けて一直線の状況になっていきます。
[四月]、銃弾千万発の製造指示。第七サティアンに七〇トンのサリンを作るためのプラント建設を開始します。七〇トンというサリンは、どのようなものかといえば、山手線の中の人間を殺すのに必要なのがだいたい七トンだそうです。その十倍で七〇という数字が出てくるのだそうです。本気だということです。
[五月]、LSDの製造に成功。薬物を使ったイニシエイションを開始。それから日雇い労務者たちをだまして山中で武装訓練を始めるとともに、自衛隊内への工作を強めていきます。
このころからたくさんの人の命を狙います。[五月]、オウム真理教被害対策弁護団長だった滝本太郎さんをサリンで殺そうとし、未遂に終わります。
[六月]、松本サリン事件です。これは行き当たりばったりの、ほとんど無差別殺人です。麻原も主だった幹部も「ハルマゲドンの物語」一生懸命で、それこそ「よい子」の真面目さでサリンを撒いております。「出家」にしろ「極限修行」にしろ、自分自身の人間性を抑圧していくうちに、他者への共感がなくなってしまったのでしょう。
[九月]、江川紹子さんにホスゲンをまく。[十二月]、小林よしのりさんに対しVX溶液での殺人未遂。大阪の会社員もスパイ容疑でVXで殺しています。内部ではスパイチェックなどの拷問やリンチ殺人も次々起こしています。
数え切れぬほどの犯罪が白昼堂々と行われています。いったい日本の警察は、どうしていたのでしょうか。全く知らなかったのでしょうか。もしそうなら、あまりにお粗末です。それとも何か意図があって泳がしていたのでしょうか。もしそうなら、実に恐ろしい意図です。
【一九九二年】[三月]、信者三〇〇人を連れてロシア救済ツアー。ソビエト崩壊後の混乱したロシアにコネクションを作り、最高会議議長や副大統領まで接近しています。そのかげで、MIー17という三〇人乗りの軍事ヘリコプターを買ったり、自動小銃を買ったりしています。建設省長官だった早川紀代秀の手帳には原爆はいくら、船はいくら、戦車一輌はいくらというメモまであったといいます。
[夏]、炭素菌の培養を指示。
【一九九三年】[三月]、毒ガスの研究と自動小銃千丁の製造を指示。
[七月]、亀戸本部で炭素菌を噴霧するも失敗。炭素菌というのは食中毒や下痢を起こさせるというようなしろものではなくて、純粋に殺人のための細菌兵器です。これにはとうとう逮捕を逃れきった法王官房の長官だった石川公一や外報部長の上祐史浩も関係しております。
[十一月]、サリンが完成。[十二月]、サリンでの池田大作氏の殺害を図るも、噴霧器がお粗末で失敗します。
【一九九四年】[一月]落田さん殺害。
[二月]、麻原は幹部を連れて中国に行き、「一九九七年に日本の王になるヴィジョンを見た、これは神の示唆である。二〇〇〇年には世界の王になる。」と秘密の説法をしております。九七年という具体的な日時が設定され、いよいよ教団の中が戦争に向けて一直線の状況になっていきます。
[四月]、銃弾千万発の製造指示。第七サティアンに七〇トンのサリンを作るためのプラント建設を開始します。七〇トンというサリンは、どのようなものかといえば、山手線の中の人間を殺すのに必要なのがだいたい七トンだそうです。その十倍で七〇という数字が出てくるのだそうです。本気だということです。
[五月]、LSDの製造に成功。薬物を使ったイニシエイションを開始。それから日雇い労務者たちをだまして山中で武装訓練を始めるとともに、自衛隊内への工作を強めていきます。
このころからたくさんの人の命を狙います。[五月]、オウム真理教被害対策弁護団長だった滝本太郎さんをサリンで殺そうとし、未遂に終わります。
[六月]、松本サリン事件です。これは行き当たりばったりの、ほとんど無差別殺人です。麻原も主だった幹部も「ハルマゲドンの物語」一生懸命で、それこそ「よい子」の真面目さでサリンを撒いております。「出家」にしろ「極限修行」にしろ、自分自身の人間性を抑圧していくうちに、他者への共感がなくなってしまったのでしょう。
[九月]、江川紹子さんにホスゲンをまく。[十二月]、小林よしのりさんに対しVX溶液での殺人未遂。大阪の会社員もスパイ容疑でVXで殺しています。内部ではスパイチェックなどの拷問やリンチ殺人も次々起こしています。
数え切れぬほどの犯罪が白昼堂々と行われています。いったい日本の警察は、どうしていたのでしょうか。全く知らなかったのでしょうか。もしそうなら、あまりにお粗末です。それとも何か意図があって泳がしていたのでしょうか。もしそうなら、実に恐ろしい意図です。
地下鉄サリン事件
【一九九五年】元旦、読売新聞が「上九一色村の土壌からサリン中間生成物を検出した」とスクープします。ようやく警察が動くかと思ったら、一月十七日に阪神大震災が起こったために、強制捜査はのびてしまいました。三月に入り、強制捜査が来るという情報を手にした「オウム」は、その二日前の[三月二〇日]に地下鉄にサリンをまくという前代未聞の無差別大量殺人事件を起こしてしまったのです。この時の出家信者は一六〇〇人、在家信者は日本に一万五千人、ロシアに三万人とも言われています。
何ともおぞましいというか、おどろおどろしい話をしてまいりましたけれど、昔のように、たとえば戦国時代のように殿様一人を倒せば国家が取れるという時代ではなくて、まがりなりにも国民の合意という形でできあがった近代国家を、別に革命的気運が盛り上がったときでない平時に、自分たちでハルマゲドンを起こして新しい国家を樹立するという発想の異常さに、呆然としてしまうばかりです。
事実、法皇官房長官の石川公一は、麻原彰晃を「神聖法皇」とする祭政一致の独裁国家を想定した「基本律草案」を作っています。(注二五)
「オウム」の事件は日本の歴史上だけでなく世界の歴史上いまだかってなかった出来事であります。歴史上繰り返されてきた革命運動は、民衆の意を体して腐敗した権力を打倒するというものでした。つまり、この世の中の「悪」を倒し、変わってこの世に「善」を打ち立てようというものでした。ところが「オウム」は、権力者も民衆も全て殺し尽くそうとしました。言い換えれば、この世そのものを否定しております。たとえそれが妄想であろうとも、「オウム」は人類史上はじめて「この世」の全てを否定した革命運動だったと思います。
何ともおぞましいというか、おどろおどろしい話をしてまいりましたけれど、昔のように、たとえば戦国時代のように殿様一人を倒せば国家が取れるという時代ではなくて、まがりなりにも国民の合意という形でできあがった近代国家を、別に革命的気運が盛り上がったときでない平時に、自分たちでハルマゲドンを起こして新しい国家を樹立するという発想の異常さに、呆然としてしまうばかりです。
事実、法皇官房長官の石川公一は、麻原彰晃を「神聖法皇」とする祭政一致の独裁国家を想定した「基本律草案」を作っています。(注二五)
「オウム」の事件は日本の歴史上だけでなく世界の歴史上いまだかってなかった出来事であります。歴史上繰り返されてきた革命運動は、民衆の意を体して腐敗した権力を打倒するというものでした。つまり、この世の中の「悪」を倒し、変わってこの世に「善」を打ち立てようというものでした。ところが「オウム」は、権力者も民衆も全て殺し尽くそうとしました。言い換えれば、この世そのものを否定しております。たとえそれが妄想であろうとも、「オウム」は人類史上はじめて「この世」の全てを否定した革命運動だったと思います。
第五章 「善」と「悪」とのドッキング
麻原のルサンチマン
麻原が「オウム神仙の会」を立ち上げてから地下鉄サリン事件まで、たった十一年でした。わずか十一年で、ヨガによる人間探求の会が、一万数千人を巻き込んだ世界最終戦争(ハルマゲドン)へと変質しております。なぜこんな事になったのだろうか、そのことを明らかにするためには、まず麻原とは何者なのかを考えてみる必要があると思います。
麻原彰晃の本名は松本智津夫といいます。熊本県八代市に、七人兄弟の六番目の子として生まれました。お父さんは畳職人で、家は貧しく借家生活でした。そのうえ先天性緑内障で、左眼はほとんど見えず右目も〇・二ぐらいの弱視だったそうです。それでお父さんから「両方とも見えないことにしろ」と言われて、お金のかからぬ熊本県立盲学校に入れられます。貧しさや眼の障害は世間から捨てられたこととして、盲学校にいれられたことは親から捨てられたこととして、智津夫少年には感じられたのではないでしょうか。コンプレックスとルサンチマン、この二つが松本智津夫の原点になっているように思います。
彼は盲学校の寄宿舎で七歳から二十歳まで過ごします。そこは、あってはならぬ事なのですが、世間から差別され隔絶された閉鎖社会だったのではないでしょうか。自尊心の強く生まれた智津夫少年には耐え難いことだったと思います。その鬱憤を何とか晴らそうと、時にはおもねり時には威喝して、先生や同級生に自分を認めてもらおうとしております。結局、彼は、もがけばもがく程みんなから疎まれてしまいました。
彼は演劇が好きで、高等部に進むと自ら脚本を書き、自作自演するようになります。もちろん主役は自分で、ヒロインも自分で決めます。文化祭では、悲劇のヒーローを演じる陶酔した松本智津夫少年があったと言います。(注二六)
彼は、盲学校で取った鍼灸師だけでは満足できなかったようです。強烈な自尊心(生きようとする本能の激しさといってもよい)をもって生まれてきた彼の中には、自分の前に立ちはだかった世間に対し、親に対し、そして眼が見えないという障害のある自分の身体に対し、燃え上がるような恨みが渦巻いていたのではないでしょうか。世間を自分の下に跪かせてやるには何がいいか、上京した彼は東大を目指して受験勉強を始めます。東大合格、そして政治家になる夢を親しい人に語っています。しかし盲学校の授業では受験の基礎もなかったでしょうし、親の支援もなく、眼も不自由です。そのうえ知子夫人と出会い、結婚、子供も生まれます。また一つ挫折しました。
まともな形では世間に太刀打ちできなくなった彼が始めたのが、「漢方亜細亜堂薬局」です。受験には誤魔化しがききませんでしたが、薬の商売となれば曖昧な部分があります。脚色一つで何とでもなると、麻原には思えたんではないでしょうか。彼は東洋医学だとか仙道だとかを研究して、怪しい薬を造り、誇大な宣伝をして儲けだしました。ところが薬事法違反で逮捕されます。また挫折です。
前科者になってはもうこの世では認められません。続いて彼は、この世の外、つまり宗教の世界に活路を見いだそうとしだします。決してへこたれない彼の本能が、薬よりももっと曖昧な宗教をかぎつけた、と言ったらいい過ぎでしょうか。
すでに見てきたように、彼は宗教の世界においてようやく自分を認めさせることに成功しました。松本智津夫あらため「麻原彰晃尊師」の誕生です。ところが彼はこれだけではまだ満足できなかった。「尊師」というのは仲間内だけのこと、世間の全部を自分に跪かせようと、つまり「神聖法皇」になろうとして、ハルマゲドんまで突っ走ってしまいました。眼が見えなくなってしまっていた麻原にとっては、現実の世界と、盲学校の文化祭で悲劇のヒーロを演じた舞台とが、重なっていたのかも知れません。そして獄に繋がれた今も、彼は妄想の中で、磔になったイエス・キリストに自分自身を重ねているように思えてなりません。
麻原彰晃の本名は松本智津夫といいます。熊本県八代市に、七人兄弟の六番目の子として生まれました。お父さんは畳職人で、家は貧しく借家生活でした。そのうえ先天性緑内障で、左眼はほとんど見えず右目も〇・二ぐらいの弱視だったそうです。それでお父さんから「両方とも見えないことにしろ」と言われて、お金のかからぬ熊本県立盲学校に入れられます。貧しさや眼の障害は世間から捨てられたこととして、盲学校にいれられたことは親から捨てられたこととして、智津夫少年には感じられたのではないでしょうか。コンプレックスとルサンチマン、この二つが松本智津夫の原点になっているように思います。
彼は盲学校の寄宿舎で七歳から二十歳まで過ごします。そこは、あってはならぬ事なのですが、世間から差別され隔絶された閉鎖社会だったのではないでしょうか。自尊心の強く生まれた智津夫少年には耐え難いことだったと思います。その鬱憤を何とか晴らそうと、時にはおもねり時には威喝して、先生や同級生に自分を認めてもらおうとしております。結局、彼は、もがけばもがく程みんなから疎まれてしまいました。
彼は演劇が好きで、高等部に進むと自ら脚本を書き、自作自演するようになります。もちろん主役は自分で、ヒロインも自分で決めます。文化祭では、悲劇のヒーローを演じる陶酔した松本智津夫少年があったと言います。(注二六)
彼は、盲学校で取った鍼灸師だけでは満足できなかったようです。強烈な自尊心(生きようとする本能の激しさといってもよい)をもって生まれてきた彼の中には、自分の前に立ちはだかった世間に対し、親に対し、そして眼が見えないという障害のある自分の身体に対し、燃え上がるような恨みが渦巻いていたのではないでしょうか。世間を自分の下に跪かせてやるには何がいいか、上京した彼は東大を目指して受験勉強を始めます。東大合格、そして政治家になる夢を親しい人に語っています。しかし盲学校の授業では受験の基礎もなかったでしょうし、親の支援もなく、眼も不自由です。そのうえ知子夫人と出会い、結婚、子供も生まれます。また一つ挫折しました。
まともな形では世間に太刀打ちできなくなった彼が始めたのが、「漢方亜細亜堂薬局」です。受験には誤魔化しがききませんでしたが、薬の商売となれば曖昧な部分があります。脚色一つで何とでもなると、麻原には思えたんではないでしょうか。彼は東洋医学だとか仙道だとかを研究して、怪しい薬を造り、誇大な宣伝をして儲けだしました。ところが薬事法違反で逮捕されます。また挫折です。
前科者になってはもうこの世では認められません。続いて彼は、この世の外、つまり宗教の世界に活路を見いだそうとしだします。決してへこたれない彼の本能が、薬よりももっと曖昧な宗教をかぎつけた、と言ったらいい過ぎでしょうか。
すでに見てきたように、彼は宗教の世界においてようやく自分を認めさせることに成功しました。松本智津夫あらため「麻原彰晃尊師」の誕生です。ところが彼はこれだけではまだ満足できなかった。「尊師」というのは仲間内だけのこと、世間の全部を自分に跪かせようと、つまり「神聖法皇」になろうとして、ハルマゲドんまで突っ走ってしまいました。眼が見えなくなってしまっていた麻原にとっては、現実の世界と、盲学校の文化祭で悲劇のヒーロを演じた舞台とが、重なっていたのかも知れません。そして獄に繋がれた今も、彼は妄想の中で、磔になったイエス・キリストに自分自身を重ねているように思えてなりません。
弟子のルサンチマン
以上、麻原彰晃を通して、「オウム」事件を考えてみました。続いて、弟子たちの側から「オウム」事件を考えてみたいと思います。それというのも、「オウム」の事件は麻原彰晃が一人で脚本を書き、一人で演出した劇ではないからです。弟子たちはマインドコントロールされた操り人形だったように言われることもありますが、決してそんなことはありません。弟子たちもまた麻原と呼応しながら、ハルマゲドンの物語をつむいでいったのだと思います。もし麻原だけの妄想なら、空想小説で終わっています。麻原彰晃と弟子たちとが共鳴しあい次第に増幅していったから、妄想を現実化させてサリンを撒くということができたのです。
はじめに詳しく見てきたように、弟子たちの「オウム」への出家は一応、善意です。ところがその結論は無差別殺人という、極悪でした。出家は入口、事件は出口とするならば、途中でとんでもないものに変わってしまったことになります。
麻原と弟子たちが共有していた物語は、解脱であり人類の救済でありました。その美しい言葉のかげで、デモニッシュな感情が共鳴しあったように思います。それは何か、しばらく考えてみたいと思います。
弟子の多くは豊かな時代に育った子ども達です。彼らを取り巻く大人たち(親や先生やテレビの中から呼びかけてくる大人)は、民主主義の何たるかをよくわきまえていて、子供をとても大切にする人びとでした。よく勉強し、優しい子であれと、教えてくるのでした。彼らはそれに応えて「良き者たらん」というエートスを育んだのではないでしょうか。簡単に言えば、「育ちの良い子供たち」です。それに対し麻原には、身体の障害や貧困に対する恨みがあります。自分を邪魔者扱いした親への不信もあったと思います。彼はその意味で「育ちの悪い子」であります。
はじめに詳しく見てきたように、弟子たちの「オウム」への出家は一応、善意です。ところがその結論は無差別殺人という、極悪でした。出家は入口、事件は出口とするならば、途中でとんでもないものに変わってしまったことになります。
麻原と弟子たちが共有していた物語は、解脱であり人類の救済でありました。その美しい言葉のかげで、デモニッシュな感情が共鳴しあったように思います。それは何か、しばらく考えてみたいと思います。
弟子の多くは豊かな時代に育った子ども達です。彼らを取り巻く大人たち(親や先生やテレビの中から呼びかけてくる大人)は、民主主義の何たるかをよくわきまえていて、子供をとても大切にする人びとでした。よく勉強し、優しい子であれと、教えてくるのでした。彼らはそれに応えて「良き者たらん」というエートスを育んだのではないでしょうか。簡単に言えば、「育ちの良い子供たち」です。それに対し麻原には、身体の障害や貧困に対する恨みがあります。自分を邪魔者扱いした親への不信もあったと思います。彼はその意味で「育ちの悪い子」であります。
よい子の故に現世を憎む
育ちの良さと育ちの悪さ、優しさと恨み、ある意味では全く反対のものに見える両者がどこで一つになったのでしょうか。私見を述べさせてもらうと、良い子であろうとするが故に培ってしまった恨みがあるのだと思います。
親からも社会からも「よい子であれ」と願われて育てられたら、どうなるか。それによって存在全体がよい子になれるのならいいのだが、実は、よい子でなければならないという意識だけが育つのです。そしてある日、親の優しさをゆりかごにして純粋培養された意識が、突然、牙を剥く。自分に良い子であれと言い聞かせてきたこの社会こそ虚偽だらけではないかと。否そればかりではない、いい子いい子と言われてきたが、身体の奥深きところから噴出してくるエゴイスチックな自分をどうしたらいいのか。輸血された他人の血がもとのいのちを拒絶するように、正義の名で植え付けられた意識が生身の自分や社会を拒絶し始めるのです。ひとことで言えば、良い子は良い子であるが故に、現実社会や生身の自分が許せなくなったのだと思います。もちろん文句の一つや二つ言ってもビクともしない現実社会であり我が身であります。そうなると意識は、自分を苦しめるものとして、現実社会や我が身(実存)を憎み始めます。よい子であれと純粋培養されていますから、諦めたり逃げたりすることは卑怯だと、自分をトコトン追いつめます。いつしか良い子の中で、おそろしい程の憎悪が育ちあがってしまうのです。
親からも社会からも「よい子であれ」と願われて育てられたら、どうなるか。それによって存在全体がよい子になれるのならいいのだが、実は、よい子でなければならないという意識だけが育つのです。そしてある日、親の優しさをゆりかごにして純粋培養された意識が、突然、牙を剥く。自分に良い子であれと言い聞かせてきたこの社会こそ虚偽だらけではないかと。否そればかりではない、いい子いい子と言われてきたが、身体の奥深きところから噴出してくるエゴイスチックな自分をどうしたらいいのか。輸血された他人の血がもとのいのちを拒絶するように、正義の名で植え付けられた意識が生身の自分や社会を拒絶し始めるのです。ひとことで言えば、良い子は良い子であるが故に、現実社会や生身の自分が許せなくなったのだと思います。もちろん文句の一つや二つ言ってもビクともしない現実社会であり我が身であります。そうなると意識は、自分を苦しめるものとして、現実社会や我が身(実存)を憎み始めます。よい子であれと純粋培養されていますから、諦めたり逃げたりすることは卑怯だと、自分をトコトン追いつめます。いつしか良い子の中で、おそろしい程の憎悪が育ちあがってしまうのです。
グルと弟子との闇取引
井上嘉宏さんは「自分自身を木端微塵に破壊したい」と麻原に訴えています。村井秀夫は、「苦しみに満ちた現世を丸ごと消滅させたい」と呟いていたと言われています。それを聞いた部下は村井の中に「澄み切った狂気」を感じたそうです。
普通、自分の奥底に秘められているデモニッシュな無意識を表に出すことは出来ません。見れば発狂するかもしれないからです。麻原と村井それに新實あたりは、サリンを撒くことも含めてデモニッシュな世界をはっきりと意識化していたようです。(上祐史裕や石川公一らは、麻原らに悪魔を演じさせ、自分は障子の影からこっそり見ていた、そんなふうに思えます)。
でも多くの弟子たちは、憎悪を無意識の中に押さえ込んで、自分たちは人類の救済事業をしていると思っていた。そしてグルを疑わずグルに従いますという形で、麻原に自分の憎悪を解き放ってもらっていたのだと思います。弟子はグルに騙されたのではない。弟子がグルを利用した面もあるのです。これがグルと弟子との間にあった、無意識の闇取引の実体でないでしょうか。
ともあれ意識していたかいなかったかの違いはあっても、奥深いところで世間に対し自分に対し憎悪を発酵させていたのです。そしていつの日か現世にピリオドを打とうと思っていたのです。麻原の狂気は村井にもあったし、村井の狂気は「オウム」にいる人たちみんなが共有していた狂気でした。それでなければ、教団あげての武装化なんて出来たはずがありません。
このように全く方向が違ったルサンチマン、ある意味では麻原の冷たいルサンチマンと弟子たちの熱いルサンチマンが、サティアンという窓のない閉ざされた空間の中で共鳴し増幅し、ついに爆発してしまいました。
表向きは人類の未来を救うという、彼らに言わせれば「壮大で使命感に溢れた」正義の物語だったわけです。いつでも表向きは全部、正義です。その正義の物語を推進していったエネルギーは恐ろしいまでの恨み、正義の名によって抑圧された自然的生命の恨みではなかったのでしょうか。
ゴキブリを殺さぬ故にサリンを撒けた
普通、自分の奥底に秘められているデモニッシュな無意識を表に出すことは出来ません。見れば発狂するかもしれないからです。麻原と村井それに新實あたりは、サリンを撒くことも含めてデモニッシュな世界をはっきりと意識化していたようです。(上祐史裕や石川公一らは、麻原らに悪魔を演じさせ、自分は障子の影からこっそり見ていた、そんなふうに思えます)。
でも多くの弟子たちは、憎悪を無意識の中に押さえ込んで、自分たちは人類の救済事業をしていると思っていた。そしてグルを疑わずグルに従いますという形で、麻原に自分の憎悪を解き放ってもらっていたのだと思います。弟子はグルに騙されたのではない。弟子がグルを利用した面もあるのです。これがグルと弟子との間にあった、無意識の闇取引の実体でないでしょうか。
ともあれ意識していたかいなかったかの違いはあっても、奥深いところで世間に対し自分に対し憎悪を発酵させていたのです。そしていつの日か現世にピリオドを打とうと思っていたのです。麻原の狂気は村井にもあったし、村井の狂気は「オウム」にいる人たちみんなが共有していた狂気でした。それでなければ、教団あげての武装化なんて出来たはずがありません。
このように全く方向が違ったルサンチマン、ある意味では麻原の冷たいルサンチマンと弟子たちの熱いルサンチマンが、サティアンという窓のない閉ざされた空間の中で共鳴し増幅し、ついに爆発してしまいました。
表向きは人類の未来を救うという、彼らに言わせれば「壮大で使命感に溢れた」正義の物語だったわけです。いつでも表向きは全部、正義です。その正義の物語を推進していったエネルギーは恐ろしいまでの恨み、正義の名によって抑圧された自然的生命の恨みではなかったのでしょうか。
ゴキブリを殺さぬ故にサリンを撒けた
今でも残された多くの信者たちが、「ゴキブリさえ殺さぬ私たちがサリンなど撒くはずがない」と言います。「事実、撒いたんだ」と言われると、いかにも育ちの良さそうな荒木浩広報部長などはほとほと困ったような顔になり、「私には分からない深い意味があるはずだ」と思考停止に入ります。(注二七)
けれども私はこう思います。「ゴキブリを殺さぬが故にサリンがまけたのではないか」。殴ることもしない、ゴキブリを殺すことさえしないということと、人を殺すということは一見すると反対のことのように見えます。ところがそれは逆で、ゴキブリを殺す者は決して無差別な殺人はしないのではないか、そう思います。
例えば連合赤軍に、植垣さんという兵士の人がおりました。彼の手記を読んでみると、その心根の美しさに涙が出てきます。本当に育ちの良い人なんです。そんな人がなぜ人を殺すことになったのか。たぶん頭の中で純粋ということを追求しすぎたために、生身の人間がもつ弱さ、醜さを許せなくなったのではないでしょうか。
彼らはきたるべき未来の民衆のために命を投げ出すことを誓う。そして社会を捨てて革命の根拠地という異次元の空間を造ります。それは人間の自然性から乖離した観念的空間です。だからそこにあっては自然的な人間の存在を許せなくなってしまうのでしょう。実際に、連合赤軍のベースキャンプではイヤリング一つが人を殺す原因になっていきました。それも、本人が革命戦士となることを助けるための「総括」だという理屈でもって。「オウム」の「ポア」とそっくりの論理です。
私自身も一九七〇年前後に大学に身を置いていましたから、あの時の雰囲気を知っています。「民衆のため」ということが全ての価値基準でした。そこから大学解体とか自己否定という思想も出て来たと思います。ところが「民衆のため」と振りかざした当の本人たちが一番、軽蔑したのは民衆の代表であるはずの自分の親たちだったのです。民衆のためといったら、それなら親を愛せるかというと、そうではない。「民衆のため」ということを言えば言うほど、「わが子かわいさの故に本音をさらけ出す」エゴイスティックな親を軽蔑し憎んでしまったのでした。
さらには「連帯」をうたいながら、共に戦っている友人のちょとした考えの違いや漏れでる人間の悲しきエゴを容赦なく指弾してしまい、その一方では、自分の中に蠢いている嘘が他人にバレないかと恐れることになる。理性でもって誠実であろうとすればする程、お互いの関係はズタズタに切り裂かれていきました。ゲバ棒で流された血よりも、理性で流された血の方が、人々の魂に深い傷跡を残したのではないでしょうか。それが極度までいくと、連合赤軍になったり、「オウム」になったりしたんだと思います。
人間とはゴキブリを殺す存在なのです。罪深い存在なのです。それが人間の事実であり、自然なのです。その事実通りに暮らしていたら、サリンなんか決して撒かない存在なのです。ところが、ゴキブリを殺さぬという不自然さを選んだために、サリンを撒きたくなってしまったのです。これが人間の意識の闇であり、マジックです。人間とは、実は呪われた存在であるのです。このことをよく知り抜いていたのが、釈尊でありソクラテスであり孔子でありキリストだったのです。
けれども私はこう思います。「ゴキブリを殺さぬが故にサリンがまけたのではないか」。殴ることもしない、ゴキブリを殺すことさえしないということと、人を殺すということは一見すると反対のことのように見えます。ところがそれは逆で、ゴキブリを殺す者は決して無差別な殺人はしないのではないか、そう思います。
例えば連合赤軍に、植垣さんという兵士の人がおりました。彼の手記を読んでみると、その心根の美しさに涙が出てきます。本当に育ちの良い人なんです。そんな人がなぜ人を殺すことになったのか。たぶん頭の中で純粋ということを追求しすぎたために、生身の人間がもつ弱さ、醜さを許せなくなったのではないでしょうか。
彼らはきたるべき未来の民衆のために命を投げ出すことを誓う。そして社会を捨てて革命の根拠地という異次元の空間を造ります。それは人間の自然性から乖離した観念的空間です。だからそこにあっては自然的な人間の存在を許せなくなってしまうのでしょう。実際に、連合赤軍のベースキャンプではイヤリング一つが人を殺す原因になっていきました。それも、本人が革命戦士となることを助けるための「総括」だという理屈でもって。「オウム」の「ポア」とそっくりの論理です。
私自身も一九七〇年前後に大学に身を置いていましたから、あの時の雰囲気を知っています。「民衆のため」ということが全ての価値基準でした。そこから大学解体とか自己否定という思想も出て来たと思います。ところが「民衆のため」と振りかざした当の本人たちが一番、軽蔑したのは民衆の代表であるはずの自分の親たちだったのです。民衆のためといったら、それなら親を愛せるかというと、そうではない。「民衆のため」ということを言えば言うほど、「わが子かわいさの故に本音をさらけ出す」エゴイスティックな親を軽蔑し憎んでしまったのでした。
さらには「連帯」をうたいながら、共に戦っている友人のちょとした考えの違いや漏れでる人間の悲しきエゴを容赦なく指弾してしまい、その一方では、自分の中に蠢いている嘘が他人にバレないかと恐れることになる。理性でもって誠実であろうとすればする程、お互いの関係はズタズタに切り裂かれていきました。ゲバ棒で流された血よりも、理性で流された血の方が、人々の魂に深い傷跡を残したのではないでしょうか。それが極度までいくと、連合赤軍になったり、「オウム」になったりしたんだと思います。
人間とはゴキブリを殺す存在なのです。罪深い存在なのです。それが人間の事実であり、自然なのです。その事実通りに暮らしていたら、サリンなんか決して撒かない存在なのです。ところが、ゴキブリを殺さぬという不自然さを選んだために、サリンを撒きたくなってしまったのです。これが人間の意識の闇であり、マジックです。人間とは、実は呪われた存在であるのです。このことをよく知り抜いていたのが、釈尊でありソクラテスであり孔子でありキリストだったのです。
第六章 神なき時代の苦悩
「我思う、故に、我あり」
これまでとりとめもなく話したことを少し整理してみたいと思います。
まず「オウム」の人びとが抱えた課題ですが、それは「自己の解脱」と「人類の救済」でありました。「解脱」を願うところには、自分自身に対する、いきどまり感、不全感があります。また現代人が抱え込んだ「私探し」という重い課題があります。「人類の救済」というところには、神なき後に神の座に着いた人間がとうとうパンドラの箱を開けてしまったような、病んだ時代状況があります。末法とも、世紀末とも思わずにおれぬ時代状況がります。
こうした自身への不全感や私探しの旅、あるいは現状に絶望して理想社会を求めるということは、人間以外の生き物には起こりません。彼らは、身体の内から来る促しに従って生きるばかりです。人間でも自意識の未発達な幼子も即自的な存在といえると思います。ところが人間は、成長とともに意識を通して自己や世界を経験するようになります。つまり、意識はその本質として、身体や世界から離れていくようになっているのです。そういう意味では、こうした課題は今はじまったものではありません。意識存在として歩み始めた人間に宿命づけられた課題だったのです。
それに気づきそれの克服方法を明らかにしたのが、釈尊、ソクラテス、孔子、キリストたちだった言えると思います。彼らは一様に、人間の意識は自分を生かす世界(神、仏、天、つまり「超越者」)を畏れることを知らず、自分が一番偉いと錯覚する、実に愚かしく実に罪深いものなのだと、教えてくれたのです。人類は長いこと彼らの教えに順って、意識が自身や世界から乖離していく不幸から逃れることが出来ました。
ところが科学の成果を手に入れた人間は、自分の頭の上に置かれたその重しが鬱陶しくなってしまいました。そしてついにそれをひっくり返してしまう日が来たのです。それがデカルトの「我思う、故に、我あり」だと思います。とうとう人間は「神の僕」でなくなりました。このデカルトの叫びが百年、二百年とたつうちに、ヨーロッパ中にゆきとどきました。その結果、人間は物質的富を手に入れることが出来ました。その代わりに、存在の根拠を失った人間は、心の奥深くに不安を抱え込んでしまったのです。今では人間は、「自由であるべく呪われている」のです。
「私はどこから来て、どこへ行くのか、私とは何か?」「何のために私はこんな苦しみを受けねばならないのか?」、神なきところでは、いくら問い叫んでも答えはありません。だからニーチェは、神が死んだからには一人一人が「超人」にならねばならないと指摘しました。ところが出て来た「超人」は、ヒットラーという悪魔でした。
まず「オウム」の人びとが抱えた課題ですが、それは「自己の解脱」と「人類の救済」でありました。「解脱」を願うところには、自分自身に対する、いきどまり感、不全感があります。また現代人が抱え込んだ「私探し」という重い課題があります。「人類の救済」というところには、神なき後に神の座に着いた人間がとうとうパンドラの箱を開けてしまったような、病んだ時代状況があります。末法とも、世紀末とも思わずにおれぬ時代状況がります。
こうした自身への不全感や私探しの旅、あるいは現状に絶望して理想社会を求めるということは、人間以外の生き物には起こりません。彼らは、身体の内から来る促しに従って生きるばかりです。人間でも自意識の未発達な幼子も即自的な存在といえると思います。ところが人間は、成長とともに意識を通して自己や世界を経験するようになります。つまり、意識はその本質として、身体や世界から離れていくようになっているのです。そういう意味では、こうした課題は今はじまったものではありません。意識存在として歩み始めた人間に宿命づけられた課題だったのです。
それに気づきそれの克服方法を明らかにしたのが、釈尊、ソクラテス、孔子、キリストたちだった言えると思います。彼らは一様に、人間の意識は自分を生かす世界(神、仏、天、つまり「超越者」)を畏れることを知らず、自分が一番偉いと錯覚する、実に愚かしく実に罪深いものなのだと、教えてくれたのです。人類は長いこと彼らの教えに順って、意識が自身や世界から乖離していく不幸から逃れることが出来ました。
ところが科学の成果を手に入れた人間は、自分の頭の上に置かれたその重しが鬱陶しくなってしまいました。そしてついにそれをひっくり返してしまう日が来たのです。それがデカルトの「我思う、故に、我あり」だと思います。とうとう人間は「神の僕」でなくなりました。このデカルトの叫びが百年、二百年とたつうちに、ヨーロッパ中にゆきとどきました。その結果、人間は物質的富を手に入れることが出来ました。その代わりに、存在の根拠を失った人間は、心の奥深くに不安を抱え込んでしまったのです。今では人間は、「自由であるべく呪われている」のです。
「私はどこから来て、どこへ行くのか、私とは何か?」「何のために私はこんな苦しみを受けねばならないのか?」、神なきところでは、いくら問い叫んでも答えはありません。だからニーチェは、神が死んだからには一人一人が「超人」にならねばならないと指摘しました。ところが出て来た「超人」は、ヒットラーという悪魔でした。
「自殺するか、狂うか、宗教に入るか」
日本では明治維新でようやくあいた窓からヨーロッパへと飛び出ていった知識人が、ヨーロッパの人間中心主義の晴れやかさ、物質文明の豊かさに触れて、神仏なき自由の世界に憧れだしました。たとえば夏目漱石がそうです。彼は時代の先駆者として、封建社会に変わる思想として個人主義を掲げます。その一方で、彼の心は「死ぬか、気が違うか、宗教にはいるか」(『行人』)に追いつめられていたのです。だから漱石は『こころ』で先生を自殺させるほかなかった。『行人』では気をふれさせるしかなかった。小説は、行き詰まった漱石が、実際に自殺したり気が違ったりする代わりに、おこなった代償行為だったのです。漱石はそうした苦しみのはてにようやく「則天去私」にいたることができました。これは彼のたどり着いた宗教だと思います。だが芥川竜之介や太宰治は酒と女と薬におぼれ死んでいくしかありませんでした。
あれから百年近くがたちました。漱石の課題はごく普通の人々の課題になってきたのです。なぜなら豊かな時代の到来は、人々をして漱石並みの意識生活者にしてしまっているからであります。時代はまさに、「自殺するか、狂うか、宗教にはいるか」ではないでしょうか。
近頃では川端康成や江藤淳が自殺しました。尾崎豊やヒデと芥川や太宰とに差があるでしょうか。今では自殺者は三万人を越えています。また分裂病とか躁鬱病などだけでなく、家庭内暴力、引きこもり、心身症など、様々な形で心を病む人が増え続けています。豊かさの中で、得体の知れない不安や苛立ちが人々の心に蓄積していっております。気も違わず自殺もしなくてすむように、ある者は気晴らしに精を出しております。趣味の世界であり、スポーツであり、グルメに温泉に旅行であります。ある者は自分の存在の根拠を求めて私探しの旅にでます。新々宗教の隆盛です。その一つが「オウム」でなかったでしょうか。
ところが「オウム」の獲得した宗教は、自分が超能力者になる宗教でした。ニーチェがいい、ヒットラーが演じたものにどこか似ています。超能力への憧れは「オウム」ばかりでありません。新々宗教の幾つかに共通した特徴です。神の死を前提にしたところから、宗教を求めたからでありましょう。
本当に、神は死んだのか? 死んだというなら、いったい誰が殺してしまったのか? 今一度、現代文明の出発点にあった「我思う、故に、我あり」を検討し直さなければならないのではないでしょうか。
止まることのない欲望に引きずられて、ものすごいスピードで突き進む人間は、今やいのちまでも自己の欲するままに取り扱おうとしています。人間の自意識に立つ文明は、必ず病気や死を受け入れず、他のいのちも許さぬ文明となります。自分ひとりだけが拡大しようとするその姿は、癌そのもののでありましょう。意識はいのちにとっての癌となり、意識に立つ人間は地球という生命体にとっての癌となってしまいました。
意識に対する抑えが効かなくなった今日、意識は自分自身を「自殺するか、狂うか、宗教にはいるか」に追い込んでしまっている。また意識の亡霊となった人間は地球環境そのものを破壊するところまで来ている。爛熟した現代文明もそれに異を唱えた「オウム」の悲劇も、我々に今一度、釈尊やソクラテスや孔子やキリストに帰れと、叫んでいるように思えるのです。
あれから百年近くがたちました。漱石の課題はごく普通の人々の課題になってきたのです。なぜなら豊かな時代の到来は、人々をして漱石並みの意識生活者にしてしまっているからであります。時代はまさに、「自殺するか、狂うか、宗教にはいるか」ではないでしょうか。
近頃では川端康成や江藤淳が自殺しました。尾崎豊やヒデと芥川や太宰とに差があるでしょうか。今では自殺者は三万人を越えています。また分裂病とか躁鬱病などだけでなく、家庭内暴力、引きこもり、心身症など、様々な形で心を病む人が増え続けています。豊かさの中で、得体の知れない不安や苛立ちが人々の心に蓄積していっております。気も違わず自殺もしなくてすむように、ある者は気晴らしに精を出しております。趣味の世界であり、スポーツであり、グルメに温泉に旅行であります。ある者は自分の存在の根拠を求めて私探しの旅にでます。新々宗教の隆盛です。その一つが「オウム」でなかったでしょうか。
ところが「オウム」の獲得した宗教は、自分が超能力者になる宗教でした。ニーチェがいい、ヒットラーが演じたものにどこか似ています。超能力への憧れは「オウム」ばかりでありません。新々宗教の幾つかに共通した特徴です。神の死を前提にしたところから、宗教を求めたからでありましょう。
本当に、神は死んだのか? 死んだというなら、いったい誰が殺してしまったのか? 今一度、現代文明の出発点にあった「我思う、故に、我あり」を検討し直さなければならないのではないでしょうか。
止まることのない欲望に引きずられて、ものすごいスピードで突き進む人間は、今やいのちまでも自己の欲するままに取り扱おうとしています。人間の自意識に立つ文明は、必ず病気や死を受け入れず、他のいのちも許さぬ文明となります。自分ひとりだけが拡大しようとするその姿は、癌そのもののでありましょう。意識はいのちにとっての癌となり、意識に立つ人間は地球という生命体にとっての癌となってしまいました。
意識に対する抑えが効かなくなった今日、意識は自分自身を「自殺するか、狂うか、宗教にはいるか」に追い込んでしまっている。また意識の亡霊となった人間は地球環境そのものを破壊するところまで来ている。爛熟した現代文明もそれに異を唱えた「オウム」の悲劇も、我々に今一度、釈尊やソクラテスや孔子やキリストに帰れと、叫んでいるように思えるのです。
第七章 「オウム」の物語
「物語」の力
もし「釈尊やソクラテスや孔子やキリストに帰れ」と言われたら、みなさんは反発されるでしょうか。かなりの方が「ハイ」と頷かれるのではないでしょうか。ところが、「ハイ」とは頷いたものの、現代人はなかなかその信仰に入れないのです。宗教に必然する「超越者の物語」が、科学的思惟方法だけが身に付いてしまった現代人には「躓きの石」となってしまうのです。宗教に入ることを邪魔している「躓きの石」を除くためにも、宗教に必然する「物語」について考えてみたいと思います。
「オウム」の人々は世間を捨てたときから、麻原が提起した「物語」を生きることになりました。それは「オウム」に集う人たちを熱狂させるとともに、個々の判断を不能にするものでもありました。たとえば林郁夫さんが地下鉄にサリンをまけと言われたとき、全く予想外のことに困惑し、その命令から逃げ出したくなったといいます。もちろん逃げることはできません。それならどうしたかというと、「これは尊師から与えられたマハームドラーの修行だ」と思いかえすことによって、内から湧き出る恐れや疑問を押し殺してしまったのです。
マハームドラーの修行というのは、仏教説話から取った「オウム」独自の物語であります。なんでも、昔ひとりのグルがいて、弟子の修行を進めるため無理難題を与えた。弟子は自分の命をも省みずグルに従ったので、その弟子の解脱は瞬時に完成したと。こういう物語を麻原は弟子に繰り返して、弟子の疑念の芽を摘んでいるのです。サリンを撒くことを命じられた弟子たちも、「マハームドラーの修行」と考えることで、おぞましい殺人事件がグルから命じられた宗教的な行為になってしまうのです。
「オウム」の人々は世間を捨てたときから、麻原が提起した「物語」を生きることになりました。それは「オウム」に集う人たちを熱狂させるとともに、個々の判断を不能にするものでもありました。たとえば林郁夫さんが地下鉄にサリンをまけと言われたとき、全く予想外のことに困惑し、その命令から逃げ出したくなったといいます。もちろん逃げることはできません。それならどうしたかというと、「これは尊師から与えられたマハームドラーの修行だ」と思いかえすことによって、内から湧き出る恐れや疑問を押し殺してしまったのです。
マハームドラーの修行というのは、仏教説話から取った「オウム」独自の物語であります。なんでも、昔ひとりのグルがいて、弟子の修行を進めるため無理難題を与えた。弟子は自分の命をも省みずグルに従ったので、その弟子の解脱は瞬時に完成したと。こういう物語を麻原は弟子に繰り返して、弟子の疑念の芽を摘んでいるのです。サリンを撒くことを命じられた弟子たちも、「マハームドラーの修行」と考えることで、おぞましい殺人事件がグルから命じられた宗教的な行為になってしまうのです。
前生譚
「オウム」にいた者は皆、グルの「予言」という物語の中で、新しき時代を夢見ていました。同じくグルの「神通力」により、麻原と弟子たちは遠き過去からの深い絆で結ばれることになるのでした。たとえば大蔵省の長官であり、麻原に次ぐステージと尊敬されていた石井久子さん、彼女は実際に麻原の子供を三人生んでいるので妻みたいなものだったんでしょうが、それを「前世において、おまえは私の妻であった」とか、あるときは「おまえは私の母であった」といって、彼女を感動させています。あるいは大内早苗さんには「おまえの前世は神であった」とか「俺の五百人の妻の中の一人だった」と言っております。早川紀代秀に対しては「俺が阿修羅界の王だった時、おまえは弟弟子であった」と。さらに、「わたしは前生の救済からおまえと一緒に動いていた。私が何を大切にするかというと前生の縁だ」と。麻原はおもだった弟子にこうした前生譚を披露していっております。弟子たちはそうした物語を喜んで受け入れ、いよいよ麻原との関係を深めていきました。(注二六)
カルマ落とし
「オウム」には「カルマ落とし」というのがあります。「オウム」は輪廻転生説に立っておりました。それで悪いことが起こったなら、それは「カルマ落とし」だと。前世の悪業をこの世で償えれた、来世まで持ち込まずにすんだ、善かった善かった、と受け取っていっております。ある時、ひとりの女性がワークの最中に硫酸を浴びる事件があったそうです。その時、痛がる本人に「カルマ落としができて善かったね」と、仲間が言ったというのです。ここには人間の自然な感覚が完全に抑圧されています。
こうなればどんな悪事を犯しても、それはその人のカルマを落としてやった善行になってしまいます。「オウム」では悪いことは「カルマ落とし」だと、善いことはグルのおかげなんだと、こういうことになっていきました。正常な感覚からすれば噴飯物に過ぎないのですが、「オウム」にはこんな物語が溢れています。そしてこうした物語こそ、「オウム」をこれほどエネルギッシュな団体にしたのです。
こうなればどんな悪事を犯しても、それはその人のカルマを落としてやった善行になってしまいます。「オウム」では悪いことは「カルマ落とし」だと、善いことはグルのおかげなんだと、こういうことになっていきました。正常な感覚からすれば噴飯物に過ぎないのですが、「オウム」にはこんな物語が溢れています。そしてこうした物語こそ、「オウム」をこれほどエネルギッシュな団体にしたのです。
上祐の陳述書
地下鉄サリン事件の最中、詭弁を弄し続けた上祐史裕が、自身の初公判で述べた陳述書にも、それがよく表れています。彼は地下鉄サリン事件以降、毎日テレビに出て、犯人が「オウム」でないことを証明しようとしました。「ゴキブリ一匹殺さぬ私たちがサリンなどを撒くはずがない」と、あたかも自分たちこそ弾圧されているのだと言い続けました。多くの日本人が、何であれほど平気に嘘が言えるのか、不思議で仕方なかったことと思います。あれは嘘だったのでしょうか? 嘘というより、彼が私たちと違う世界に立っていた、ということだったんです。逮捕後の初公判で彼が述べた陳述書に、それがよく示されておりますので読んでみたいと思います。
「私たちは偉大な予言に基づいて生きている。新しい時代が近づいており、そこではすべての魂が苦しみから解放される。精神的、霊的に崇高な世界のために、麻原尊師はあらゆる意味で重要な導き手であり、救世主と考えている。私にとってのすべてであります。「オウム」の真理もその時に明らかになるでしょう。予言とはすべて神の言葉であり、すべて現象化している。信者の中で智慧あるものは理解している。それを堅く信じ続けること、臆病にならないこと、ありきたりの知性を超えて、現世の苦しみに耐える勇気が必要であり、そのために私は努力し続けます。予言では新しい時代が来れば聖なるものはさらに聖を行い、邪なるものはさらに邪を深める。よって起訴事実について私の方から申し上げることは何もありません」。(注二八)
地下鉄にサリンを撒いただけでなく、それ以外にも何人ものいのちを殺めてしまった、ということが明らかになっても、上祐は謝罪を行なおうとしておりません。なおも、「麻原尊師はあらゆる意味で重要な導き手であり、救世主である」とし、「すべての魂が苦しみから解放される」「新しい時代」が来るまで、「(予言)を堅く信じ続けること、臆病にならないこと、ありきたりの知性を超えて、現世の苦しみに耐える勇気が必要であり、そのために私は努力し続けます」と言ってます。
この陳述書はなんとも恐ろしいものであります。アニメの世界と同じ光景がイメージされているのでしょうか。いかに悲しかろうと、新しい時代の到来するまでには、もっともっと多くのいのちが流されることを覚悟しよう、と言っているようです。ここが連合赤軍との違いです。連合赤軍の人たちは、仲間を殺したという「事実」に頭を垂れて、自分たちの思想のどこに誤りがあったのか、自己批判を始めました。しかし上祐たちは今もなお、「神に選ばれた真理の戦士による、人類救済の戦い」という「オウム」の物語の中にいます。
「私たちは偉大な予言に基づいて生きている。新しい時代が近づいており、そこではすべての魂が苦しみから解放される。精神的、霊的に崇高な世界のために、麻原尊師はあらゆる意味で重要な導き手であり、救世主と考えている。私にとってのすべてであります。「オウム」の真理もその時に明らかになるでしょう。予言とはすべて神の言葉であり、すべて現象化している。信者の中で智慧あるものは理解している。それを堅く信じ続けること、臆病にならないこと、ありきたりの知性を超えて、現世の苦しみに耐える勇気が必要であり、そのために私は努力し続けます。予言では新しい時代が来れば聖なるものはさらに聖を行い、邪なるものはさらに邪を深める。よって起訴事実について私の方から申し上げることは何もありません」。(注二八)
地下鉄にサリンを撒いただけでなく、それ以外にも何人ものいのちを殺めてしまった、ということが明らかになっても、上祐は謝罪を行なおうとしておりません。なおも、「麻原尊師はあらゆる意味で重要な導き手であり、救世主である」とし、「すべての魂が苦しみから解放される」「新しい時代」が来るまで、「(予言)を堅く信じ続けること、臆病にならないこと、ありきたりの知性を超えて、現世の苦しみに耐える勇気が必要であり、そのために私は努力し続けます」と言ってます。
この陳述書はなんとも恐ろしいものであります。アニメの世界と同じ光景がイメージされているのでしょうか。いかに悲しかろうと、新しい時代の到来するまでには、もっともっと多くのいのちが流されることを覚悟しよう、と言っているようです。ここが連合赤軍との違いです。連合赤軍の人たちは、仲間を殺したという「事実」に頭を垂れて、自分たちの思想のどこに誤りがあったのか、自己批判を始めました。しかし上祐たちは今もなお、「神に選ばれた真理の戦士による、人類救済の戦い」という「オウム」の物語の中にいます。
第八章 いのちの物語
「物語」とは何か
それでは「物語」がいけないのかというと、私はそうではないと思っています。ちょっと面倒な話になりますが、「オウム」は物語の内容が悪かったのであって、物語を否定してしまうと、また元の木阿弥になってしまいます。
物語というのは、人生の意味を了解するためにとっても大切なものなのです。人生を無駄に過ごしてしまったなぁという感が通底する時、「あぁ、俺は浦島太郎だった」と思うのです。日本人は、「人生を無駄にするなよ」なんて言うより、「浦島太郎になるなよ」と言い合ってきたのではないでしょうか。ところが小賢しくなった我々は、浦島なんておらない、あれは科学的な知恵のない時代のお伽噺だといって、捨ててしまったのです。
いつしか日本人は、自分の人生の全体を受けとめる物語を失ってしまいました。人生訓みたいなものでは、頭の先には届いても、いのちの底まで届かないのではないでしょうか。今では、いのちそのものが、自分の人生の全体を受けとめるべき物語を求めているのだと思います。
たとえば宮崎駿の作品が若い人々にとどまらず、多くの人々の心を捕まえて放さないのはなぜでしょうか。『風の谷のナウシカ』とか『もののけ姫』とかは、人類の業ともいうべき重い課題が「物語」という形で力強く示されているからでありましょう。
『モモ』を書いたミヒャエル・エンデに『はてしなき物語』という小説があります。それは、ファンタジーを失った大人によって増殖された虚無が世界を呑み込み崩壊させてしまうのを、ファンタジーを失っていない幼い魂が救うという、実に深い英知に充ちた物語です。『モモ』や『はてしなき物語』を読んだとき、これは現代の経典、それもいのちの救いを説く浄土の経典だと思ったものです。エンデは「ファンタジー=物語」の大切さを見事な「物語」で教えてくれました。
物語というのは、人生の意味を了解するためにとっても大切なものなのです。人生を無駄に過ごしてしまったなぁという感が通底する時、「あぁ、俺は浦島太郎だった」と思うのです。日本人は、「人生を無駄にするなよ」なんて言うより、「浦島太郎になるなよ」と言い合ってきたのではないでしょうか。ところが小賢しくなった我々は、浦島なんておらない、あれは科学的な知恵のない時代のお伽噺だといって、捨ててしまったのです。
いつしか日本人は、自分の人生の全体を受けとめる物語を失ってしまいました。人生訓みたいなものでは、頭の先には届いても、いのちの底まで届かないのではないでしょうか。今では、いのちそのものが、自分の人生の全体を受けとめるべき物語を求めているのだと思います。
たとえば宮崎駿の作品が若い人々にとどまらず、多くの人々の心を捕まえて放さないのはなぜでしょうか。『風の谷のナウシカ』とか『もののけ姫』とかは、人類の業ともいうべき重い課題が「物語」という形で力強く示されているからでありましょう。
『モモ』を書いたミヒャエル・エンデに『はてしなき物語』という小説があります。それは、ファンタジーを失った大人によって増殖された虚無が世界を呑み込み崩壊させてしまうのを、ファンタジーを失っていない幼い魂が救うという、実に深い英知に充ちた物語です。『モモ』や『はてしなき物語』を読んだとき、これは現代の経典、それもいのちの救いを説く浄土の経典だと思ったものです。エンデは「ファンタジー=物語」の大切さを見事な「物語」で教えてくれました。
仏さまの足音
現代というのは、ある意味で科学的知性に立ったために、自分の全体を受けとめる物語を失っていると思います。そのため生きていることが単なる偶然になってしまったり、生理現象になったり、金銭に置き換えられてしまったりして、生きていることの不思議さを感じられない無味乾燥な世界になっているのではないでしょうか。
榎本栄一さんに、
榎本栄一さんに、
足 音
夜 かすかな風の音
雨の音
これは仏さまが
この人の世を
おあるきになる足音である
雨の音
これは仏さまが
この人の世を
おあるきになる足音である
という詩があります。(注二九)これに対し、私たちはどうでしょうか。雨が降れば低気圧が来ていると思い、さらには生活の邪魔をするもののごとく見てしまっています。
あるいは松原祐善先生の友人だった黒田沐山居さんの詩に、
あるいは松原祐善先生の友人だった黒田沐山居さんの詩に、
「ちぢに鳴く
田の蛙めは
母(おも)よ 何」
「彼こそは法蔵比丘よ
おぼろ夜に
村の人どち寝むまも
思い砕かす菩薩どちなれ」
田の蛙めは
母(おも)よ 何」
「彼こそは法蔵比丘よ
おぼろ夜に
村の人どち寝むまも
思い砕かす菩薩どちなれ」
という詩があります。(注三〇)「あれは蛙が繁殖のために鳴いているんだ」という科学的な理解と、受け止め方が全然、違います。私たちは物語を失うとともに、いのちの通った温かな世界を失ってしまったのです。
たべものさまには仏がござる
今から十五年ぐらい前になりますが、宇野正一さんの『はじめに念仏あり』(注三一)という本に出会って、宗教のもつ物語の大切さにはじめて気づきました。時間もないので詳しく申せませんが、それはおおよそこういう話です。
宇野さんはおじいちゃんに育てられたのですが、そのおじいちゃんの教えに「たべものさまには仏がござる、おがんで食べなされ」というのがありました。ところが学校の先生は「君のおじいさんは昔の人だで、迷信を信じといでるだな、ご飯粒の中には、蛋白質と含水炭素と、脂肪と水分、その他のものは入っとやせんがや」と言われたそうです。なぜ先生はおじちゃんの教えを「迷信」と決めつけたのでしょうか。それは、お米をいくら科学的に分析しても「仏さま」なるものが出てこないからであります。
私の最初の迷いも同じものでした。学校教育を受け、科学的知識が身に付くに従って、仏教が嘘ぽっく感じられるようになったものです。というのも、宇宙の果てまで明らかになろうとしているのに、浄土が見つかったという報告を聞いたことがない。すべての存在を分析していったら分子や原子になるだけだし、いのちを解明していくと遺伝子にいきつくだけで、どこにも仏さまなど出てこない。結局宗教は、社会科学が説明するように、弱い人間が自己満足のために作り上げた妄想にすぎないのではないかと思うようになりました。大なり小なり日本人の多くは、今こう思っているのではないでしょうか。
こうしていつしか我々は、お米に「蛋白質と含水炭素と脂肪と水分」しか見ることができなくなってしまいました。昔の人のように「仏さま」を拝むことがなくなりました。そうするとどういうことが起こってきたかというと、お米に対して「おいしいかまずいか」「値段が高いか安いか」という関心でしか関われなくなったのです。あるのは私のわがままな心だけです。
宇野さんはおじいちゃんに育てられたのですが、そのおじいちゃんの教えに「たべものさまには仏がござる、おがんで食べなされ」というのがありました。ところが学校の先生は「君のおじいさんは昔の人だで、迷信を信じといでるだな、ご飯粒の中には、蛋白質と含水炭素と、脂肪と水分、その他のものは入っとやせんがや」と言われたそうです。なぜ先生はおじちゃんの教えを「迷信」と決めつけたのでしょうか。それは、お米をいくら科学的に分析しても「仏さま」なるものが出てこないからであります。
私の最初の迷いも同じものでした。学校教育を受け、科学的知識が身に付くに従って、仏教が嘘ぽっく感じられるようになったものです。というのも、宇宙の果てまで明らかになろうとしているのに、浄土が見つかったという報告を聞いたことがない。すべての存在を分析していったら分子や原子になるだけだし、いのちを解明していくと遺伝子にいきつくだけで、どこにも仏さまなど出てこない。結局宗教は、社会科学が説明するように、弱い人間が自己満足のために作り上げた妄想にすぎないのではないかと思うようになりました。大なり小なり日本人の多くは、今こう思っているのではないでしょうか。
こうしていつしか我々は、お米に「蛋白質と含水炭素と脂肪と水分」しか見ることができなくなってしまいました。昔の人のように「仏さま」を拝むことがなくなりました。そうするとどういうことが起こってきたかというと、お米に対して「おいしいかまずいか」「値段が高いか安いか」という関心でしか関われなくなったのです。あるのは私のわがままな心だけです。
人間死ねばゴミになる
お米の価値は本来、私の恣意性を超えたものです。だからそれを「仏さまがござる」と言い表したのでした。「仏さま」とは存在の価値を言い表す言葉だったのです。ものを分析する科学の言葉と根本的に違うものなのです。ところがその区別を知りわける智慧のないまま、先生は「仏さま」なるものは迷信だと断罪してしまったのです。今の日本にはもう、ものそのものの価値を豊かに表現する物語がなくなってしまいました。学校給食の現場では、子ども達が汚いものでも捨てるがごとく、無造作に食べ物を捨てています。「もったいない」とか「ありがたい」などは死語になりつつあります。日本人がエコノミック・アニマルと言われるようになってしまったのも、人間が根源的にもっているわがままな心を、物語という形で戒めてきた宗教を失ったからではないでしょうか。
これはお米だけの話ではありません。我々はもう何事をも、科学の眼でしか見れなくなりました。いのちの誕生も、精子と卵子の結合という生理現象として納得する。だからいのちそのものへの畏敬の念は薄れ、あるのは自分のエゴだけ。今では、子供は作るものになってしまった。河村ふでさんという方に、「わが子というものは、自分のおなかから生まれても、自分のものじゃない。み仏さまからのお預かりのものだから、拝んで育てにゃの」(注三二)という温かな言葉がありますが、はたして今の子供は親から拝まれて育っているでしょうか。大切にされていそうで、実はそれも親のエゴのまま。親が自分の満足のために育てたペットに他ならないのではないでしょうか。
あるいは死すことも、心臓が止まるという生理現象として、火葬したら骨になるという物理現象とてしか受け止めれなくなっています。その後に残るのは、今まで世界にふんぞり返ってきた「私」の消滅という恐ろしい虚無であります。すると「死」は「骨になる」という物理現象をこえて価値のない「ゴミ」としか思えなくなる。「巨悪は眠らせぬ」といって田中角栄氏を有罪にもちこんだ検事総長の伊藤栄樹さんは「人間死ねばゴミになる」と言って死んでいきました。(注三三)
これはお米だけの話ではありません。我々はもう何事をも、科学の眼でしか見れなくなりました。いのちの誕生も、精子と卵子の結合という生理現象として納得する。だからいのちそのものへの畏敬の念は薄れ、あるのは自分のエゴだけ。今では、子供は作るものになってしまった。河村ふでさんという方に、「わが子というものは、自分のおなかから生まれても、自分のものじゃない。み仏さまからのお預かりのものだから、拝んで育てにゃの」(注三二)という温かな言葉がありますが、はたして今の子供は親から拝まれて育っているでしょうか。大切にされていそうで、実はそれも親のエゴのまま。親が自分の満足のために育てたペットに他ならないのではないでしょうか。
あるいは死すことも、心臓が止まるという生理現象として、火葬したら骨になるという物理現象とてしか受け止めれなくなっています。その後に残るのは、今まで世界にふんぞり返ってきた「私」の消滅という恐ろしい虚無であります。すると「死」は「骨になる」という物理現象をこえて価値のない「ゴミ」としか思えなくなる。「巨悪は眠らせぬ」といって田中角栄氏を有罪にもちこんだ検事総長の伊藤栄樹さんは「人間死ねばゴミになる」と言って死んでいきました。(注三三)
人間の「行」ー割れたコップをくっつけるー
宗教の智慧とは、私と世界とを貫く物語を見いだす智慧だと思います。科学はものを明らかにするために、そのものを限りなく分析していきます。バラバラにしてしまいます。それが科学の知恵です。それに対し宗教の智慧は、バラバラにしか見えないものの中を貫く「一」なるものを見いだす智慧です。宗教は一如の世界です。親鸞聖人にも、一如、一道、一乗、一実、一法、一心、一行、一念、一処等々、真実の世界が「一」という言葉で表されています。「一」は現象界を貫くものです。それは眼では見えないものです。だから、それは必ず物語をもってしか語れないのです。
ところが、私がこれまでやってきたことは、ガチャンと割ってしまったコップを、人間の努力という名の接着剤で一生懸命くっつけようとすることでした。愛といい連帯といっても、それははじめに割れてしまっているんです。仏教では、人間の意識を「分別」と言ってきました。すごい智慧だと思います。「分」「別」によってはじめにバラバラにしておいて、慌ててくっつけようとする、それは「必ず不可なり」です。もうスタートでずれているのです。
ところが人間の眼は、それが見えないようにできている。それに気づかずバラバラになった世界を、自分の努力でもとの一如の世界に戻そうとする。真面目であればあるほど、必ず自分が「全知全能の神」になる他ないように追いつめられてしまいます。「オウム」がまさにそうなんです。親鸞聖人はそれを聖道門と指摘されたのです。これが「行」をたてる宗教の陥るジレンマです。
ところが、私がこれまでやってきたことは、ガチャンと割ってしまったコップを、人間の努力という名の接着剤で一生懸命くっつけようとすることでした。愛といい連帯といっても、それははじめに割れてしまっているんです。仏教では、人間の意識を「分別」と言ってきました。すごい智慧だと思います。「分」「別」によってはじめにバラバラにしておいて、慌ててくっつけようとする、それは「必ず不可なり」です。もうスタートでずれているのです。
ところが人間の眼は、それが見えないようにできている。それに気づかずバラバラになった世界を、自分の努力でもとの一如の世界に戻そうとする。真面目であればあるほど、必ず自分が「全知全能の神」になる他ないように追いつめられてしまいます。「オウム」がまさにそうなんです。親鸞聖人はそれを聖道門と指摘されたのです。これが「行」をたてる宗教の陥るジレンマです。
「私」からの出発
村上春樹氏は、「オウム」の人たちの心境は、「たしかに出てきた結果は悪かった。反省はしています。でもオウム真理教というあり方の方向性そのものは間違っていないし、その部分までを全否定する必要は認められない」ということになるのでないか、と言っております。(注三四)
本当にそうなのでしょうか。はじめは良かったけれど途中からおかしくなったのではなく、はじめがおかしかったからおかしな最後になったのではないか。世間を汚れていると見、自分に息苦しさを感じる、その最初の感覚を前提にして、その埋め合わせを誠実にやろうとすればするほど、どんどんおかしくなっていったのではないでしょうか。これが「行」というものの宿命というか、聖道門というものの限界だと思います。言い方を変えるならば、「私(人間)からの出発」の限界であります。
親鸞聖人はすべてのご和讃を終えるにあたって、
本当にそうなのでしょうか。はじめは良かったけれど途中からおかしくなったのではなく、はじめがおかしかったからおかしな最後になったのではないか。世間を汚れていると見、自分に息苦しさを感じる、その最初の感覚を前提にして、その埋め合わせを誠実にやろうとすればするほど、どんどんおかしくなっていったのではないでしょうか。これが「行」というものの宿命というか、聖道門というものの限界だと思います。言い方を変えるならば、「私(人間)からの出発」の限界であります。
親鸞聖人はすべてのご和讃を終えるにあたって、
よしあしの文字をもしらぬひとはみな
まことのこころなりけるを
善悪の字しりがおは
おおそらごとのかたちなり
まことのこころなりけるを
善悪の字しりがおは
おおそらごとのかたちなり
是非しらず邪正もわかぬ
このみなり
小慈小悲もなけれども
名利に人師をこのむなり (注三五)
このみなり
小慈小悲もなけれども
名利に人師をこのむなり (注三五)
というご和讃を置かれ、自分自身を深く悲嘆されています。そのお心は、みんなに仏法を分かってもらいたいとたくさんの和讃を作ってきたが、みんなみんな嘘でした、こうしたことは「善悪の字」を知ったかぶりした「おおそらごとのかたち」でした、私親鸞の根性は「是非・邪正」もわからず「慈悲」のかけらもないくせに、みんなから立派な先生と誉められ富を手にしたがる「名利に人師をこのむ」ものでした、なんとも恥ずかしいことですと、こういうことでないでしょうか。
親鸞聖人がおっしゃるように、人間の自我はいかなることをも、たとえそれが「無我」を教える仏法であろうとも、一切を我がために利用してかかる存在なのです。「私」とは「おおそらごと」以外の何者でもありません。「私からの出発」とは「嘘からの出発」ということです。「嘘」から決して「真実」は生まれないのです。
親鸞聖人がおっしゃるように、人間の自我はいかなることをも、たとえそれが「無我」を教える仏法であろうとも、一切を我がために利用してかかる存在なのです。「私」とは「おおそらごと」以外の何者でもありません。「私からの出発」とは「嘘からの出発」ということです。「嘘」から決して「真実」は生まれないのです。
仏の智慧 ーコップは割れていなかったー
最初の間違いが見えないままに、基本は正しかったけど麻原がおかしかった、途中からおかしくなったと。この思いは「オウム」に留まっている人だけでなく、「オウム」を出た人たちにも通ずるものです。「オウム」ばかりでなく、連合赤軍の人たちの総括を見てみても、基本は正しかったけれど、どこかで方向が違ったと。永田洋子さんのものなどを読むと、何ともいえぬ辛さに襲われます。人間の無明、それこそ根本無明です。仏教とは、人間の意識が起こすこうした「転倒」に気づき、意識以前の存在の本来性に帰ることを教えるものなのです。
いのちは、手であったり、心臓であったり、脳であったりと、部分に分けることはできません。分けた後、それらを一つ一つくっつけていっても、もはやいのちになりません。いのちはそれらの総合であります。親と私と別ではありません。花や木や犬や猫や、大空や遠い星々と、私は別物ではありません。私が生きているということは、それらの全てと一つのことなのです。一如こそ、宗教の教えるところです。本当は、コップは割れていなかったのです。割れたと思ったのは錯覚で、決して割れてはいなかった、そう気づく智慧を親鸞聖人は「信心」と言われたのです。そう思います。
いのちは、手であったり、心臓であったり、脳であったりと、部分に分けることはできません。分けた後、それらを一つ一つくっつけていっても、もはやいのちになりません。いのちはそれらの総合であります。親と私と別ではありません。花や木や犬や猫や、大空や遠い星々と、私は別物ではありません。私が生きているということは、それらの全てと一つのことなのです。一如こそ、宗教の教えるところです。本当は、コップは割れていなかったのです。割れたと思ったのは錯覚で、決して割れてはいなかった、そう気づく智慧を親鸞聖人は「信心」と言われたのです。そう思います。
第九章 回 心
「親鸞一人がためなりけり」
親鸞聖人に、「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり。されば、そくばくの業をもちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ」(『歎異抄』後序)というお言葉があります。私は単なる偶然の存在でもなく、はたまた終わりなき苦悩を背負い続ける不条理な存在でもない。五劫の昔から弥陀に念じられてきたいのちだった、という気づきです。親鸞聖人の回心とは自己のアイデンティティの回復でもあったのです。
また、法然上人の恩徳を讃えるご和讃に、
また、法然上人の恩徳を讃えるご和讃に、
命終その期ちかづきて
本師源空のたまわく
往生みたびになりぬるに
このたびことにとげやすし
本師源空のたまわく
往生みたびになりぬるに
このたびことにとげやすし
阿弥陀如来化してこそ
本師源空としめしけれ
化縁すでにつきぬれば
浄土にかえりたまいにき (注三六)
本師源空としめしけれ
化縁すでにつきぬれば
浄土にかえりたまいにき (注三六)
こういうご和讃があります。親鸞聖人は法然上人を、釈尊在世の過去から来世の浄土まで、弥陀の御物語の中で頂かれております。「父母は誰で、いつ生まれて、何歳の時何をして、何の病気で死んで、云々」という現代人の受け止め方と違います。現代人は事象を追いかけます。親鸞聖人はその事象の底に流れている意味を頂いていきます。そして、その意味は物語でしか語ることが出来ないのです。
如是我聞
結論みたいなことになりますが、浄土真宗も他の伝統的な宗教と同じく、科学の前に恐れをなして宗教に必然する物語を捨てようとしてきたのではないでしょうか。同朋会運動は信仰回復運動のはずでしたが、いつしか学問沙汰になってしまっていないでしょうか。
学問沙汰になってしまったということは、『大無量寿経』に説かれる本願の物語によって私が証されていくのでなく、逆に私の方が『大無量寿経』を分かろうとしだしたということです。浄土真宗の教えの根幹をなしていた弥陀の御物語を人間の知恵でも分かる言葉に翻訳(非神話化)しようとして、いつしかそのいのちを枯らしてしまわなかったでしょうか。
結婚生活がうまくいかず苦しんでいる友に、児玉先生が「法蔵菩薩のご修行中や」と愛おしく言われたのを聞いたことがあります。こういうのが浄土真宗だったのです。今一度、妙好人たちが生活の中で生み出した物語を学ぶべきだと思います。親鸞聖人の教えの中心にある本願の物語を我が身の上に頂けるか、格闘しなければならないと思います。それが本当の求道でないでしょうか。求道と学問は違います。学問はいくらおこなっても、ただ知恵が増えるだけです。自分自身の生きることが根底からひっくり返る回心は、人間の知恵にとっては躓きの石である本願の御物語を「如是、如是」と聞けるかにかかっています。
学問沙汰になってしまったということは、『大無量寿経』に説かれる本願の物語によって私が証されていくのでなく、逆に私の方が『大無量寿経』を分かろうとしだしたということです。浄土真宗の教えの根幹をなしていた弥陀の御物語を人間の知恵でも分かる言葉に翻訳(非神話化)しようとして、いつしかそのいのちを枯らしてしまわなかったでしょうか。
結婚生活がうまくいかず苦しんでいる友に、児玉先生が「法蔵菩薩のご修行中や」と愛おしく言われたのを聞いたことがあります。こういうのが浄土真宗だったのです。今一度、妙好人たちが生活の中で生み出した物語を学ぶべきだと思います。親鸞聖人の教えの中心にある本願の物語を我が身の上に頂けるか、格闘しなければならないと思います。それが本当の求道でないでしょうか。求道と学問は違います。学問はいくらおこなっても、ただ知恵が増えるだけです。自分自身の生きることが根底からひっくり返る回心は、人間の知恵にとっては躓きの石である本願の御物語を「如是、如是」と聞けるかにかかっています。
如来からの出発
学びの姿勢で大切なこととして、「答えに飛びつくのでない。問いを生きるのだ」ということが言われます。あるいは安田先生に、「不安に立つ」というお言葉があります。こういった言葉は、早く助って楽になろうとする私の弱さを糺してくれます。弱い人間には宗教は甘い誘いであり、面倒な世間から逃げ込む繭にさえなります。そうなってはならないと、「問いを生きる」とか「不安に立つ」ということが言われたのだと思います。
こうした言葉は、教えを求める私の位置の確認を促してくださいます。でもこれだけでは求道になりません。「問い」に対する「答え」がいります。答えは自分の未来です。未来が見いだせて、はじめて歩み出すことが可能になるのです。では私たちの未来はどんな形で与えられるのかというと、それは一つの物語としてであります。物語とは経典であります。経典に説かれている如来です。ところがそれはまだ私の窺い知れない世界です。如来の物語の真実性を、私の前を歩いている善き人から賜るのです。そういう意味では、善き人という形になった如来の物語から促されて、はじめて新しい一歩を踏み出すことができるのです。
「オウム」に集った人々が、自分が生きていることを確認すべき物語を麻原から仕入れたのも、一理あるところなんです。ところが麻原自身は「最終解脱」をしたなどと嘯いて、自分自身が答えになってしまった。ここが親鸞聖人と決定的に違うところです。親鸞聖人にあっては、自らを嘘とし、如来を真とした。自らは問いにたち、答えは如来においた。麻原は自らを真とし、答えを私有化した。真実に対する大いなる罪であり、犯した罪の重さに彼は崩れ去る運命だったのです。
親鸞聖人も「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべしと、よき人のおおせをかぶりて、信ずるほかに別の子細なきなり」と言われています。答えは私(実存)の側になく、如来(未来)の側にある。私ならいかようにも表現できましょうが、如来の世界は物語という形でしか表現されないのだろうと思います。
「オウム」の人たちの失敗を、我々真宗門徒が笑うことができるでしょうか。彼らは宗教のもつ物語性に取り憑かれて自分を見失いました。教団としての長い歴史をもつ私たちはその恐ろしさを警戒しすぎて、物語を解体しようとし、結果的にはお念仏のいのちを失った。失敗はしない代わりに、親鸞聖人との同一念仏が遠ざかった。その両者の底に流れているのは、「自我意識の否定」の不徹底であります。
こうした言葉は、教えを求める私の位置の確認を促してくださいます。でもこれだけでは求道になりません。「問い」に対する「答え」がいります。答えは自分の未来です。未来が見いだせて、はじめて歩み出すことが可能になるのです。では私たちの未来はどんな形で与えられるのかというと、それは一つの物語としてであります。物語とは経典であります。経典に説かれている如来です。ところがそれはまだ私の窺い知れない世界です。如来の物語の真実性を、私の前を歩いている善き人から賜るのです。そういう意味では、善き人という形になった如来の物語から促されて、はじめて新しい一歩を踏み出すことができるのです。
「オウム」に集った人々が、自分が生きていることを確認すべき物語を麻原から仕入れたのも、一理あるところなんです。ところが麻原自身は「最終解脱」をしたなどと嘯いて、自分自身が答えになってしまった。ここが親鸞聖人と決定的に違うところです。親鸞聖人にあっては、自らを嘘とし、如来を真とした。自らは問いにたち、答えは如来においた。麻原は自らを真とし、答えを私有化した。真実に対する大いなる罪であり、犯した罪の重さに彼は崩れ去る運命だったのです。
親鸞聖人も「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべしと、よき人のおおせをかぶりて、信ずるほかに別の子細なきなり」と言われています。答えは私(実存)の側になく、如来(未来)の側にある。私ならいかようにも表現できましょうが、如来の世界は物語という形でしか表現されないのだろうと思います。
「オウム」の人たちの失敗を、我々真宗門徒が笑うことができるでしょうか。彼らは宗教のもつ物語性に取り憑かれて自分を見失いました。教団としての長い歴史をもつ私たちはその恐ろしさを警戒しすぎて、物語を解体しようとし、結果的にはお念仏のいのちを失った。失敗はしない代わりに、親鸞聖人との同一念仏が遠ざかった。その両者の底に流れているのは、「自我意識の否定」の不徹底であります。
回心ー弥陀の智慧をたまわりてー
石原吉郎さんという方に『望郷と海』(注三七)という本があります。石原さんはキリスト者でありますが、この本に収められた彼の日記に、宗教において最も大切な「回心」とはどういうことかを見事に表現してくれていると思われるところがあります。そこに、これまで述べてきた根源的な問題がまとめて書かれていると思われますので、今日の話の締めくくりとして引用したいと思います。
「私はどれだけ幼いときから自分を嫌悪したか分からない(それにもかかわらず、自分自身に限りなく執着した)。その頃から今に到るまで『変わりたい』『別の人間になりたい』ということは、いつも私の心の底にうずきつづけている願いである。そうしてしまいには、私はこのような自己嫌悪を、自分にとって唯一の美徳であるかのように考えるまでになった」。その誠実さは死と隣り合わせだったシベリア抑留でも貫こうとするほどの激しさでした。しかし、どんなに激しく願っても、「私自身はそれこそびた一文だって変りはしなかったのだ」というのです。
親鸞聖人の言葉を借りれば、私とは曠劫来流転してきたいのちなのです。この世に生まれてから始まった煩悩ではないんです。煩悩成就の凡夫としてこの世に生まれてきた私ですから、変わるはずがないんです。ところが私たちの意識は、真の智慧がないから、それを変えようとする。つまり、私が私でない何者かになって助かろうとする。これが人間の意識が起こす転倒です。
「オウム」の人々も同じ過ちを犯しました。煩悩を憎み、取れない煩悩を取り除こうとしました。「身」は変わらないが「心」は変わりうると思うのは錯覚です。「煩悩のない私」なんて、「空を飛ぶ私」、「水の中を泳ぐ私」と同じ類で、夢想の中ではあっても、現実には絶対にないことなんです。
石原さんは、ここにいたってコペルニクス的転回をします。びた一文変わらない私ならば、私が私であるままに助かるしかないと。その道はどこにあるか。「〈新しい人間〉とは、今のままの人間が今のままの姿で、今とはまったく別の新しい光に照らされた姿である。もしそうであるなら、それは〈新しい人間〉へ飛躍する力は、わたしの中にはないということである。それは、何かとの〈邂逅〉によってしか起こりえない。その光が復活の光であるとは、今ただちに口に出してはいえないにしても、私はそのような光を、今はキリストの復活の方向にしか予感できないのだ」。
私にはこの言葉と、『歎異抄』の第十六章に出てくる親鸞聖人のお言葉とが一つに聞こてまいります。「日ごろ本願他力真宗をしらざるひと、弥陀の智慧をたまわりて日ごろのこころにては、往生かなうべからずとおもいて、もとのこころをひきかえて、本願をたのみまいらするをこそ、回心とはもうしそうらえ」。
「弥陀の智慧をたまわる」以外に、私が私の意識の呪縛から完全に解放されることはないのだと思います。「罪悪深重煩悩熾盛の衆生をたすけんがための(本)願」と知らされたとき、ここは仏と仏が呼応するいのちの世界なんでありましょう。
「私はどれだけ幼いときから自分を嫌悪したか分からない(それにもかかわらず、自分自身に限りなく執着した)。その頃から今に到るまで『変わりたい』『別の人間になりたい』ということは、いつも私の心の底にうずきつづけている願いである。そうしてしまいには、私はこのような自己嫌悪を、自分にとって唯一の美徳であるかのように考えるまでになった」。その誠実さは死と隣り合わせだったシベリア抑留でも貫こうとするほどの激しさでした。しかし、どんなに激しく願っても、「私自身はそれこそびた一文だって変りはしなかったのだ」というのです。
親鸞聖人の言葉を借りれば、私とは曠劫来流転してきたいのちなのです。この世に生まれてから始まった煩悩ではないんです。煩悩成就の凡夫としてこの世に生まれてきた私ですから、変わるはずがないんです。ところが私たちの意識は、真の智慧がないから、それを変えようとする。つまり、私が私でない何者かになって助かろうとする。これが人間の意識が起こす転倒です。
「オウム」の人々も同じ過ちを犯しました。煩悩を憎み、取れない煩悩を取り除こうとしました。「身」は変わらないが「心」は変わりうると思うのは錯覚です。「煩悩のない私」なんて、「空を飛ぶ私」、「水の中を泳ぐ私」と同じ類で、夢想の中ではあっても、現実には絶対にないことなんです。
石原さんは、ここにいたってコペルニクス的転回をします。びた一文変わらない私ならば、私が私であるままに助かるしかないと。その道はどこにあるか。「〈新しい人間〉とは、今のままの人間が今のままの姿で、今とはまったく別の新しい光に照らされた姿である。もしそうであるなら、それは〈新しい人間〉へ飛躍する力は、わたしの中にはないということである。それは、何かとの〈邂逅〉によってしか起こりえない。その光が復活の光であるとは、今ただちに口に出してはいえないにしても、私はそのような光を、今はキリストの復活の方向にしか予感できないのだ」。
私にはこの言葉と、『歎異抄』の第十六章に出てくる親鸞聖人のお言葉とが一つに聞こてまいります。「日ごろ本願他力真宗をしらざるひと、弥陀の智慧をたまわりて日ごろのこころにては、往生かなうべからずとおもいて、もとのこころをひきかえて、本願をたのみまいらするをこそ、回心とはもうしそうらえ」。
「弥陀の智慧をたまわる」以外に、私が私の意識の呪縛から完全に解放されることはないのだと思います。「罪悪深重煩悩熾盛の衆生をたすけんがための(本)願」と知らされたとき、ここは仏と仏が呼応するいのちの世界なんでありましょう。
凡夫の身に落在す
石原さんは自分の未来をイエス・キリストに予感することが出来ました。この日より生きる姿勢が根本的に変わることになったのでした。そのところを次のように語っております。「私はこういう人間であるよりほかに、ありようがないのだという確かな認識以外の場所から、私は出発してはならない。ありえざる理想像の高みから、自分を見下ろし、叱責し、絶望するほど不毛なことはない。そういう〈前のめり〉の姿勢から一時も早く立ち直ることこそ、私にとって今、最も必要なことなのだ。私が希望をつかもうとあせるのは、実は逃避にほかならないからである」。
「オウム」の人たちは煩悩の身を厭い怖れて、ながいながい迷いの旅に出て傷だらけになってしまいました。それは石原さんもキリストも親鸞聖人も通った道であります。「オウム」の人々のご苦労は、石原さんのご苦労であり、そのままキリストのご苦労であり、親鸞聖人のご苦労でもあります。ささやかながらも私も通った苦労であります。
石原さんは迷いの果てに、イエス・キリストに会い転倒していた意識が破れて、凡夫の身にはじめて落在することが出来ました。石原さんの降り立った位置は、キリストの降り立った位置であり、親鸞聖人の降り立った位置であります。私も降り立とうとしている位置であり、必ずや「オウム」の人たちも降り立たずにはおれぬ位置であるはずです。
結局新しい世紀も、人間の生きる限りは、釈尊やソクラテスや孔子やキリストが辿り着いたところに立ち返るほかないことを、「オウム」は身を以て教えてくれているのではないでしょうか。
丁寧な生活が出来ない私です。考えもまた大雑把なものでしかありません。お聞き苦しかったことでしょうが、これが私ですので、そのままお許し願いたいと思います。有り難うございました。
「オウム」の人たちは煩悩の身を厭い怖れて、ながいながい迷いの旅に出て傷だらけになってしまいました。それは石原さんもキリストも親鸞聖人も通った道であります。「オウム」の人々のご苦労は、石原さんのご苦労であり、そのままキリストのご苦労であり、親鸞聖人のご苦労でもあります。ささやかながらも私も通った苦労であります。
石原さんは迷いの果てに、イエス・キリストに会い転倒していた意識が破れて、凡夫の身にはじめて落在することが出来ました。石原さんの降り立った位置は、キリストの降り立った位置であり、親鸞聖人の降り立った位置であります。私も降り立とうとしている位置であり、必ずや「オウム」の人たちも降り立たずにはおれぬ位置であるはずです。
結局新しい世紀も、人間の生きる限りは、釈尊やソクラテスや孔子やキリストが辿り着いたところに立ち返るほかないことを、「オウム」は身を以て教えてくれているのではないでしょうか。
丁寧な生活が出来ない私です。考えもまた大雑把なものでしかありません。お聞き苦しかったことでしょうが、これが私ですので、そのままお許し願いたいと思います。有り難うございました。
付 記
以上、縷々述べてきたことは、昨年(二〇〇〇年)七月一二日に真宗大谷派教学研究所の現代宗教研究班で発表したものに加筆訂正したものであります。
今、この稿を終えるにあたって、「オウム」に関わった多くの人たちの苦悩を、どこまで受け止めることができたかと、振り返ってみた時、なんだか申し訳なさで一杯になります。
また、どうしても気になることが一つあります。それは「オウム」について語る時、井上、高橋、林氏たちについては自然に「井上さん、高橋さん、林さん」と「さん」をつけて呼んでいるのに、麻原、村井、上祐、石川氏たちに対しては「麻原、村井、上祐、石川」と呼び捨てにせずにおれない私がいるということです。
「オウム」のことを考える時、心のどこかで「井上さん、高橋さん、林さん」らと悲しみを共有しながら、その解決を模索しようとしてきました。しかし未だ「オウム」の物語の中にいる麻原、村井、上祐、石川氏たちは、私の心の中において、私の外に私に敵対して立っております。だから私は麻原氏を外に見、下に見下して「麻原」と呼び捨てにせずにおれないのだと思います。
このことは何を意味しているか。それは私が、私の中の「麻原」的なもの「オウム」的なもの、つまり「悪魔」的なものを深く恐れている、というでしょう。この稿において私は、現代の問題は、(それは人間の根本問題でもあるのですが)、人間のかかえる「悪」をどう解放するかということだと言ってまいりましたが、そう言っている当の本人が、なお「悪」を解決できていないんだということが明らかになったように思います。
一九九七年一月、九十一歳で往生された藤原正遠先生に、「麻原彰晃でも助かるのですか」と質問したら、即座に「助かりますよ」と応えられたことを思い出します。先生は「麻原さんも仏さまに摂まっていますよ」とか、「ここに麻原彰晃よりひどい者がおりますよ」とも語られました。先生は如来の光明の中で極悪人の事実に立たれ、そこから南無阿弥陀仏と如来を仰がれていたのだと思います。
私も親鸞聖人の教えを聞くようになり、悪の恐れからずいぶん解放されたと思っていましたが、悪人の事実に墜ちきれずに、途中で止まっているようです。なぜでしょうか。結局、如来様を信じていないということなんでしょうか。
人
悪人
極悪人
極重悪人─
〝極重悪人 唯称仏〟 (木村無相)(注三八)
私の「オウム」はまだ終わっていません。麻原氏と共に「極重悪人の私」の助かる道をこれからも尋ねてまいろうと思います。 ( 二〇〇一年一〇月二六日)
(真宗大谷派教学研究所発行『教化研究第126号』所収)
注一 『別冊宝島四七六 隣のオウム真理教』一九九七年一二月
注二 岩波『漱石全集第十一巻』三〇七頁
注三 麻原彰晃著『超能力秘密の開発法』(島薗進『オウム真理教の奇跡』八頁参照)
注四 岡村美穂子・上田閑照共著『思い出の小箱から』 燈影舎 一九九七年発行
注五 降籏賢一著『オウム裁判と日本人』二二頁参照 平凡社 二〇〇〇年五月
注六 宮内勝典・高橋英利共著『日本社会がオウムを生んだ』一一〇頁 河出書房新社 一九九九年三月
注七 『朝日新聞』特集「地下鉄サリン事件実行犯十一人の過去」一九九五年七月十日
注八 高橋英利著『オウムからの帰還』草思社、一九九六年
注九 村上春樹著『約束された場所で』一八三頁 文藝春秋社 一九九八年
注一〇 同上一一七頁
注一一 同上 一一二頁
注一二 芹沢俊介著『「オウム」現象の解読』三八頁 筑摩書房 一九九六年四月
注一三 同書一〇頁
注一四 同書一一頁
注一五 同書五九頁
注一六 村上春樹著『約束された場所で』一八六頁
注一七 大泉実成著『麻原彰晃を信じる人びと』洋泉社 一九九六年一月
注一八 降籏賢一著『オウム裁判と日本人』六二頁
注一九 大泉実成著 『マレーバクは悪夢を見ないー夢をコントロールする民族セノイへ の旅』扶桑社 一九九四年
注二〇 加納秀一著『カルトにはまる11の動機』一五二頁 アストラ、二〇〇〇年六月
注二一 宮内勝典・高橋英利共著『日本社会がオウムを生んだ』一三頁~一八頁
注二二 加納秀一著『カルトにはまる11の動機』六五頁
注二三 島薗進著『オウム真理教の奇跡』岩波ブックレット 一九九五年七月
注二四 カナリヤの会編『オウムをやめた私たち』岩波書店 二〇〇〇年五月
注二五 降籏賢一著『オウム裁判と日本人』一〇二頁
注二六 『朝日新聞』特集「ウム解剖ーグルと呼ばれた男」一九九五年一〇月二三日
注二七 【参考】森達也『「A」撮影日誌』現代書館 二〇〇〇年六月
注二八 『朝日新聞』一九九六年三月一五日
注二九 榎本栄一著『煩悩林』難波別院 一九七八年
注三〇 黒田沐山居著『かはづ抄 なむおものうた』法蔵館 一九七一年
注三一 宇野正一著『はじめに念仏あり』法蔵館 一九八三年
注三二 河村としこ著『み仏様との日暮らしを』樹心社 一九九八年
注三三 伊藤栄樹著『人は死ねばゴミになる』新潮社 一九八八年
注三四 村上春樹著『約束された場所で』二六〇頁
注三五 親鸞聖人『正像末和讃』
注三六 親鸞聖人『高僧和讃』
注三七 石原吉郎著『望郷と海』二三二頁~二三八頁 筑摩書房 一九七二年
注三八 木村無相著『念仏詩抄』永田文昌堂 一九七三年
注二 岩波『漱石全集第十一巻』三〇七頁
注三 麻原彰晃著『超能力秘密の開発法』(島薗進『オウム真理教の奇跡』八頁参照)
注四 岡村美穂子・上田閑照共著『思い出の小箱から』 燈影舎 一九九七年発行
注五 降籏賢一著『オウム裁判と日本人』二二頁参照 平凡社 二〇〇〇年五月
注六 宮内勝典・高橋英利共著『日本社会がオウムを生んだ』一一〇頁 河出書房新社 一九九九年三月
注七 『朝日新聞』特集「地下鉄サリン事件実行犯十一人の過去」一九九五年七月十日
注八 高橋英利著『オウムからの帰還』草思社、一九九六年
注九 村上春樹著『約束された場所で』一八三頁 文藝春秋社 一九九八年
注一〇 同上一一七頁
注一一 同上 一一二頁
注一二 芹沢俊介著『「オウム」現象の解読』三八頁 筑摩書房 一九九六年四月
注一三 同書一〇頁
注一四 同書一一頁
注一五 同書五九頁
注一六 村上春樹著『約束された場所で』一八六頁
注一七 大泉実成著『麻原彰晃を信じる人びと』洋泉社 一九九六年一月
注一八 降籏賢一著『オウム裁判と日本人』六二頁
注一九 大泉実成著 『マレーバクは悪夢を見ないー夢をコントロールする民族セノイへ の旅』扶桑社 一九九四年
注二〇 加納秀一著『カルトにはまる11の動機』一五二頁 アストラ、二〇〇〇年六月
注二一 宮内勝典・高橋英利共著『日本社会がオウムを生んだ』一三頁~一八頁
注二二 加納秀一著『カルトにはまる11の動機』六五頁
注二三 島薗進著『オウム真理教の奇跡』岩波ブックレット 一九九五年七月
注二四 カナリヤの会編『オウムをやめた私たち』岩波書店 二〇〇〇年五月
注二五 降籏賢一著『オウム裁判と日本人』一〇二頁
注二六 『朝日新聞』特集「ウム解剖ーグルと呼ばれた男」一九九五年一〇月二三日
注二七 【参考】森達也『「A」撮影日誌』現代書館 二〇〇〇年六月
注二八 『朝日新聞』一九九六年三月一五日
注二九 榎本栄一著『煩悩林』難波別院 一九七八年
注三〇 黒田沐山居著『かはづ抄 なむおものうた』法蔵館 一九七一年
注三一 宇野正一著『はじめに念仏あり』法蔵館 一九八三年
注三二 河村としこ著『み仏様との日暮らしを』樹心社 一九九八年
注三三 伊藤栄樹著『人は死ねばゴミになる』新潮社 一九八八年
注三四 村上春樹著『約束された場所で』二六〇頁
注三五 親鸞聖人『正像末和讃』
注三六 親鸞聖人『高僧和讃』
注三七 石原吉郎著『望郷と海』二三二頁~二三八頁 筑摩書房 一九七二年
注三八 木村無相著『念仏詩抄』永田文昌堂 一九七三年