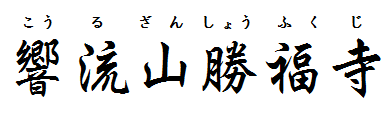響流山勝福寺 宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌・お待ち受け聞法会
宗祖親鸞聖人のご生涯 ⑥ (2018年11月28日)
藤谷知道
関東での20年にわたる伝道に区切りをつけ、親鸞聖人は京に帰り『教行信証』を書き上げました。ところが、聖人がいなくなった関東では、次第に「ただ念仏」(本願他力)のおこころが判らなくなったのでしょう、「お念仏は一度でいいのか、多いほどいいのか」というような教義論争がおこったり、あるいは、「悪人こそ助かるのだから、何でも思い通りにしたらいいんだ」という造悪(ぞうあく)無(む)碍(げ)を唱える人々が出てきました。
こうした誤った考え(異義)を糺(ただ)すために親鸞聖人の子の善鸞(ぜんらん)が関東に赴きましたが、善鸞は異義を糺すどころか、逆に「本願はしぼめる花」などと言って、関東にできた僧伽を混乱に陥れてしまったのです。
このとき親鸞聖人は80歳になっていました。聖人の人生は波瀾万丈です。幼くして親と死別し、出家の道を選んだものの、覚りの開けぬ苦しい日々が続きました。しかしそれも、法然上人に出遇い、本願の世界に目覚めることができました。その歓びの日々も長くは続かず、専修念仏への弾圧で越後への流罪となりました。ようやく流罪が解け新天地の関東で布教に励み、20年後には「ただ念仏」の教えを歓ぶ僧伽ができました。そこで聖人は残された人生を、「ただ念仏」の教え(本願他力の教え)は弱者のなぐさめではなく、これこそ自他共に助かっていく大乗仏教である、ということを明らかにせんとして、『教行信証』の完成に尽力されました。75歳頃には『教行信証』が完成したと思われますが、そのままでは関東のお同行には判りません。そこで、「いなかのひとびと」にも判るように、ご和讃や仮名聖教を次々と書いていたところです。聖人のお気持ちからすれば、「なんとか自分の使命を果たすことができたかな」とほっとされていたのではないでしょうか。そんなところに関東から僧伽崩壊の知らせが舞い込んできたのです。
お手紙のあちこちに、「かえすがえすあわれにかなしうおぼえそうろう」〔聖典五七七頁〕とか「ともかくももうすにおよばずそうろう」〔聖典五九七頁〕とか、「あさましくそうろう、あさましくそうろう」〔聖典五七八頁〕と嘆きの言葉が綴られています。さも、ありなん、であります。
しかし聖人は思い返しました。関東での混乱は「詮ずるところ」、「ひとびとの信心のまことならぬこと」があらわになったのだから「よきことにてそうろう」と。そして、今一度、なぜ、往生浄土の正因たる「真実信心」を獲得できず、造悪無碍の異義に走ったり、善鸞なんかの言葉に迷ってしまうのか、あらためて「信心」の中身について思索されていかれたのです。
こうした誤った考え(異義)を糺(ただ)すために親鸞聖人の子の善鸞(ぜんらん)が関東に赴きましたが、善鸞は異義を糺すどころか、逆に「本願はしぼめる花」などと言って、関東にできた僧伽を混乱に陥れてしまったのです。
このとき親鸞聖人は80歳になっていました。聖人の人生は波瀾万丈です。幼くして親と死別し、出家の道を選んだものの、覚りの開けぬ苦しい日々が続きました。しかしそれも、法然上人に出遇い、本願の世界に目覚めることができました。その歓びの日々も長くは続かず、専修念仏への弾圧で越後への流罪となりました。ようやく流罪が解け新天地の関東で布教に励み、20年後には「ただ念仏」の教えを歓ぶ僧伽ができました。そこで聖人は残された人生を、「ただ念仏」の教え(本願他力の教え)は弱者のなぐさめではなく、これこそ自他共に助かっていく大乗仏教である、ということを明らかにせんとして、『教行信証』の完成に尽力されました。75歳頃には『教行信証』が完成したと思われますが、そのままでは関東のお同行には判りません。そこで、「いなかのひとびと」にも判るように、ご和讃や仮名聖教を次々と書いていたところです。聖人のお気持ちからすれば、「なんとか自分の使命を果たすことができたかな」とほっとされていたのではないでしょうか。そんなところに関東から僧伽崩壊の知らせが舞い込んできたのです。
お手紙のあちこちに、「かえすがえすあわれにかなしうおぼえそうろう」〔聖典五七七頁〕とか「ともかくももうすにおよばずそうろう」〔聖典五九七頁〕とか、「あさましくそうろう、あさましくそうろう」〔聖典五七八頁〕と嘆きの言葉が綴られています。さも、ありなん、であります。
しかし聖人は思い返しました。関東での混乱は「詮ずるところ」、「ひとびとの信心のまことならぬこと」があらわになったのだから「よきことにてそうろう」と。そして、今一度、なぜ、往生浄土の正因たる「真実信心」を獲得できず、造悪無碍の異義に走ったり、善鸞なんかの言葉に迷ってしまうのか、あらためて「信心」の中身について思索されていかれたのです。
弥陀の本願信ずべし
こうしてできあがったのが三帖和讃の一つ『正(しょう)像(ぞう)末(まつ)和讃』でした。この『正像末和讃』の冒頭には、「康(こう)元(げん)二歳 丁巳(ひのとのみ) 二月九日夜 寅時(とらのとき) 夢告云」と但し書きされた、
弥陀の本願信ずべし 本願信ずるひとはみな
摂取不捨の利益にて 無上覚をばさとるなり 〔聖典五〇〇頁〕
摂取不捨の利益にて 無上覚をばさとるなり 〔聖典五〇〇頁〕
という夢告讃が置かれています。関東のお同行たちの信仰の揺らぎは、お同行だけの話ではなく、自からの信心の不徹底の反映だとお受け取りになったのでありましょう。聖人は関東のお同行たちと一つになって、救世菩薩よりあらためて「弥陀の本願信ずべし」と教命されたのでした。
悲泣と悲歎
ところで『正像末和讃』のはじめにおかれている「正像末浄土和讃」58首は、
釈迦如来かくれましまして 二千余年になりたまう
正像の二時はおわりにき 如来の遺弟(ゆいてい)悲(ひ)泣(きゅう)せよ 〔聖典五〇〇頁〕
正像の二時はおわりにき 如来の遺弟(ゆいてい)悲(ひ)泣(きゅう)せよ 〔聖典五〇〇頁〕
で始まっています。
また「正像末浄土和讃」に続いて、、
また「正像末浄土和讃」に続いて、、
不(ふ)了(りょう)仏(ぶっ)智(ち)のしるしには 如来の諸智を疑惑して
罪福信じ善(ぜん)本(ぽん)を たのめば辺(へん)地(ぢ)にとまるなり 〔聖典五〇五頁〕
罪福信じ善(ぜん)本(ぽん)を たのめば辺(へん)地(ぢ)にとまるなり 〔聖典五〇五頁〕
という「不思議の弥陀の御ちかいをうたがう つみとがをしらせんとあらわせる」「仏智疑惑和讃」23首があり、さらには、
浄土真宗に帰すれども 真実の心はありがたし
虚仮不実のわが身にて 清浄の心もさらになし 〔聖典五〇八頁〕
虚仮不実のわが身にて 清浄の心もさらになし 〔聖典五〇八頁〕
という「これは愚禿がかなしみなげきにして述懐としたり」という「愚禿悲歎述懐和讃」16首があります。
造悪無碍の異義や善鸞事件は親鸞聖人が犯した誤りではありません。ですから、普通なら同行たちの信心を問題にするところでありましょう。ところが親鸞聖人はそれを自己の内に問い直されて、「仏智疑惑和讃」や「愚禿悲歎述懐和讃」をお造りなられました。
造悪無碍の異義や善鸞事件は親鸞聖人が犯した誤りではありません。ですから、普通なら同行たちの信心を問題にするところでありましょう。ところが親鸞聖人はそれを自己の内に問い直されて、「仏智疑惑和讃」や「愚禿悲歎述懐和讃」をお造りなられました。
恩徳讃
こうした「機の深信」の徹底において、
弥陀の五(ご)劫(こう)思(し)惟(ゆい)の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人(いちにん)がためなりけり。されば、そくばくの業をもちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ。 〔『歎異抄』六四〇頁〕
という「法の深信」となるのでありましょう。
「正像末浄土和讃」は、
「正像末浄土和讃」は、
如来大悲の恩徳は 身を粉にしても報ずべし
師主知識の恩徳も ほねをくだきても謝すべし 〔聖典五〇五頁〕
師主知識の恩徳も ほねをくだきても謝すべし 〔聖典五〇五頁〕
という「恩徳讃」で終わっているのです。
このように「悲歎」と「讃嘆」とが一つであるのが親鸞聖人の教えて下さった「真実信心」であります。
このように「悲歎」と「讃嘆」とが一つであるのが親鸞聖人の教えて下さった「真実信心」であります。
聖人の御入滅
さて、今日は11月28日、親鸞聖人が浄土へ還られた日ですが、聖人の御往生はどんな感じだったのでしょうか。その様子について、聖人の曾孫にあたる覚如上人は『御伝鈔』に次のように記しています。
聖人弘長(こうちよう)二歳(さい) 壬戌(みずのえいぬ) 仲冬(ちゆうとう)下旬の候より、いささか不(ふ)例(れい)の気まします。自爾以来(それよりこのかた)、口に世(せ)事(じ)をまじえず、ただ仏恩のふかきことをのぶ。声に余言(よごん)をあらわさず、もっぱら称名たゆることなし。しこうして同第八日午時(うまのとき)、頭(ず)北(ほく)面(めん)西(さい)右(う)脇(きょう)に臥(ふ)し給(たま)いて、ついに念仏の息たえましましおわりぬ。時に、頽齢(たいれい)九旬に満ちたまう。 〔聖典七三六頁〕
聖人の御往生の様子が実に簡潔に述べられております。「口に世事をまじえず、ただ仏恩のふかきことをのぶ。声に余言をあらわさず、もっぱら称名たゆることなし」というお姿に掌が合わされます。「ついに念仏の息たえましましおわりぬ」と聞き、聖人の御生涯が想い起こされ、聖人のご苦労に報恩謝徳のお念仏が申されます。聖人の最期の姿は、「自然(じねん)法(ほう)爾(に)」の世界を生きられた聖人にまことにふさわしいものでありました。
聖人の御往生の様子が実に簡潔に述べられております。「口に世事をまじえず、ただ仏恩のふかきことをのぶ。声に余言をあらわさず、もっぱら称名たゆることなし」というお姿に掌が合わされます。「ついに念仏の息たえましましおわりぬ」と聞き、聖人の御生涯が想い起こされ、聖人のご苦労に報恩謝徳のお念仏が申されます。聖人の最期の姿は、「自然(じねん)法(ほう)爾(に)」の世界を生きられた聖人にまことにふさわしいものでありました。
法然上人の御往生
聖人の御臨終に立ち会われた末娘の覚信尼は、火葬を終えた12月1日、越後の母・恵信尼に手紙を書きました。そのお手紙は残っていませんが、それを受け取られた恵信尼の返事が残っています。そこには、「されば、御臨終はいかにもわたらせ給え、疑い思いまいらせぬうえ、云々」〔『恵信尼消息』六一八頁〕という言葉が出てきます。どうやら覚信尼は、聖人の御臨終の姿を見て、本当に浄土へ往生できたのか疑問をもったようです。
それというのも、法然上人の御往生について、聖人ご自身が
それというのも、法然上人の御往生について、聖人ご自身が
本師(ほんじ)源空のおわりには 光明紫雲のごとくなり
音楽哀婉(あいえん)雅亮(がりよう)にて 異香(いきよう)みぎりに暎芳(えいほう)す 〔聖典四九九頁〕
と歌われていたからです。親鸞聖人ご自身は法然上人の御往生に立ち会われていません。遠く越後の空から遙かに京を拝すばかりでした。しかし、聖人の編纂された『西(さい)方(ほう)指(し)南(なん)抄(しょう)』には、法然上人の最期の様子を伝える「法然上人臨終行儀」「諸人霊夢記」「源空私日記」が納められていて、そこには法然上人の御往生に際しておこった摩訶不思議な奇(き)瑞(ずい)が縷々伝えられています。それらは、端的に言えば、臨終にあたり阿弥陀仏が来迎したという奇瑞でした。
たしかに、法然上人は専修念仏を提唱しました。往生にあたり、弟子の勧める臨終行儀を断っています。それというのも法然上人には、法然上人を迎えに来た阿弥陀如来が観えていたからでした。弟子には観えず法然上人だけに観えていたということは、人々にいよいよ不可思議な思いを生み、さらには京中の人々が「霊夢」を観ることを誘発したのではないでしょうか。法然上人ご自身の信心はともかく、人々にとっては、上人の御往生は、阿弥陀如来が来迎してお浄土へ連れていってもらった、というものでした。聖人も人々の間で言い伝えられたそうした逸話に基づき御和讃を作られたのだと思います。
娘の覚信尼は親鸞聖人の御往生にあたり、そうした不思議な奇瑞を心待ちしたのかもしれません。しかし、なんにもありませんでした。「口に世事をまじえず、ただ仏恩のふかきことをのぶ。声に余言をあらわさず、もっぱら称名たゆることなし。… ついに念仏の息たえましましおわりぬ」というものでした。聖人が繰り返し教えられていた通り、
音楽哀婉(あいえん)雅亮(がりよう)にて 異香(いきよう)みぎりに暎芳(えいほう)す 〔聖典四九九頁〕
と歌われていたからです。親鸞聖人ご自身は法然上人の御往生に立ち会われていません。遠く越後の空から遙かに京を拝すばかりでした。しかし、聖人の編纂された『西(さい)方(ほう)指(し)南(なん)抄(しょう)』には、法然上人の最期の様子を伝える「法然上人臨終行儀」「諸人霊夢記」「源空私日記」が納められていて、そこには法然上人の御往生に際しておこった摩訶不思議な奇(き)瑞(ずい)が縷々伝えられています。それらは、端的に言えば、臨終にあたり阿弥陀仏が来迎したという奇瑞でした。
たしかに、法然上人は専修念仏を提唱しました。往生にあたり、弟子の勧める臨終行儀を断っています。それというのも法然上人には、法然上人を迎えに来た阿弥陀如来が観えていたからでした。弟子には観えず法然上人だけに観えていたということは、人々にいよいよ不可思議な思いを生み、さらには京中の人々が「霊夢」を観ることを誘発したのではないでしょうか。法然上人ご自身の信心はともかく、人々にとっては、上人の御往生は、阿弥陀如来が来迎してお浄土へ連れていってもらった、というものでした。聖人も人々の間で言い伝えられたそうした逸話に基づき御和讃を作られたのだと思います。
娘の覚信尼は親鸞聖人の御往生にあたり、そうした不思議な奇瑞を心待ちしたのかもしれません。しかし、なんにもありませんでした。「口に世事をまじえず、ただ仏恩のふかきことをのぶ。声に余言をあらわさず、もっぱら称名たゆることなし。… ついに念仏の息たえましましおわりぬ」というものでした。聖人が繰り返し教えられていた通り、
真実信心の行人は、摂取不捨のゆえに、正定聚のくらいに住す。このゆえに、臨終まつことなし、来迎たのむことなし。信心のさだまるとき、往生またさだまるなり。来迎の儀式をまたず。 〔『末燈鈔』六〇〇頁〕
の御往生だったのです。聖人の最後は現生(げんしよう)正定聚(しようじようじゆ)の教えを身をもって証明するものでした。
臨終来迎
そもそも、臨終の来迎を頼む往生と、臨終の来迎を頼む必要のない往生とは、どう違うのでしょうか。『往生要集』を書いた源信僧都は志を同じくする二十五人の仲間と「二十五三昧会」という秘密の念仏結社をつくり、日頃から念仏行にいそしみ、臨終に際してはお互いに導きあって間違いなく来迎にあずかるよう準備しました。しかし「正念場」という言葉があるように、臨終の時に痛みや不安で狂乱し「正念」に住することができぬかもしれません。そうすればそれまでの努力もみな虚しいことになります。往生が死後のことである限り、生前には往生の可・不可は不明であります。臨終の瞬間、正念を失って、来迎にあずかり損ねた時のために、源信僧都たちは「光明(こうみよう)真言(しんごん)土砂加持(どしやかじ)」といって、光明真言によって加持した土砂を墓にまいたりしているのです。
自然法爾
このように聖人以前の人々は、「浄土は来世にあり、当然、そこに往くのも来世」と了解していました。そうした浄土は地獄と対になった浄土であります。また、阿弥陀如来は来世の浄土に住するものとして、臨終の際の来迎がもっとも近づくのであって、決して今生の私にまでは届かぬ存在でした。
それに対し親鸞聖人の浄土観は、今生のことでした。なぜなら、弥陀の浄土は物理的な場所ではなかったのです。「西方十万億仏土の彼方」とは心の距離、迷いの深さでした。摂取不捨の心光こそが如来の浄土ではないでしょうか。如来は「罪悪深重煩悩熾盛の衆生」の私たちを深く矜哀(こうあい)されて本願を発(おこ)されました。本願はただ今の私のためです。
それに対し親鸞聖人の浄土観は、今生のことでした。なぜなら、弥陀の浄土は物理的な場所ではなかったのです。「西方十万億仏土の彼方」とは心の距離、迷いの深さでした。摂取不捨の心光こそが如来の浄土ではないでしょうか。如来は「罪悪深重煩悩熾盛の衆生」の私たちを深く矜哀(こうあい)されて本願を発(おこ)されました。本願はただ今の私のためです。
本願力にあいぬれば むなしくすぐるひとぞなき
功徳の宝海みちみちて 煩悩の濁水へだてなし 〔天親讃四九〇頁〕
この本願こそ、煩悩具足の私をして仏道を歩ましめさせるはたらきの場、つまり浄土ではないでしょうか。親鸞聖人においては、浄土は地獄と対になって死後に待っている存在ではなく、自身の生死を包む世界として、また自他のいのちを包む世界として、目覚めればここにはたらいてある世界でした。だから聖人にとって浄土とは、地獄と対(つい)になった世界ではなく、迷いの流(る)転(てん)(生死流転)を超えた目覚め(出離生死)の世界なのです。
聖人はかって自分のいのちをねらった山伏弁円(べんねん)こと明法房の往生について、「明法御坊の往生のこと、おどろきもうすべきにはあらねども、かえすがえすうれしうそうろう」〔『親鸞聖人御消息集(広本)』五六〇頁〕と述べられました。
また86歳の御消息の最後には、
功徳の宝海みちみちて 煩悩の濁水へだてなし 〔天親讃四九〇頁〕
この本願こそ、煩悩具足の私をして仏道を歩ましめさせるはたらきの場、つまり浄土ではないでしょうか。親鸞聖人においては、浄土は地獄と対になって死後に待っている存在ではなく、自身の生死を包む世界として、また自他のいのちを包む世界として、目覚めればここにはたらいてある世界でした。だから聖人にとって浄土とは、地獄と対(つい)になった世界ではなく、迷いの流(る)転(てん)(生死流転)を超えた目覚め(出離生死)の世界なのです。
聖人はかって自分のいのちをねらった山伏弁円(べんねん)こと明法房の往生について、「明法御坊の往生のこと、おどろきもうすべきにはあらねども、かえすがえすうれしうそうろう」〔『親鸞聖人御消息集(広本)』五六〇頁〕と述べられました。
また86歳の御消息の最後には、
この身はいまはとしきわまりてそうらえば、さだめてさきだちて往生しそうらわんずれば、浄土にてかならずかならずまちまいらせそうろうべし。〔『末燈鈔』第12通六〇六頁〕
と書かれております。
さらには人々の間で聖人の御遺言として口伝えされてきた「御臨末(ごりんまつ)の御(ご)書(しょ)」には、
さらには人々の間で聖人の御遺言として口伝えされてきた「御臨末(ごりんまつ)の御(ご)書(しょ)」には、
我が歳きわまりて、安養の浄土に還帰すというとも、和歌の浦曲(うらわ)の片(かた)男(お)浪(なみ)の、寄せかけ寄せかけ帰らんに同じ。一人居て喜ばは二人と思うべし、二人居て喜ばは三人と思うべし、その一人は親鸞なり。我なくも法(のり)は尽きまじ和歌の浦あをくさ人のあらん限りは。
とあります。
親鸞聖人以前の念仏者たちにあった、地獄に堕ちるか極楽に往けるかという必死な形相は消え去り、深い寂けさをたたえた自(じ)然(ねん)法(ほう)爾(に)の世界が広がっています。
聖人の御往生は浄土真宗のまことを示した身業説法(しんごうせつぽう)でありました。
とあります。
親鸞聖人以前の念仏者たちにあった、地獄に堕ちるか極楽に往けるかという必死な形相は消え去り、深い寂けさをたたえた自(じ)然(ねん)法(ほう)爾(に)の世界が広がっています。
聖人の御往生は浄土真宗のまことを示した身業説法(しんごうせつぽう)でありました。