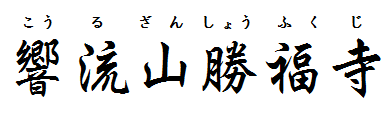響流山勝福寺 宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌・お待ち受け聞法会
宗祖親鸞聖人のご生涯 ⑥ (2018年10月13日)
藤谷知道
「浄土真宗」の開顕 ― 再び京へ ー
天福二年、聖人62歳の頃、東国での20年にわたる布教に終わりをつげて京に帰られました。その理由について、聖人は何も語っていませんが、聖人、畢生の事業であった『顕浄土真実教行証文類』を完成させるために京に帰ることを決断された、と思います。
聖人は『教行信証』以外にもたくさんのお聖教を書かれましたが、それらはすべて76歳以降です。主なものをあげると、76歳『浄土和讃』『高僧和讃』、78歳『唯信鈔文意』、80歳『浄土文類聚鈔』、83歳『尊号真像銘文』『愚禿鈔』『浄土三経往生文類』、84歳『入出二門偈』『西方指南抄』書写、85歳『正像末和讃』『一念多念文意』などです。
また、聖人のお手紙は全部で43通残っていますが、覚信尼あての「いやおんなのこと」という年代不明のもの以外はすべて79歳以降です。なぜ、それまで一通もないのでしょうか。これもまた、聖人の著作についても見られたように、60代から70代中頃までは思索に傾注し、70代後半からの晩年はまた「自信教人信」の使命を果たすことに身を捧げられたことのあらわれでないでしょうか。
最後になりましたが、東国の弟子たちにあてた仮名聖教や御消息類の署名は「愚禿親鸞」とか「親鸞」となっており、そこには「釋」の一字が入っていません。それらは「非僧非俗」を立場として生きられた聖人のの精神をあらわしていると思います。
それに対し、『顕浄土真実教行証文類』には「愚禿釋親鸞」と「釋」の一字を入れて署名しています。「非僧非俗」を立場とされた親鸞聖人なのに、なぜ、あえて「釋」の一字を入れられたのでしょうか。そこには、何のために『顕浄土真実教行証文類』を書かずにおれなかったのか、という執筆の動機と深く関係していると思います。「愚禿釋親鸞」の名において、「浄土真宗」は日本の片隅に開いたいた一宗教では決してなく、時代を超え、所を越えて、すべての人に通じる教えであることを証明するためであったからでありましょう。
聖人は『教行信証』以外にもたくさんのお聖教を書かれましたが、それらはすべて76歳以降です。主なものをあげると、76歳『浄土和讃』『高僧和讃』、78歳『唯信鈔文意』、80歳『浄土文類聚鈔』、83歳『尊号真像銘文』『愚禿鈔』『浄土三経往生文類』、84歳『入出二門偈』『西方指南抄』書写、85歳『正像末和讃』『一念多念文意』などです。
また、聖人のお手紙は全部で43通残っていますが、覚信尼あての「いやおんなのこと」という年代不明のもの以外はすべて79歳以降です。なぜ、それまで一通もないのでしょうか。これもまた、聖人の著作についても見られたように、60代から70代中頃までは思索に傾注し、70代後半からの晩年はまた「自信教人信」の使命を果たすことに身を捧げられたことのあらわれでないでしょうか。
最後になりましたが、東国の弟子たちにあてた仮名聖教や御消息類の署名は「愚禿親鸞」とか「親鸞」となっており、そこには「釋」の一字が入っていません。それらは「非僧非俗」を立場として生きられた聖人のの精神をあらわしていると思います。
それに対し、『顕浄土真実教行証文類』には「愚禿釋親鸞」と「釋」の一字を入れて署名しています。「非僧非俗」を立場とされた親鸞聖人なのに、なぜ、あえて「釋」の一字を入れられたのでしょうか。そこには、何のために『顕浄土真実教行証文類』を書かずにおれなかったのか、という執筆の動機と深く関係していると思います。「愚禿釋親鸞」の名において、「浄土真宗」は日本の片隅に開いたいた一宗教では決してなく、時代を超え、所を越えて、すべての人に通じる教えであることを証明するためであったからでありましょう。
僧伽崩壊の危機 ― 異義の広がり ー
先に、親鸞聖人の御消息のほとんどが79歳からのものと言いましたが、そこには、聖人が東国を去って月日が経つほどに聖人の教えが判らなくなり、その結果として、真実信心にほど遠い異義が広がっていったということがありました。
そのため、あちこちにできていた門徒のグループは、親鸞聖人に直接教えを聞こうと、代表を選んで京にのぼりました。その様子が『歎異抄』第二章に出てくる、「おのおの十余か国のさかいをこえて、身命をかえりみずして、たずねきたらしめたまう御こころざし、ひとえに往生極楽のみちをといきかんがためなり」〔聖典六二七頁〕であります。
それでは何を聞いたかというと、それが「念仏よりほかに往生のみちをも存知し、また法文等をもしりたるらん」という、親鸞聖人に対する疑念でした。親鸞聖人はそれに対し「おおきなるあやまりなり」と即答されています。
東国の弟子たちは、なぜ、「念仏よりほかに往生のみちをも存知し、また法文等をもしりたるらん」と思われたのでしょうか? それは「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし」という単純極まりない道理は、聖人ご自身が「親鸞におきては ・・・ よきひとのおおせをかぶりて信ずる」と告白されているように、その教えを生きる「よきひと」を信ずることを通してこそ、はじめて信じることができるものであるからです。
ですから、もしその教えを説くよきひとが眼前からいなくなったら、その教えが単純極まりないだけに、複雑なほど貴いように思えるようになっている人間の頭では信楽受持することができなくなるのです。かくして、「ただ念仏」の教えが、いつしか難しい教理問答のようになり、もつれた糸をほどくべく、「身命をかえりみずして(身の危険を冒してまでも)」親鸞聖人を尋ねたのでありましょう。
そのため、あちこちにできていた門徒のグループは、親鸞聖人に直接教えを聞こうと、代表を選んで京にのぼりました。その様子が『歎異抄』第二章に出てくる、「おのおの十余か国のさかいをこえて、身命をかえりみずして、たずねきたらしめたまう御こころざし、ひとえに往生極楽のみちをといきかんがためなり」〔聖典六二七頁〕であります。
それでは何を聞いたかというと、それが「念仏よりほかに往生のみちをも存知し、また法文等をもしりたるらん」という、親鸞聖人に対する疑念でした。親鸞聖人はそれに対し「おおきなるあやまりなり」と即答されています。
東国の弟子たちは、なぜ、「念仏よりほかに往生のみちをも存知し、また法文等をもしりたるらん」と思われたのでしょうか? それは「ただ念仏して、弥陀にたすけられまいらすべし」という単純極まりない道理は、聖人ご自身が「親鸞におきては ・・・ よきひとのおおせをかぶりて信ずる」と告白されているように、その教えを生きる「よきひと」を信ずることを通してこそ、はじめて信じることができるものであるからです。
ですから、もしその教えを説くよきひとが眼前からいなくなったら、その教えが単純極まりないだけに、複雑なほど貴いように思えるようになっている人間の頭では信楽受持することができなくなるのです。かくして、「ただ念仏」の教えが、いつしか難しい教理問答のようになり、もつれた糸をほどくべく、「身命をかえりみずして(身の危険を冒してまでも)」親鸞聖人を尋ねたのでありましょう。
難信
このことは宗教の本質に関わることなので、もう少し考えてみたいと思います。
親鸞聖人は正信偈の「依経段」を「弥陀仏の本願念仏は、邪見驕慢の悪衆生、信楽を受持すること、はなはだもって難し」の言葉で締めくくっています。なぜなら「他力回向の信心」とは、私(自我意識で成り立つところの私)の分別がおこなう「自力の信心」とは違うからです。「自力の信心」には、その裏に自我の損得勘定が入り込んでおり、本願を信じると言いながら、その実は、本願を利用して自分はうまいこと助かろうという、そんな心でしかありません。この自我が折れることが至難なんです。自我が折れて、本願に乗托していく無我なる心、つまり真実信心をたまわることは「難中之難無過斯(難の中の難、これに過ぎたるはなし)」であります。
親鸞聖人は正信偈の「依経段」を「弥陀仏の本願念仏は、邪見驕慢の悪衆生、信楽を受持すること、はなはだもって難し」の言葉で締めくくっています。なぜなら「他力回向の信心」とは、私(自我意識で成り立つところの私)の分別がおこなう「自力の信心」とは違うからです。「自力の信心」には、その裏に自我の損得勘定が入り込んでおり、本願を信じると言いながら、その実は、本願を利用して自分はうまいこと助かろうという、そんな心でしかありません。この自我が折れることが至難なんです。自我が折れて、本願に乗托していく無我なる心、つまり真実信心をたまわることは「難中之難無過斯(難の中の難、これに過ぎたるはなし)」であります。
言葉で迷う
なぜでしょうか。それは、宗教的に獲得された境地は言葉で表現される、ということに関係しています。ことに仏教は、「仏法」とも言われるように「法」に目覚めていく教えであり、その「法」は言葉で表現されます。そこが他の世界との大きな違いです。
ところが人間の知性(分別)は、言葉を聞くとその意味を考え、意味がわかるとその言葉で言い表そうとしていた世界も判ったと勘違いするようになっているのです。つまり、人間は言葉によって目覚めもするが、言葉によって迷いもする存在なのです。厳密に言えば、人間は言葉によってまず迷うものです。迷いに迷って、ようやく迷いに気づき、気づくことを通してはじめて目覚めに至るのです。
ところが人間の知性(分別)は、言葉を聞くとその意味を考え、意味がわかるとその言葉で言い表そうとしていた世界も判ったと勘違いするようになっているのです。つまり、人間は言葉によって目覚めもするが、言葉によって迷いもする存在なのです。厳密に言えば、人間は言葉によってまず迷うものです。迷いに迷って、ようやく迷いに気づき、気づくことを通してはじめて目覚めに至るのです。
義なきを義とす
親鸞聖人の御消息によれば、一念・多念の諍論や、有念・無念の諍論があったことがうかがわれます。一念・多念の諍論とは、往生には一念で足たれとするのか、それとも、一声でも多く念仏する方がいいのか、という論争です。有念・無念の諍論とは、阿弥陀仏やその浄土を心に想うて念仏すべきか、それとも無念無想で念仏すべきか、という諍論です。
親鸞聖人は、そのような論争自体が自力聖道の考え方だとしりぞけられました。つまり、教えの言葉を小賢しく解釈することは仏智を疑惑した相(すがた)なんだと知らせ、「往生は、ともかくも凡夫のはからいにてすべきことにてもそうらわず。・・ただ願力にまかせてこそおわします」〔聖典五六三頁〕と諭し、他力にあっては「義なきを義とす」〔聖典頁〕と繰りかえされたのでした。
親鸞聖人は、そのような論争自体が自力聖道の考え方だとしりぞけられました。つまり、教えの言葉を小賢しく解釈することは仏智を疑惑した相(すがた)なんだと知らせ、「往生は、ともかくも凡夫のはからいにてすべきことにてもそうらわず。・・ただ願力にまかせてこそおわします」〔聖典五六三頁〕と諭し、他力にあっては「義なきを義とす」〔聖典頁〕と繰りかえされたのでした。
造悪無碍
こうした一念多念、有念無念という観念的な論争よりも、もっと深刻だったのが造(ぞう)悪(あく)無(む)碍(げ)の異義でした。造悪無碍とは「煩悩具足の身なれば、こころにもまかせ、身にもすまじきことをもゆるし、口にもいうまじきことをもゆるし、こころにもおもうまじきことをもゆるして、いかにもこころのままにあるべし」(『親鸞聖人御消息集』第一通〔聖典五六一頁〕)と、煩悩を正当化し居直っていく考えです。こうした「造悪無碍」(何をしても差し支えなし)の考えは、「自我」にとって、道徳という箍(たが)を断ち自分を自由にしてくれる麻薬みたいなものではないでしょうか。「悪人正機」を説く専修念仏の教えのあるところ、造悪無碍の邪義は繰り返し巻き返し出てきます。
それは法然上人の時にもありました。そのため専修念仏は世の道徳を破壊するものとして、専修念仏を弾圧する口実に使われました。同じように、東国の地でも造悪無碍の邪義は繰り返し出てきました。ことに親鸞聖人が東国を去って時間が経つほどに、造悪無碍の邪義は大きくなっていったようです。
それは法然上人の時にもありました。そのため専修念仏は世の道徳を破壊するものとして、専修念仏を弾圧する口実に使われました。同じように、東国の地でも造悪無碍の邪義は繰り返し出てきました。ことに親鸞聖人が東国を去って時間が経つほどに、造悪無碍の邪義は大きくなっていったようです。
悪人正機の教え
親鸞聖人の開顕された浄土真宗は「悪人正機」の教えと言われます。「悪人正機」とは、『歎異抄』に「善人なおもて往生をとぐ、いわんや悪人をや」〔聖典六二七頁〕とあるように、「善人」よりも「悪人」の方こそ阿弥陀仏の本願のお目当てである、という教えです。
それはどういうことかというと、本願は「いつでも、どこでも、誰にでも」救いの手を差しのべてくださっていますが、人間の悲しき宿業とでも言いましょうか、そんな無条件の救済を、曠劫来流転してきた人間の心は信ずることができないのです。それはこの私の実感でもあります。
たとえて言えば、泳ぎの上手な人が水にぷかっと浮いてみせ、「こんな風に力を抜いたら浮かぶよ」と勧められても、泳ぎのできない人は怖くって水に身を任せることができないのと同じです。ましてや、自分の力で善業を積めると思っている間は本願を頼む気になど絶対になりません。だから『歎異抄』では「自力作善のひとは、ひとえに他力をたのむこころかけたるあいだ、弥陀の本願にあらず」〔同〕と言われているのです。
ところが、どんなにもがいても悪業しかできず、こんな私は地獄に堕ちるしかないのか、となった時、はじめて弥陀の本願を頼んでみようという心が生まれてくるのです。それを『歎異抄』では「煩悩具足のわれらは、いずれの行にても、生死をはなるることあるべからざるをあわれみたまいて、願をおこしたまう本意、悪人成仏のためなれば、他力をたのみたてまつる悪人、もっとも往生の正因なり」〔同〕と教えてくださっているのです。
つまり「悪人正機」の教えの眼目は、本気でご本願を頼む者は誰か、というところにあるのです。「悪人」と言っても、それは「罪悪生死の凡夫」であることを悲しみ弥陀を頼むことになった「悪人」のことです。
ところが人間の心はずる賢くできていて、これ幸いにと、この教えに飛びついて、「悪」を畏れることなどいらない、助かるためには「悪」をたくさんつくった方がいいんだ、と自分に都合の良いように解釈する者が出て来るのです。そしてその者は、必ずと言っていいほど、「赤信号みんなで渡れば怖くない」の類いで、他の人を巻き込んでいくことになるのです。これが「造悪無碍」の邪義です。人間の悲しみに深く寄り添った「悪人正機」の教えも、それを自我で握ってしまえば、世の道徳を破壊する邪教となってしまうということです。このように、宗教には道徳を超えるか、道徳の破壊者となるか、紙一重のところがあります。
善鸞義絶
それはどういうことかというと、本願は「いつでも、どこでも、誰にでも」救いの手を差しのべてくださっていますが、人間の悲しき宿業とでも言いましょうか、そんな無条件の救済を、曠劫来流転してきた人間の心は信ずることができないのです。それはこの私の実感でもあります。
たとえて言えば、泳ぎの上手な人が水にぷかっと浮いてみせ、「こんな風に力を抜いたら浮かぶよ」と勧められても、泳ぎのできない人は怖くって水に身を任せることができないのと同じです。ましてや、自分の力で善業を積めると思っている間は本願を頼む気になど絶対になりません。だから『歎異抄』では「自力作善のひとは、ひとえに他力をたのむこころかけたるあいだ、弥陀の本願にあらず」〔同〕と言われているのです。
ところが、どんなにもがいても悪業しかできず、こんな私は地獄に堕ちるしかないのか、となった時、はじめて弥陀の本願を頼んでみようという心が生まれてくるのです。それを『歎異抄』では「煩悩具足のわれらは、いずれの行にても、生死をはなるることあるべからざるをあわれみたまいて、願をおこしたまう本意、悪人成仏のためなれば、他力をたのみたてまつる悪人、もっとも往生の正因なり」〔同〕と教えてくださっているのです。
つまり「悪人正機」の教えの眼目は、本気でご本願を頼む者は誰か、というところにあるのです。「悪人」と言っても、それは「罪悪生死の凡夫」であることを悲しみ弥陀を頼むことになった「悪人」のことです。
ところが人間の心はずる賢くできていて、これ幸いにと、この教えに飛びついて、「悪」を畏れることなどいらない、助かるためには「悪」をたくさんつくった方がいいんだ、と自分に都合の良いように解釈する者が出て来るのです。そしてその者は、必ずと言っていいほど、「赤信号みんなで渡れば怖くない」の類いで、他の人を巻き込んでいくことになるのです。これが「造悪無碍」の邪義です。人間の悲しみに深く寄り添った「悪人正機」の教えも、それを自我で握ってしまえば、世の道徳を破壊する邪教となってしまうということです。このように、宗教には道徳を超えるか、道徳の破壊者となるか、紙一重のところがあります。
善鸞義絶
そうした中、京から、親鸞聖人の名代を自称する「善鸞*」がやってきました。善鸞は親鸞聖人の子どもです。東国の弟子たちはきっと、善鸞に対し、親鸞聖人に替わって自分たちを導いてくれることを期待したことでしょう。しかし、結果から言うと、そうではありませんでした。善鸞はとんでもない異義を吹聴し東国教団をいっそうの混乱に陥れてしまったのでした。
建長7年11月9日(親鸞聖人83歳)付けの消息によれば、「慈信坊のくだりて、わがききたる法文こそまことにてはあれ、ひごろの念仏はみないたずらごとなり」と言いふらし、その結果、「おおぶの中太郎のかたのひとびとは、九十なん人とかや、みな慈信坊のかたへとて、中太郎入道をすてたる」〔聖典五七五頁〕ということが起こりました。
また翌建長8年正月9日付けの消息によれば、「これよりは余のひとを強縁として念仏ひろめよ」〔聖典五七七頁〕と親鸞聖人が言った、と言いふらしています。「余のひとを強縁として」とは「権力者に取り入って」ということです。この前後、東国のリーダーであった性信が鎌倉幕府に呼び出され、弾圧の危機にありました。そんな中で善鸞が言った「これよりは余のひとを強縁として念仏ひろめよ」の一言は、承元の法難に際し決して妥協しなかった親鸞聖人には信じられない暴言であったことでしょう。
そしてついに、建長8年5月29日、親鸞聖人はわが子善鸞を義絶し、東国の門弟たちにそれを公表しました。それが「善鸞義絶状」と呼ばれる消息です。「慈信一人に、よる親鸞がおしえた」〔聖典六一一頁〕と秘事法門をよそおい、こともあろうに「第十八の本願をば、しぼめるはなにたとえて、人ごとにみな(弥陀の本願を)すてまいらせた」ことは「ほうぼうのとが、五逆のつみ」だと断罪し、慈信については「いまは、おやということあるべからず、ことおもうことおもいきりた」りと、「三宝・神明にもうしきりおわりぬ」〔聖典六一二頁〕と書き記すことになりました。
建長7年11月9日(親鸞聖人83歳)付けの消息によれば、「慈信坊のくだりて、わがききたる法文こそまことにてはあれ、ひごろの念仏はみないたずらごとなり」と言いふらし、その結果、「おおぶの中太郎のかたのひとびとは、九十なん人とかや、みな慈信坊のかたへとて、中太郎入道をすてたる」〔聖典五七五頁〕ということが起こりました。
また翌建長8年正月9日付けの消息によれば、「これよりは余のひとを強縁として念仏ひろめよ」〔聖典五七七頁〕と親鸞聖人が言った、と言いふらしています。「余のひとを強縁として」とは「権力者に取り入って」ということです。この前後、東国のリーダーであった性信が鎌倉幕府に呼び出され、弾圧の危機にありました。そんな中で善鸞が言った「これよりは余のひとを強縁として念仏ひろめよ」の一言は、承元の法難に際し決して妥協しなかった親鸞聖人には信じられない暴言であったことでしょう。
そしてついに、建長8年5月29日、親鸞聖人はわが子善鸞を義絶し、東国の門弟たちにそれを公表しました。それが「善鸞義絶状」と呼ばれる消息です。「慈信一人に、よる親鸞がおしえた」〔聖典六一一頁〕と秘事法門をよそおい、こともあろうに「第十八の本願をば、しぼめるはなにたとえて、人ごとにみな(弥陀の本願を)すてまいらせた」ことは「ほうぼうのとが、五逆のつみ」だと断罪し、慈信については「いまは、おやということあるべからず、ことおもうことおもいきりた」りと、「三宝・神明にもうしきりおわりぬ」〔聖典六一二頁〕と書き記すことになりました。
「善鸞」の正体
それにしても、耳を疑うような話です。善鸞は、なぜ、ここまでひどい教説をはいたのでしょうか。
ここで少し善鸞について考えてみたいと思います。まず善鸞は誰の子かということがあります。善鸞義絶状に出てくる「ままはは」という言葉から、恵信尼に先だって結婚した人の子でないかという説がありますが、私は平松令三氏が言うように、親鸞聖人と恵信尼との間に生まれた子と考えて間違いないと思ってます。ただし、善鸞は親鸞聖人の身近で育ち、念仏の教えを親しく教授されたわけではありません。
覚如の伝記『慕帰絵(ぼきえ)』には善鸞のことを「慈信房(じしんぼう) 元(もと) 宮(く)内(ない)卿(きょう) 善鸞」とあり、『日野一流系図』にも「宮内卿、遁(とん)世(せい)号(ごう) 慈信房」とあります。「宮内卿」というのは「公(きみ)名(な)」といって、比叡山での僧の呼び方です。親鸞聖人が比叡山時代「範(はん)宴(ねん)少(しょう)納(な)言(ごん)」と、「範宴」に自己の出自を誇示する「少納言」という「公名」をつけていたのと同じです。
善鸞も幼くして出家し、比叡山で仏教を学んだようです。これは善鸞だけのことでなく、親鸞聖人の兄弟も、本願寺教団の基礎を造った覚如も、その長男の存覚も、皆、幼くして出家し、比叡で仏教を学びました。まだまだ浄土真宗の教えを体系的に伝授していく教育機関がなかったからです。
しかし善鸞は、親鸞聖人のように「雑行を棄てて本願に帰す」という回心の体験にいたらなかったのではないでしょうか。自身の宗教心の根幹をなしていたのは天台で学んだ密教のままで、頭の先で親鸞聖人の他力回向の信心を理解しようとしていた程度だったと思われます。
このことは、覚如の伝記『最(さい)須(しゅ)敬(けい)重(ちょう)絵(え)詞(ことば)』や『慕帰絵』に出てくるエピソードからもうかがえます。親鸞聖人の曽孫にあたる覚如は、聖人の行跡を尋ねて東国を旅しましたが、その折、晩年の善鸞に出会っています。一度は、常州小柿の山中で病気になった時、その病床を訪ねた善鸞が、「われ符(ふ)をもって、よろずの災難を治す」と、加持祈祷した護符を飲むように勧めています。また、鎌倉の海岸で、「聖人よりたまわられける無碍光如来の名号・・頸にかけ、馬上にて他事なく念仏」する姿を見ています。その姿は専修念仏の行者のものではなく、念仏するといっても加持祈祷をこととする行者の念仏だったようです。
また、平松令三氏が指摘するように、親鸞聖人ご自身は一度も「善鸞」と言っておりません。「善鸞義絶状」と呼ばれてきた消息においても「慈信」と呼んでいます。社会に公開する義絶状に「名」を書かず房号で済ますということはあり得ないはずです。
それに、親鸞聖人は「親鸞は弟子一人ももたずそうろう」と言われました。だからでありましょう、弟子に「親」や「鸞」の一字を与えるというようなことは、ただの一人もしていません。ましてや「善信」と「親鸞」から一字ずつ取って「善鸞」という名を与えるということなど、考えられないことです。
こうしてみると慈信(善鸞)は自己の信仰に自信がないぶんだけ、虎の威を借る狐のように、「善鸞」と名のることで親鸞聖人の後継者であるかのように自己をアピールし、さらには、自分だけが夜こっそり教えを受けたと秘事法門のごとくカモフラージュして、何が何でも他の有力門弟の上に立とうとしたのではないでしょうか。それにしても、「十八願をしぼめる花にたとえた」とは、あきれてものが言えません。
ここで少し善鸞について考えてみたいと思います。まず善鸞は誰の子かということがあります。善鸞義絶状に出てくる「ままはは」という言葉から、恵信尼に先だって結婚した人の子でないかという説がありますが、私は平松令三氏が言うように、親鸞聖人と恵信尼との間に生まれた子と考えて間違いないと思ってます。ただし、善鸞は親鸞聖人の身近で育ち、念仏の教えを親しく教授されたわけではありません。
覚如の伝記『慕帰絵(ぼきえ)』には善鸞のことを「慈信房(じしんぼう) 元(もと) 宮(く)内(ない)卿(きょう) 善鸞」とあり、『日野一流系図』にも「宮内卿、遁(とん)世(せい)号(ごう) 慈信房」とあります。「宮内卿」というのは「公(きみ)名(な)」といって、比叡山での僧の呼び方です。親鸞聖人が比叡山時代「範(はん)宴(ねん)少(しょう)納(な)言(ごん)」と、「範宴」に自己の出自を誇示する「少納言」という「公名」をつけていたのと同じです。
善鸞も幼くして出家し、比叡山で仏教を学んだようです。これは善鸞だけのことでなく、親鸞聖人の兄弟も、本願寺教団の基礎を造った覚如も、その長男の存覚も、皆、幼くして出家し、比叡で仏教を学びました。まだまだ浄土真宗の教えを体系的に伝授していく教育機関がなかったからです。
しかし善鸞は、親鸞聖人のように「雑行を棄てて本願に帰す」という回心の体験にいたらなかったのではないでしょうか。自身の宗教心の根幹をなしていたのは天台で学んだ密教のままで、頭の先で親鸞聖人の他力回向の信心を理解しようとしていた程度だったと思われます。
このことは、覚如の伝記『最(さい)須(しゅ)敬(けい)重(ちょう)絵(え)詞(ことば)』や『慕帰絵』に出てくるエピソードからもうかがえます。親鸞聖人の曽孫にあたる覚如は、聖人の行跡を尋ねて東国を旅しましたが、その折、晩年の善鸞に出会っています。一度は、常州小柿の山中で病気になった時、その病床を訪ねた善鸞が、「われ符(ふ)をもって、よろずの災難を治す」と、加持祈祷した護符を飲むように勧めています。また、鎌倉の海岸で、「聖人よりたまわられける無碍光如来の名号・・頸にかけ、馬上にて他事なく念仏」する姿を見ています。その姿は専修念仏の行者のものではなく、念仏するといっても加持祈祷をこととする行者の念仏だったようです。
また、平松令三氏が指摘するように、親鸞聖人ご自身は一度も「善鸞」と言っておりません。「善鸞義絶状」と呼ばれてきた消息においても「慈信」と呼んでいます。社会に公開する義絶状に「名」を書かず房号で済ますということはあり得ないはずです。
それに、親鸞聖人は「親鸞は弟子一人ももたずそうろう」と言われました。だからでありましょう、弟子に「親」や「鸞」の一字を与えるというようなことは、ただの一人もしていません。ましてや「善信」と「親鸞」から一字ずつ取って「善鸞」という名を与えるということなど、考えられないことです。
こうしてみると慈信(善鸞)は自己の信仰に自信がないぶんだけ、虎の威を借る狐のように、「善鸞」と名のることで親鸞聖人の後継者であるかのように自己をアピールし、さらには、自分だけが夜こっそり教えを受けたと秘事法門のごとくカモフラージュして、何が何でも他の有力門弟の上に立とうとしたのではないでしょうか。それにしても、「十八願をしぼめる花にたとえた」とは、あきれてものが言えません。
かえすがえすあわれにかなしうおぼえそうろう
親鸞聖人はそんな善鸞の行状をどんな思いで聞いたでしょうか。外から来る弾圧よりも、はるかにつらい、それこそ気も萎えてしまう出来事であったことでしょう。
また、「さしもたしかなる証文を、ちからをつくしてかずあまたかきてまいらせて」〔聖典五九七頁〕きた東国の門弟たちが、「慈信坊にすかされて、信心みなうかれおうて」しまったことを、どんな思いで聞かれたでしょうか。
親鸞聖人のこれまでの人生を振り返ってみます。
幼くして父と別れ、母と死別することになったた聖人。そのうえ、源平の戦いや養和の大飢饉と、この世に現出した地獄絵を見てしまいました。
9歳で出家し、「後(ご)世(せ)を祈った」叡山での求道は次第に行き詰まり、29歳になった聖人は追い詰められるようにして、六角堂での百日参籠に入りました。するとそこで、救世観音の夢告を受けました。その夢告に順って、20年間におよぶ比叡での学びを棄て、末法の世を生きる一人の凡夫となって、法然上人の仰せのままに「ただ念仏して弥陀にたすけられる」本願念仏の行者とならせていただいのでした。
しかし、その歓びもつかの間、旧仏教からの圧力で専修念仏は停止され、聖人は僧の身分を剥奪され、越後への流罪の身となりました。この流罪生活を逆縁として大地に生きる群萠となり、自らを「愚禿親鸞」と名のるようになりました。ここに正真正銘の在家仏教が確立したのではないでしょうか。
流罪赦(しゃ)免(めん)後は、旧弊に閉じられた京を棄て、新たな文化が生まれ出ようとしていた東国に赴きました。そこでの20年に及ぶ布教で、大地に生きる人々の中に「御同朋・御同行」と互いに呼び合う僧伽が生まれました。
60歳を過ぎ、仏法流通の使命もなんとか果たせたので、残された時間を『顕浄土真実教行証文類』を書き上げることに捧げようと京に帰り、十余年の歳月をかけてようやく『顕浄土真実教行証文類』が完成したと思います。
この時、聖人は70代の半ばでありました。聖人は結果的には90歳まで長生きされましたが、人生50年の時代です、私の推測ではありますが、この時の聖人のお心は「自分の使命はこれで終えた」という満足感にあふれたものであったのではないでしょうか。
ところが、そんな聖人のところに、東国の方からあやしげな知らせが届くようになってきたのです。はじめは、聖覚法印の『唯信鈔』などを書き与えたり、聖人自ら『浄土和讃』『高僧和讃』などを造ったりして「浄土真宗」の真意を説き明かそうと努力しましたが、その甲斐もなく、人々の間に造悪無碍の異義がはやったり、一念多念の論争など「義」をもてあそぶことが広がっていきました。そして、その極めつけが、善鸞事件であり、鎌倉幕府の念仏停止の動きであったのです。聖人のお気持ちや、いかばかりであったことでしょうか
「かえすがえすあわれにかなしうおぼえそうろう」〔聖典五七七頁〕とか「ともかくももうすにおよばずそうろう」〔聖典五九七頁〕とか、「あさましくそうろう、あさましくそうろう」〔聖典五七八頁〕とかの言葉からは、聖人のため息が聞こえてきそうです。
また、「さしもたしかなる証文を、ちからをつくしてかずあまたかきてまいらせて」〔聖典五九七頁〕きた東国の門弟たちが、「慈信坊にすかされて、信心みなうかれおうて」しまったことを、どんな思いで聞かれたでしょうか。
親鸞聖人のこれまでの人生を振り返ってみます。
幼くして父と別れ、母と死別することになったた聖人。そのうえ、源平の戦いや養和の大飢饉と、この世に現出した地獄絵を見てしまいました。
9歳で出家し、「後(ご)世(せ)を祈った」叡山での求道は次第に行き詰まり、29歳になった聖人は追い詰められるようにして、六角堂での百日参籠に入りました。するとそこで、救世観音の夢告を受けました。その夢告に順って、20年間におよぶ比叡での学びを棄て、末法の世を生きる一人の凡夫となって、法然上人の仰せのままに「ただ念仏して弥陀にたすけられる」本願念仏の行者とならせていただいのでした。
しかし、その歓びもつかの間、旧仏教からの圧力で専修念仏は停止され、聖人は僧の身分を剥奪され、越後への流罪の身となりました。この流罪生活を逆縁として大地に生きる群萠となり、自らを「愚禿親鸞」と名のるようになりました。ここに正真正銘の在家仏教が確立したのではないでしょうか。
流罪赦(しゃ)免(めん)後は、旧弊に閉じられた京を棄て、新たな文化が生まれ出ようとしていた東国に赴きました。そこでの20年に及ぶ布教で、大地に生きる人々の中に「御同朋・御同行」と互いに呼び合う僧伽が生まれました。
60歳を過ぎ、仏法流通の使命もなんとか果たせたので、残された時間を『顕浄土真実教行証文類』を書き上げることに捧げようと京に帰り、十余年の歳月をかけてようやく『顕浄土真実教行証文類』が完成したと思います。
この時、聖人は70代の半ばでありました。聖人は結果的には90歳まで長生きされましたが、人生50年の時代です、私の推測ではありますが、この時の聖人のお心は「自分の使命はこれで終えた」という満足感にあふれたものであったのではないでしょうか。
ところが、そんな聖人のところに、東国の方からあやしげな知らせが届くようになってきたのです。はじめは、聖覚法印の『唯信鈔』などを書き与えたり、聖人自ら『浄土和讃』『高僧和讃』などを造ったりして「浄土真宗」の真意を説き明かそうと努力しましたが、その甲斐もなく、人々の間に造悪無碍の異義がはやったり、一念多念の論争など「義」をもてあそぶことが広がっていきました。そして、その極めつけが、善鸞事件であり、鎌倉幕府の念仏停止の動きであったのです。聖人のお気持ちや、いかばかりであったことでしょうか
「かえすがえすあわれにかなしうおぼえそうろう」〔聖典五七七頁〕とか「ともかくももうすにおよばずそうろう」〔聖典五九七頁〕とか、「あさましくそうろう、あさましくそうろう」〔聖典五七八頁〕とかの言葉からは、聖人のため息が聞こえてきそうです。
よきことにてそうろう
しかし、ため息で終わらないのが聖人です。「流罪」もまた「師教の恩(おん)致(ち)なり」〔『御伝鈔』七二五頁〕と受け止め直されました。弾圧した人に対しても「念仏そしらんひとをたすかれとおぼしめして、念仏しあわせたまうべくそうろう」〔聖典五七八頁〕と仰せになられました。今度は、この出来事を「よきことにてそうろう」と受け止め返されたのでした。
なぜなら、「慈信坊がもうすことによりて、ひとびとの日ごろの信のたじろきおう」たことは、「詮ずるところ」、「ひとびとの信心のまことならぬこと」があらわになったのだから「よきことにてそうろう」と言いきったのです。そして、今一度、なぜ、往生浄土の正因たる「真実信心」を獲得できず、造悪無碍の異義に走ったり、善鸞なんかの言葉に迷ってしまうのか、あらためて「信心」の中身について思索されていかれたと思います。
なぜなら、「慈信坊がもうすことによりて、ひとびとの日ごろの信のたじろきおう」たことは、「詮ずるところ」、「ひとびとの信心のまことならぬこと」があらわになったのだから「よきことにてそうろう」と言いきったのです。そして、今一度、なぜ、往生浄土の正因たる「真実信心」を獲得できず、造悪無碍の異義に走ったり、善鸞なんかの言葉に迷ってしまうのか、あらためて「信心」の中身について思索されていかれたと思います。