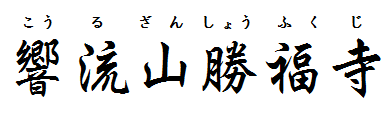宗祖親鸞聖人の御生涯① 誕生~出家
末法の世
― 宗祖の生きられた時代 ―
来年(二〇一一年)は親鸞聖人の七五〇回御遠忌の年となります。90歳でなくなられたのですから、お生まれになったのは八四〇年前となります。つまり、聖人は平安時代の終わりから鎌倉時代の初期を生きられたということです。それはどんな時代だったのでしょうか。
聖人は今から八三七年前の、承(じょう)安(あん)三年(一一七三年)にお生まれになりました。その時代は、奈良、平安と続いた律令国家が機能不全に陥り、社会全体が大混乱に陥っていた時代です。天皇とは名ばかりで、藤原一族の既得権益を守る道具となってしまっていた朝廷(摂関(せっかん)政治)。天皇家の復権を目指す院政(鳥羽上皇、後白河上皇、後鳥羽上皇)。人々を宗教的に呪(じゅ)縛(ばく)して君臨する南都北嶺の巨大寺院(延暦寺、東大寺、興福寺など)。次第に力をつけてきた源平の武士団。人々の嘆きをよそに、この四者による権力闘争が数十年にわたって繰り広げられていました。
鴨(かもの)長(ちょう)明(めい)の『方丈記』には権力闘争の陰で人々におそいかかった悲惨な出来事が縷(る)々(る)書かれています。その一部を紹介すると、
又養和のころかとよ、… 二年が間、世の中飢渇して、あさましきこと侍りき。或は春夏日でり、或は秋冬大風、大水などよからぬ事どもうちつゞきて、五穀ことごとくみのらず。むなしく春耕し、夏植うるいとなみありて、秋かり冬收むるぞめきはなし。これによりて、國々の民、或は地を捨てゝ堺を出で、或は家をわすれて山にすむ。… 仁和寺(にんなじ)に、慈尊院の大藏卿隆曉(りゅうぎょう)法印(ほういん)といふ人、かずしらず死ぬることをかなしみて、その死首の見ゆるごとに、額に阿字を書きて、縁をむすばしむるわざをなむせられける。その人數を知らむとて、四五兩月がほどかぞへたりければ、京の中、一條より南、九條より北、京極より西、朱雀より東、道のほとりにある頭、すべて四萬二千三百あまりなむありける。……
これは養和の大飢饉についての記述ですが、このほか、地震や竜巻、大火事に福原遷都など、人々を次々に襲った災害が書き記されています。
まさに、仏教の説くところの「末(まっ)法(ぽう)の世」の到来であります。人々の、この世への絶望の深まりは『往生要集』(源信僧都)などによって「欣(ごん)求(ぐ)浄(じょう)土(ど)・厭(おん)離(り)穢(え)土(ど)」、― この世を厭い、来世の極楽を願う風潮を生み出しました。次々と『往生伝』が書かれ、日本中に極楽浄土を願う念仏の声が広がっていったのです。親鸞聖人は、社会秩序が崩壊し人々が塗炭の苦しみを強いられる「末法の世」に生まれ、来世への憧(どう)憬(けい)にしがみつくほかなかった社会風潮の中で成長したのでした。
親鸞聖人と末法の時代(聖人誕生前後の時代の様相)
│ 西暦 │和暦 │年齢│ │
│一〇五二・永承 七・ ・最澄『末法灯明記』に、永承七年をもって末法にいる、と記す。
│一一五六・保元 元・ ・保(ほう)元(げん)の乱 清盛、義朝を味方につけた後白河天皇側の勝利。武士が台頭するきっかけとなった。 │
*天皇家(弟・後白河天皇 × 兄・崇徳上皇) 藤原摂関家(兄・忠通 × 弟・頼長)
源氏(子・義朝 × 父・為義」 平氏(甥・清盛 × 叔父・忠正)
― 天皇・藤原・源・平とも、親子、兄弟が二つに別れて殺し合った。
│一一五九・平治 元・ ・平(へい)治(じ)の乱 源氏を倒し、平氏の世となる。
│一一七三・承安 三・一 ・親鸞聖人、誕生│
│一一七五・安元 元・三・京都大風・
│一一七六│安元 二│四 │大地震 │
│一一七七│治承 元│五 │4月 京都大火(太郎焼亡)大内裏の大半、関白藤原基房ら公卿の邸宅などを焼失│
│ │ │ │6月 鹿ヶ谷の陰謀(後白河の息のかかった西光、藤原成親、俊寛らが、平氏打倒を│
│ │ │ │ 計画するも失敗) │
│一一七八│治承 二│六 │4月 京都大火(次郎焼亡 )庶民の暮らす七条界隈が焼失 │
│一一七九│治承 三│七 │大地震 │
│一一八〇│治承 四│八 │親鸞聖人の母、逝去 │
│ │ │ │5月 以仁王(もちひとおう)の挙兵 後白河の三男、以仁王が平氏打倒の令旨(りょうじ)を出すが失敗 │
│ │ │ │9月 源頼朝、源義仲、挙兵 │
│ │ │ │12月 平重衡(しげひら)、東大寺、興福寺を焼く │
│ │ │ │ 【福原遷都関係】 │
│ │ │ │4月22日 清盛(62歳)の外孫、安徳天皇が二歳で即位する。 │
│ │ │ │6月2日 福原遷都 平氏への恨みが渦巻く京を嫌って、安徳天皇・高倉上皇・後白│
│ │ │ │ 河法皇をひきつれて、平氏の根拠地、福原(神戸)に都を移す。 │
│ │ │ │11月23日、平氏への反発がかえって強まり、しかたなく都を再び京に戻す。│
│一一八一│養和 元│九 │閏2月 清盛 没 │
│ │ │ │親鸞聖人、出家。 │
│ │ │ │(~1182)養和の大飢饉 │
│一一八三│寿永 二│一一│木曽義仲、入京。乱暴狼藉を働く。 │
│一一八五│文治 元│一三│平氏一門、壇ノ浦で滅亡 │
│一一九二│建久 三│二〇│源頼朝、征夷大将軍となり鎌倉幕府を開く。 │
│ │ │ │ │
【僧兵】 ・この当時、南都北嶺の寺院は膨大な荘園をもち、それを背景に何千という僧兵をかかえてい た。その僧兵たちの争いは世俗権力も顔負けするほどの貪欲さで、自己の利権を守るために 争いを繰り返していた。東大寺と興福寺の争い、延暦寺と園城寺の争い、さらには延暦寺の 中でも東塔と西塔が争い、あるいは学(がく)生(しょう)と堂衆が争いを繰り返していたのである。
・また、世俗勢力との争いになると、興福寺は春日神社のご神木をかつぎ、延暦寺は日吉神社 の神輿を担いで朝廷に強訴し、自らの言い分を貫こうとした。
・こうしたことから、院政をひき藤原家から政治の実権を奪い返した白河上皇も、「意の如く にならざるもの、鴨河の水、双(すご)六(ろく)の賽(さい)、山(やま)法(ほう)師(し)の三つ」と言ったといわれています。
宿業の身を生きる
― 日野家の系譜 ―
親鸞聖人は朝廷を牛耳っていた藤原一族の日野家に生まれました。朝廷に仕え出世すれば「国司」になれる身分でしたが、聖人の兄弟は全員出家しております。どんな家系だったのでしょうか。
承安(じようあん)三年(一一七三)、親鸞聖人は誕生されました。父は日野有範(ありのり)。母については、源氏の流れをくむ吉光女(きつこうによ)であると伝えられています。日野家は、摂関家を独占する藤原北家の流れで、儒学や歌道によって朝廷に仕えていました。
祖父、経尹(つねまさ)は阿波権守(ごんのかみ)になっていますが、『尊(そん)卑(ぴ)分(ぶん)脈(みゃく)』という中世の家系図に「放埒(ほうらつ)人」(道に外れた人間)と不名誉な記述がされています。
父、有範は、『日野一流系図』(実悟)に「皇太后宮(こうたいごうぐう)大進(だいしん)、従五位下、出家、三室戸の大進入道と号す」とあり、あまり出世していません。また晩年は出家したようです。
有範の長兄(聖人の伯父、養父)範綱(のりつな)は、後白河法皇に仕え、若狭の守に任ぜられています。また、鹿ヶ谷の変の際、範綱も法皇に重く用いられているということで拷問を受け、播磨に流されたともいわれています。(平家物語)
有範の次兄、宗業(むねなり)は以仁王(もちひとおう)の学問の師でした。 後白河法皇の第三皇子の以仁王は一一八〇年、平氏征討の令旨(りようじ)を出して源頼政とともに挙兵しましたが、宇治川の合戦に敗れ、平氏に殺されました。宗業はその首実検をさせられています(慈円『愚管抄』)。晩年には従三位に叙せられ、 文章博士(もんじょうはかせ)や式部大輔(しきぶたいふ)を歴任しています。 また、聖人の越後配流決定の直前には、建永二年正月の除目(じもく)(大臣以外の官を任ずる朝廷の儀式)で「越後権介(ごんのすけ)」に任ぜられてもいます。
*式部大輔 … 式部省は「文官の人事考課、礼式、及び選叙(叙位及び任官)、行賞を司り、役人養成機関である大学寮を統括するため、八省の内でも中務省(なかつかさしよう)に次いで重要な省とされてきた。」(『ウィキペディア』) *「大輔(だいふ)」は「卿」に次ぐ次官。
親鸞聖人のお母さんについては、『親鸞聖人正明伝』(伝・存覚作)に、「母は、源氏、八幡太郎義家の孫女、貴光女(きつこうによ)と申しき」とありますが、詳しいことは解っていません。聖人八歳の時、亡くなったようです。なお聖人の幼名としては「松若丸」「十八公麿(まつまろ)」という名が伝えられています。
*最近、西山深草(浄土宗西山派の研究者グループ)が膨大な「鎌倉遺文」などを調べて、貴光女(吉光女)は 源頼朝の姉である、という新説を出した。(『親鸞は源頼朝の甥』白馬社) 親鸞聖人を貴族の側の視点からだ けでなく、武士の側の視点もあわせて見ると、聖人の生涯がよりよく分かるような気がします。
このように、聖人の家系は、学問や歌で朝廷に仕える中流貴族であったようです。律令体制が崩壊しつつあった平安時代の末期の中流貴族にとっては、必死の勉学とコネ(賄賂)を駆使して、何らかの官職を手に入れなければ生きていけませんでした。聖人の父君や伯父君は、①藤原家が支配する朝廷と、②天皇親政を志向する院政と、③武力でもって新しい時代を切り開こうとする平氏(源氏)と、④宗教でもってこの世に君臨しようとする寺社、その四者が合従連衡を繰り返しては政治の主導権を奪い合った末法の世(乱世)の中を、官僚としての知恵と政治的なカンを駆使して必死に渡り歩いたのではないかと思います。
ところで有範の子は、親鸞聖人ばかりでなく四人(二人?)の弟も出家しています。有範に子供を育てる力がなかったからでしょうか。その理由として、皇太后宮大進どまりの有範は兄たちと違って才能がなかったとも言われてきました。はたしてそうでしょうか。妻が源氏の出であったこと、自らも出家したことなどを考え合わせると、もしかしたら日野の「血」が騒いで平家打倒の争乱に巻き込まれたということも考えられるのではないでしょうか。
また、聖人たち兄弟全員が出家したというところには、お母さんが早く亡くなったことが関係しているかもしれません。当時は母系社会の名残もあり、聖人達はお母さんのもとで養育された可能性が大きく、源氏に連なるお母さんは平氏全盛のもとでは肩身が狭かっただろうし、そのお母さんが亡くなれば、なおさら、子の養育が難しくなって出家せざるを得なかったのかも知れません。
出家への道
―親鸞聖人の原体験―
聖人は数えの九歳で出家しました。その時、聖人の心に去来していたものは何だったでしょうか。親元を離れての求道の日々は、さぞや辛いものであったでありましょう。それに耐えさせたものは何だったのでしょうか。
聖人が出家するにあたって古来、言い伝えられてきた一つのエピソードがあります。聖人が伯父範綱に連れられて青蓮院に慈円を訪ねると、慈円が「今日はもう遅い、式は明日にしよう」と言われたので、即座に「明日ありと思う心のあだ桜 夜半(よわ)に嵐の吹かぬものかは」と歌われたという話です。このエピソードは後世の作り話かも知れませんが、聖人九歳の心の真実を言い当てているのではないでしょうか。なにが聖人をして、それほど必死に出家を求めさせたのでしょうか。
『親鸞聖人正明伝』には四歳の聖人が「二月十五日、晩景のころ、十八公麿(まつまろ)ひそかに庭におり、泥沙をもて仏像三躯(たい)を造りてこれにむかい、礼拝恭敬(くきょう)あることしばしばなり」というエピソードを伝えています。また、聖人の母・吉光女は、「臨終のとき、範綱卿夫婦を呼びまいらせて申されけるは、二人の幼兄ども、四歳にして先考(せんこう)(=父親)におくれ、八歳にしてまた母をうしなう、故にためしなき単孤無頼の者にてはべるなり。かならず、二人ともに出家となし、父母の菩提をとむらわせさせ給うべし」と遺言されたとあります。
こうしたエピソードからうかがえることは、幼くして仏を拝むという資質に、父の不遇、母の逝去という悲しみが重なり、その上、先にもふれたように「末法の世」を目の当たりにしたということがあって、幼きながらも聖人は「生死いづる道」を求めて出家されたと思います。
「原体験」という言葉があります。『大辞林』には「記憶の底にいつまでも残り、その人が何らかの形でこだわり続けることになる幼少期の体験」と説明され、『大辞泉』には「その人の思想が固まる前の経験で、以後の思想形成に大きな影響を与えたもの」と説明されています。つまり、後々に、その人の思想や生き方を決定するようになる、幼子の魂に深く刻み込まれた経験のことであります。
これまで繰り返し、親鸞聖人の生まれ出た時代の様相(末法の世の到来)や、聖人一家に流れる「血(宿業)」について触れてきたのも、聖人の原体験ということを考えてみたかったからです。聖人は、仏教伝来以来、営々と築きあげてこられた日本仏教の伝統に安住できず、時には内側から、時には外側からそれに体当たりし、ついにはそれを突き破って新しい世界を開かれました。その聖人のエネルギーの源泉は幼き魂に刻み込まれた記憶、つまり原体験のしからしむるところ大であったと思うからであります。
菩薩の精神を語るに、時に、無垢(むく)で瑞々(みずみず)しい幼子の魂に比することがあります。幼子の経験は未熟なためについ軽んじられがちですが、実は、無垢であるが故にかえって大人よりも深い魂の持ち主なのではないでしょうか。
なぜ、29歳で比叡の山を出でたのか?
なぜ、戒を破って結婚に踏み切ったのか?
なぜ、流罪赦免(しやめん)後、京に戻らず関東に行ったのか?
なぜ、『教行信証』を書き残されたのか?
道を求めて ― 懸命の修学 ―
聖人が出家した頃の延暦寺は、朝廷の庇護のもと富を蓄え兵をもち堕落していましたが、その一方で、仏法の精神にふれた求道者たちが次々と生まれ出てもいたのです。
人生の転機に立たされた時、聖人はいつも、厳しい道を選んでおられます。「名聞(みようもん)・利養(りよう)・勝他(しようた)」の心とたたかいながら、それを振り払い、はるかに仏を仰ぎながら次の一歩を踏み出していかれました。それこそ、三宝に帰依する真実信心(無我なる我)による大乗(だいじよう)菩薩道(ぼさつどう)であったと、私にはそのように思えてなりません。こうした選びを聖人にさせたものは、なによりも「真実」を求めてやまぬ菩提心であったでしょうし、同時に、聖人の原体験にうながされた一切衆生と共に助からんとする心(度衆生心(どしゆじようしん))でなかったかと思います。
東本願寺から出ている『宗祖親鸞聖人』(真宗教学研究所)には、聖人の比叡での求道が次のよう書かれています。
九歳から二十九歳までの、人生においてもっとも多感な少・青年時代を、親鸞聖人は比叡の山に生きられた。
伝教大師によって開かれた比叡山は、大乗菩薩道の根本道場として、その使命を自負し、権威を誇っていた。しかし、聖人が学ばれたころには、その山も、すでに、奈良の諸宗などと同じように、現世の祈祷や、現実の生活とは無関係な学問の場になりはてていた。
しかも、事あるごとに、寺院に加持・祈祷を求めることができたのは、つねに社会の上層を占める人々であった。そのため、寺院はしだいに貴族社会とむすびつき、その寄進をうけて、広大な荘園を支配する領主となっていった。そのうえ、僧兵とよばれる武力をすらもつようになり、時代の乱れをいよいよはなはだしいものにしたのである。
権力とむすびつくことで、しだいに世俗にまみれていった寺院は、さらにその内部にも身分的な対立をうみだし、争いのやむこともないありさまであった。もちろん、寺院の堕落・騒乱をよそに、ひたすら修学にはげむ僧たちもいなかったわけではない。しかし、その人たちも、多くは、ただみずからの学問の世界にのみ閉じこもる人たちであった。
そのころの聖人については、受戒して僧となり、のちに堂僧(どうそう)をつとめていられたことが知られているだけである。
ただ、聖人の教えをしたう人々の間には、建久二年(一一九一)、19歳の秋、聖人は、磯長(しなが)の聖徳太子廟にこもられ、そこで夢告をうけられたと言いつたえられている。その夢告のなかの「日域は大乗相応の地」「汝の命根(みょうこん)まさに十余歳なるべし」「善信善信真菩薩」という言葉は、そのころ聖人がどのような問いをもって生きていられたかを示している。
すなわち、賜った命の限界を見すえながら、聖人は、どこに生死の迷いをはなれる道がひらかれるのかという苦悶を、夢告をうけるほどまでにつきつめておられたのであろう。山での二十年間は、いよいよふかまってくるその問いをかかえての、修学の日々であったのである。 (『宗祖親鸞聖人』16頁)