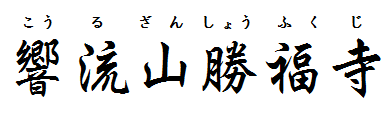響流山勝福寺 宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌・お待ち受け聞法会 (二〇一八年八月十八日)
宗祖親鸞聖人のご生涯 ④
藤谷知道
藤谷知道
弾圧の兆し — 七ケ条の制誡 —
法然上人のもとでの歓びの日々も長くは続きませんでした。旧仏教側は念仏の勢いに恐れをなし、専修念仏は邪教であると言いがかりをつけてきたのです。
法然上人の伝記である『法然上人行状絵図』(巻31)には「元久元年冬のころ、山(さん)門(もん)大講堂の庭に三塔会合して専修念仏停(ちょう)止(じ)すべきよし、座(ざ)主(す)大僧正に訴(うったえ)申(もうし)けり」という記述があります。元久元年(一二〇四年)という年は親鸞聖人(32歳)が法然上人(72歳)の教えを聞くようになって3年目の年です。法然上人は比叡に学ばれた僧でしたし、摂政・関白の九条兼実に戒を授けたりしておりますので、延暦寺との関係が残っていたのでしょう。全山あげて、天台座主に監督責任を問うたようです。それに対して法然上人は、11月7日付けで、門下の者に自戒を求める「七ケ条の制誡(せいかい)」を作り、190名に署名させています。合わせて同日付けで、「叡(えい)山(ざん)黒谷沙(しゃ)門(もん)源空」の名で座主真性に「起(き)請(しょう)文(もん)」を送り、叡山の怒りを鎮めようとしました。親鸞聖人はこの「七ケ条の制誡」に、翌8日、87番目に「僧綽空」の名で署名しています。
法然上人の伝記である『法然上人行状絵図』(巻31)には「元久元年冬のころ、山(さん)門(もん)大講堂の庭に三塔会合して専修念仏停(ちょう)止(じ)すべきよし、座(ざ)主(す)大僧正に訴(うったえ)申(もうし)けり」という記述があります。元久元年(一二〇四年)という年は親鸞聖人(32歳)が法然上人(72歳)の教えを聞くようになって3年目の年です。法然上人は比叡に学ばれた僧でしたし、摂政・関白の九条兼実に戒を授けたりしておりますので、延暦寺との関係が残っていたのでしょう。全山あげて、天台座主に監督責任を問うたようです。それに対して法然上人は、11月7日付けで、門下の者に自戒を求める「七ケ条の制誡(せいかい)」を作り、190名に署名させています。合わせて同日付けで、「叡(えい)山(ざん)黒谷沙(しゃ)門(もん)源空」の名で座主真性に「起(き)請(しょう)文(もん)」を送り、叡山の怒りを鎮めようとしました。親鸞聖人はこの「七ケ条の制誡」に、翌8日、87番目に「僧綽空」の名で署名しています。
*「七箇条制誡」
一、いまだ、一句の文義を窺わず、真言・止観を破し奉って、余の仏・菩薩を謗ずることを停止す べき事。
一、無智にもかかわらず有智の人に対し、別解別行の輩に会い、好んで諍論をすることを停止すべ き事。
一、別解別行の人に対して、愚痴偏執の心をもって、本業を棄て置くべきと称して、あながちにこ れを嫌い笑うことを停止すべき事。
一、念仏門においては戒行なしと号し、専ら婬酒食肉を勧め、たまたま律儀を守るを雑行人と名づ けて、弥陀の本願を憑む者は、造悪を恐れることなかれということを停止すべき事。
一、いまだ是非をわきまえざる痴人、聖教を離れ、師説に背いて、ほしいままに私の義を述べ、み だりに諍論を企て、智者に笑われ、愚人を迷乱することを停止すべき事。
一、愚鈍の身にもかかわらず、ことに唱導を好み、正法を知らず、種々の邪法を説いて、無智の道 俗を教化することを停止すべき事。
一、自ら仏教にあらざる邪法を説いて、偽って師範の説と号することを停止すべき事。
一、いまだ、一句の文義を窺わず、真言・止観を破し奉って、余の仏・菩薩を謗ずることを停止す べき事。
一、無智にもかかわらず有智の人に対し、別解別行の輩に会い、好んで諍論をすることを停止すべ き事。
一、別解別行の人に対して、愚痴偏執の心をもって、本業を棄て置くべきと称して、あながちにこ れを嫌い笑うことを停止すべき事。
一、念仏門においては戒行なしと号し、専ら婬酒食肉を勧め、たまたま律儀を守るを雑行人と名づ けて、弥陀の本願を憑む者は、造悪を恐れることなかれということを停止すべき事。
一、いまだ是非をわきまえざる痴人、聖教を離れ、師説に背いて、ほしいままに私の義を述べ、み だりに諍論を企て、智者に笑われ、愚人を迷乱することを停止すべき事。
一、愚鈍の身にもかかわらず、ことに唱導を好み、正法を知らず、種々の邪法を説いて、無智の道 俗を教化することを停止すべき事。
一、自ら仏教にあらざる邪法を説いて、偽って師範の説と号することを停止すべき事。
こうした努力の甲斐もなく念仏停止の要求は南都も包みこんだ旧仏教界あげてのものになっていきました。在家出家を問わず、男(なん)女(にょ)貴(き)賤(せん)ことごとく、ただ念仏の信一つで救われるという専修念仏の教えは、乾いた大地に水を注ぐがごとく人々の心にしみ込み、人々の心を解放していきました。その歓びからくる勢いは、時に行き過ぎを生むことになりましたが、もう法然上人でも止めることが出来なかったのではないでしょうか。
興福寺奏状 — 朝廷を動かす —
しかし、翌二年(一二〇五)十月、南都の興福寺は、法然上人ならびに弟子らの罪をかぞえあげて、処罰するよう朝廷につよく迫りました。戒律復興に努めていた解脱上人貞慶(じょうけい)にとって、菩提心を問わず戒を無視する専修念仏の教えは仏教そのものを否定する邪義としか思えなかったようです。南都北嶺の八宗を代表して貞慶が起草した「興福寺奏状」は以下のように「九箇条の失」をあげて念仏停止を朝廷に迫るものでした。
第一 新宗を立てる失 第二 新像を図する失 第三 釈尊を軽んずる失
第四 万善を妨ぐる失 第五 霊神に背く失 第六 浄土に暗き失
第七 念仏を誤る失 第八 釈衆を損ずる失 第九 国土を乱す失
第四 万善を妨ぐる失 第五 霊神に背く失 第六 浄土に暗き失
第七 念仏を誤る失 第八 釈衆を損ずる失 第九 国土を乱す失
この「興福寺奏状」を受けた朝廷の様子が当時、蔵(くろ)人(うど)頭(のとう)であった三条長(なが)兼(かげ)の『三長記』という日記に詳しく出ています。前後のやりとりから伺えることは、念仏停止を強く迫る興福寺に対し、朝廷は(仏罰を怖れて?)「一部の偏執の輩」の行き過ぎた行為ということで済ませようとしていたようであります。 しかし、ささやかな出来事から事態は思いがけぬ方向に展開していったのでした。
承(しょう)元(げん)の法難 — 死罪四人、流罪八人 —
建永元年(一二〇六)12月、後鳥羽上皇が熊(くま)野(の)詣(もうで)で留守の間に、院の御所の女房たちが住蓮房・安楽房らの念(ねん)仏(ぶつ)会(え)に参加し、夜も泊まったという噂が流れました。こともあろうに、安楽には2月30日に「行空、(安楽房)遵西の罪名を勘がうべし」との宣旨が下っていたのでした。それを無視したかのごとき行状に、後鳥羽上皇は怒りを爆発させ、興福寺の奏状をとりあげ、承(しょう)元(げん)元年(一二〇七)2月、住蓮房ら四人が死罪に、また、法然上人はじめ八人が流罪に処せられることになりました。このとき、法然上人は藤井元(もと)彦(ひこ)の罪名で土佐の国へ、親鸞聖人は藤井善(よし)信(ざね)の罪名で越後の国へ流罪となりました。
弾圧のきっかけはスキャンダルであったとしても、なぜそうまでして、専修念仏を弾圧する必要があったのか、その本質的な理由について最後に考えてみたいと思います。
「専修念仏」とは、阿弥陀如来が本願を建てられたその正意は「念仏衆生 摂取不捨」にあると信じて念仏申していく道であります。必然的に、これまでのように諸仏・諸菩薩、諸々の天神地祇に帰依することをやめ、弥陀一仏に帰依していくことになります。このことは、南都北嶺の仏教界や日本伝来の神々に帰依する為政者たちには許し難い「神仏軽(けい)侮(ぶ)」の相(すがた)と映ったであろうし、神仏の怒りをまねき「国を乱す」ものとして許しがたいものと思われたに違いありません。
また、救いの根拠が自力の善根にあるのではなく如来の本願にあるという浄土門の教えは、戒をまもり善根を積んでいくことで覚りを得るとした、これまでの仏教の常識を破るものでありました。このことは、仏教の根本をなす菩提心の否定と映り、それこそ仏法を破る「破戒の者」と弾劾せずにおれなかったことでありましょう。
また、「悪(あく)人(にん)正(しょう)機(き)」(阿弥陀仏は、罪業深く生きるほかなき末代の悪人の救済を念じて、五劫に思惟し兆載(ちょうさい)永(よう)劫(ごう)に修行してご本願を建ててくださった)の教説は、聖道門の者には「この行者に成(なり)ぬれば、女犯(にょぼん)をこのむも魚鳥を食も、阿弥陀仏はすこしもとがめ玉(たま)はず。一向専修にいりて念仏ばかりを信じつれば、一(いち)定(じょう)最後にむかへ玉ふぞ」(愚管抄)「罪を怖れ、悪を憚(はばか)るは、これ仏を憑(たの)まざるの人なり」(興福寺奏状)と世の道徳を否定する「造(ぞう)悪(あく)無(む)碍(げ)」の輩と映ったことでありましょう。
このように「浄土門」と「聖道門」は橋の掛け渡しのしようがないほど深い溝がありました。世の権力が聖道門の側にある以上、ある意味では浄土門への弾圧は必然的でもあったのです。
弾圧のきっかけはスキャンダルであったとしても、なぜそうまでして、専修念仏を弾圧する必要があったのか、その本質的な理由について最後に考えてみたいと思います。
「専修念仏」とは、阿弥陀如来が本願を建てられたその正意は「念仏衆生 摂取不捨」にあると信じて念仏申していく道であります。必然的に、これまでのように諸仏・諸菩薩、諸々の天神地祇に帰依することをやめ、弥陀一仏に帰依していくことになります。このことは、南都北嶺の仏教界や日本伝来の神々に帰依する為政者たちには許し難い「神仏軽(けい)侮(ぶ)」の相(すがた)と映ったであろうし、神仏の怒りをまねき「国を乱す」ものとして許しがたいものと思われたに違いありません。
また、救いの根拠が自力の善根にあるのではなく如来の本願にあるという浄土門の教えは、戒をまもり善根を積んでいくことで覚りを得るとした、これまでの仏教の常識を破るものでありました。このことは、仏教の根本をなす菩提心の否定と映り、それこそ仏法を破る「破戒の者」と弾劾せずにおれなかったことでありましょう。
また、「悪(あく)人(にん)正(しょう)機(き)」(阿弥陀仏は、罪業深く生きるほかなき末代の悪人の救済を念じて、五劫に思惟し兆載(ちょうさい)永(よう)劫(ごう)に修行してご本願を建ててくださった)の教説は、聖道門の者には「この行者に成(なり)ぬれば、女犯(にょぼん)をこのむも魚鳥を食も、阿弥陀仏はすこしもとがめ玉(たま)はず。一向専修にいりて念仏ばかりを信じつれば、一(いち)定(じょう)最後にむかへ玉ふぞ」(愚管抄)「罪を怖れ、悪を憚(はばか)るは、これ仏を憑(たの)まざるの人なり」(興福寺奏状)と世の道徳を否定する「造(ぞう)悪(あく)無(む)碍(げ)」の輩と映ったことでありましょう。
このように「浄土門」と「聖道門」は橋の掛け渡しのしようがないほど深い溝がありました。世の権力が聖道門の側にある以上、ある意味では浄土門への弾圧は必然的でもあったのです。
弾圧者を悲しむ
親鸞聖人は、この承元の法難について、『教行信証』の後序に、
竊(ひそ)かに以(おもん)みれば、聖道の諸教は行(ぎょう)証(しょう)久しく廃れ、浄土の真宗は証(しょう)道(どう)いま盛なり。しかるに諸寺の釈門、教に昏(くら)くして真(しん)仮(け)の門戸を知らず、洛(らく)都(と)の儒林(じゅりん)、行に迷うて邪(じゃ)正(しょう)の道路を弁(わきま)うることなし。ここをもって興福寺の学徒、太上天皇諱(いみな)尊成(たかなり)、今上(きんじょう)諱為(ため)仁(ひと) 聖(せい)暦(れき)・承元丁(ひのと)の卯(う)の歳(とし)、仲(ちゅう)春(しゅん)上旬の候に奏達す。主上臣下、法に背き義に違し、忿(いかり)を成し怨(うらみ)を結ぶ。 〔聖典三九八頁〕
と述べておられます。
親鸞聖人は、「聖道門」による「浄土門」の弾圧を、平氏に源氏が取って代わったというような勢力争いではなく、「邪」なるものが「真」なるものを踏みにじった「法に背き義に違」するものとして、厳しく弾劾されているのです。
もっともその弾劾は、いつかはこの恨みを晴らさんというような個人的なものではなく、「念仏を御こころにいれてつねにもうして、念仏そしらんひとびと、この世のちの世までのことを、いのりあわせたまうべくそうろう」(『御消息集』五七八頁)と言われるように、念仏を弾圧する人をも悲しまれてのものでした。
法然上人も親鸞聖人も、この流罪を受けとめ直して「そもそもまた、大師聖人源空、もし流刑に処せられたまわずは、われまた配所に赴かんや、もしわれ配所におもむかずは、何によりてか辺(へん)鄙(ぴ)の群類を化せん、これ猶(なお)師教(しきょう)の恩(おん)致(ち)なり」〔『御伝鈔』七二五頁〕と歓ばれました。
自らを弾圧するものを悲しまれていき、それを逆縁とすることで新しく世界を開いていく、浄土真宗とはなんとふところの深い教えでありましょう。これはもう人間の心で出来ることではありません。それこそ如来のお心でありましょう。
と述べておられます。
親鸞聖人は、「聖道門」による「浄土門」の弾圧を、平氏に源氏が取って代わったというような勢力争いではなく、「邪」なるものが「真」なるものを踏みにじった「法に背き義に違」するものとして、厳しく弾劾されているのです。
もっともその弾劾は、いつかはこの恨みを晴らさんというような個人的なものではなく、「念仏を御こころにいれてつねにもうして、念仏そしらんひとびと、この世のちの世までのことを、いのりあわせたまうべくそうろう」(『御消息集』五七八頁)と言われるように、念仏を弾圧する人をも悲しまれてのものでした。
法然上人も親鸞聖人も、この流罪を受けとめ直して「そもそもまた、大師聖人源空、もし流刑に処せられたまわずは、われまた配所に赴かんや、もしわれ配所におもむかずは、何によりてか辺(へん)鄙(ぴ)の群類を化せん、これ猶(なお)師教(しきょう)の恩(おん)致(ち)なり」〔『御伝鈔』七二五頁〕と歓ばれました。
自らを弾圧するものを悲しまれていき、それを逆縁とすることで新しく世界を開いていく、浄土真宗とはなんとふところの深い教えでありましょう。これはもう人間の心で出来ることではありません。それこそ如来のお心でありましょう。
なぜ越後だったのか
親鸞聖人は「僧尼令(そうにりよう)」の規定にもとづき還俗(げんぞく)(僧の身分を剥奪(はくだつ)し俗人に戻すこと)させられ「藤井(ふじい)善信(よしざね)」という俗名をつけられて「遠流(おんる)」(遠隔地への流罪)となりました。
ところで、流罪の地が越後となった事情は何だったのでしょうか。朝廷の人事記録である『公卿(くぎよう)補任(ぶにん)』によると、配流決定の直前、建永二年正月の除目(じもく)(官の任命)で、伯父日野宗業(むねなり)が「越後権介(ごんのすけ)」に任ぜられています。「権介」とは今でいえば、副知事代理になるそうです。当時は自らは赴任しない遥任(ようにん)が多かったようですが、それでも現地の役人に命令をだすことはできましょう。この伯父が引受人となって配流先が越後になったのではないかと思います。
また妻、恵信の実家、三善家は越後に所領を持っていたと思われます。それは恵信尼が晩年、越後で過ごしていることからも窺えます。恵信尼の属する三善家からは時々、越後の国司が出ています。そうしたことが繰り返されるうちに、いつしか三善家は越後に領地をもつようになっていたのではないでしょうか。今になってはそのどちらかはっきりしませんが、ともかく親鸞聖人一家を引き受けることのできる場所として越後に決定したのではないかと思われます。
こうしたことも、このたびの流罪は、人殺しのような凶悪犯や政治的な逆徒に対する類のものではなく、人々から深く帰依されていた念仏者に対するものであるため、刑を命じた朝廷にも後ろめたさがあったからです。そのため、流罪といってもその内実は、懲罰的なものではなく、保護観察付きの所払いのようなものであったと思われます。
承元元年(一二〇七)3月16日、その日の昼、法然上人が配所の土佐へ向けて出発することになっていたので、聖人はそれより先にと、未明のうちに京を出て越後へと出発しました。親鸞聖人はどのようにして流罪の地へ送られたのでしょうか。
当時の「流罪」は現代の懲役刑のようなものではありません。「獄令(ごくりよう)」には「凡(おおよ)そ流(る)人(にん)科断すること已に定まらむ、及び移郷の人は、皆妻妾(さいしよう)棄放(きほう)して配所に至ることを得じ」と書かれています。囚われの身の聖人に付き添うようにして恵信尼や子も道を歩かれたのか、それとも日をおいて妻子は流罪の地へ行かれたのか。どちらにしても、配所へ赴く旅は、真実に順って生きることの厳しさを身に刻み込む旅であったに違いありません。
ところで、聖人一家はどこを通って越後に入ったのでしょうか。越中までは陸路を行き、親不知を海路で越えたのでしょうか。昔から、越後には居多ヶ浜(こたがはま)(現・新潟県上越市)から上陸したと言い伝えられています。聖人一家はその居多ヶ浜から遠からぬ所にあった越後の国分寺の側に居(竹の内草庵)をかまえたようです。
ところで、流罪の地が越後となった事情は何だったのでしょうか。朝廷の人事記録である『公卿(くぎよう)補任(ぶにん)』によると、配流決定の直前、建永二年正月の除目(じもく)(官の任命)で、伯父日野宗業(むねなり)が「越後権介(ごんのすけ)」に任ぜられています。「権介」とは今でいえば、副知事代理になるそうです。当時は自らは赴任しない遥任(ようにん)が多かったようですが、それでも現地の役人に命令をだすことはできましょう。この伯父が引受人となって配流先が越後になったのではないかと思います。
また妻、恵信の実家、三善家は越後に所領を持っていたと思われます。それは恵信尼が晩年、越後で過ごしていることからも窺えます。恵信尼の属する三善家からは時々、越後の国司が出ています。そうしたことが繰り返されるうちに、いつしか三善家は越後に領地をもつようになっていたのではないでしょうか。今になってはそのどちらかはっきりしませんが、ともかく親鸞聖人一家を引き受けることのできる場所として越後に決定したのではないかと思われます。
こうしたことも、このたびの流罪は、人殺しのような凶悪犯や政治的な逆徒に対する類のものではなく、人々から深く帰依されていた念仏者に対するものであるため、刑を命じた朝廷にも後ろめたさがあったからです。そのため、流罪といってもその内実は、懲罰的なものではなく、保護観察付きの所払いのようなものであったと思われます。
承元元年(一二〇七)3月16日、その日の昼、法然上人が配所の土佐へ向けて出発することになっていたので、聖人はそれより先にと、未明のうちに京を出て越後へと出発しました。親鸞聖人はどのようにして流罪の地へ送られたのでしょうか。
当時の「流罪」は現代の懲役刑のようなものではありません。「獄令(ごくりよう)」には「凡(おおよ)そ流(る)人(にん)科断すること已に定まらむ、及び移郷の人は、皆妻妾(さいしよう)棄放(きほう)して配所に至ることを得じ」と書かれています。囚われの身の聖人に付き添うようにして恵信尼や子も道を歩かれたのか、それとも日をおいて妻子は流罪の地へ行かれたのか。どちらにしても、配所へ赴く旅は、真実に順って生きることの厳しさを身に刻み込む旅であったに違いありません。
ところで、聖人一家はどこを通って越後に入ったのでしょうか。越中までは陸路を行き、親不知を海路で越えたのでしょうか。昔から、越後には居多ヶ浜(こたがはま)(現・新潟県上越市)から上陸したと言い伝えられています。聖人一家はその居多ヶ浜から遠からぬ所にあった越後の国分寺の側に居(竹の内草庵)をかまえたようです。
流罪を内面化する
親鸞聖人は『歎異抄』の第一章に、弥陀の本願は「罪悪深重(ざいあくじんじゆう)煩悩熾盛(ぼんのうしじよう)の衆生をたすけんがため」〔聖典六二六頁〕の願であると教えて下さっています。聖人の慶ばれた本願は、煩悩に狂うばかりでなく、自他を傷つけてしか生きられない罪業深き凡夫をすくうものでした。本願の正(しょう)機(き)としての「罪悪深重煩悩熾盛の衆生」という頷きは、なによりも聖人ご自身の自覚からくるものでありましょうが、それを如実に教えてくれたのは、罪人という身分であり、越後の地で出会った人々だったのではないでしょうか。
聖人は藤原一門に属する日野家に生まれました。出家した比叡の山では「官(かん)僧(そう)」として身分を保障されていました。山を下り、法然上人門下になっても、信心一異の諍論などから窺えることは教理的な課題です。心は凡夫になろうとも身(深層意識)はエリートであったのではないでしょうか。「いし・かわら・つぶてのごとくなるわれらなり」〔『唯信鈔文意』五五三頁〕という地平は、流罪による生活から開かれたに違いありません。
苛酷な戦争体験を問い続ける中で親鸞聖人の教えに辿り着かれた人々がたくさんいました(野間宏・真継伸彦など)。最近では、朝鮮人の高(コ)史(サ)明(ミョン)先生や中国人の張(チャン)偉(ウェイ)先生が人間への絶望の彼方で親鸞聖人に出遇(であ)われました。親鸞聖人には、人間という在り方に対する深い悲しみがあふれています。越後への流罪は、親鸞聖人をして、貴族の子としてあるいは僧として護ってくれていた外套がはぎ取られ、「罪悪深重煩悩熾盛の衆生」という人間存在の根源へと導かれる出来事だったと思います。
聖人は藤原一門に属する日野家に生まれました。出家した比叡の山では「官(かん)僧(そう)」として身分を保障されていました。山を下り、法然上人門下になっても、信心一異の諍論などから窺えることは教理的な課題です。心は凡夫になろうとも身(深層意識)はエリートであったのではないでしょうか。「いし・かわら・つぶてのごとくなるわれらなり」〔『唯信鈔文意』五五三頁〕という地平は、流罪による生活から開かれたに違いありません。
苛酷な戦争体験を問い続ける中で親鸞聖人の教えに辿り着かれた人々がたくさんいました(野間宏・真継伸彦など)。最近では、朝鮮人の高(コ)史(サ)明(ミョン)先生や中国人の張(チャン)偉(ウェイ)先生が人間への絶望の彼方で親鸞聖人に出遇(であ)われました。親鸞聖人には、人間という在り方に対する深い悲しみがあふれています。越後への流罪は、親鸞聖人をして、貴族の子としてあるいは僧として護ってくれていた外套がはぎ取られ、「罪悪深重煩悩熾盛の衆生」という人間存在の根源へと導かれる出来事だったと思います。
教信沙弥の定
『恵信尼消息』によれば、越後流罪から4年目の39歳の時、信蓮房が生まれています。『日野一流系図』によれば、この信蓮房は聖人と恵信尼の3番目の子供です。還俗させられ藤井善信と名告ることになった親鸞聖人は、「僧」という身分意識から解放され、文字通り肉食妻帯の在家生活者となったのではないかと思われます。覚如上人の書かれた『改邪鈔(がいじゃしょう)』には、聖人が「つねの御持言(ごじごん)」として「われはこれ賀古の教信(きょうしん)沙(しゃ)弥(み)の定(じよう)なり」〔聖典六八〇頁〕と言われていたことが記されています。
教信沙弥とは奈良時代後期から平安時代にかけて活躍した念仏聖(ヒジリ)です。はじめは興福寺で修学しましたが、後に隠遁して播磨国賀古駅の近くに草庵を結び、妻帯し子をもうけ、荷役などしながら道行く人々に念仏を勧めたと言い伝えられていました(『今昔物語』など)。そうした教信沙弥に自身を重ねていく自己認識は越後での生活から始まったことでしょう。
聖人には、「群生海(ぐんじようかい)」とか「群萌(ぐんもう)」とかという言葉があります。また、親鸞聖人の御遺言と言われてきた「御臨末(ごりんまつ)の御(ご)書(しょ)」には「あをくさ人」という言葉がのこされています。こうした言葉は、自分の外に人々を見ている限り生まれるはずがりません。結婚し、次々と子供を授かり、妻子を通して村人と生活を共にしていく中で生まれ出てきた感覚でありましょう。こうしたいのちに対する愛おしみがあってはじめて、「いし・かわら・つぶてのごとくなるわれら」〔『唯信鈔文意』五五三頁〕という共感も生まれてきたのでありましょうし、そうした者こそ如来の正機であるという確信を深めることが出来たと思います。弥陀の本願が「罪悪深重煩悩熾盛の衆生」を助けずんば止まぬのも、煩悩を許し罪を問わぬというのではなく、そうでしか有りえぬ衆生といういのちをこそ悲しまれるからであります。
教信沙弥とは奈良時代後期から平安時代にかけて活躍した念仏聖(ヒジリ)です。はじめは興福寺で修学しましたが、後に隠遁して播磨国賀古駅の近くに草庵を結び、妻帯し子をもうけ、荷役などしながら道行く人々に念仏を勧めたと言い伝えられていました(『今昔物語』など)。そうした教信沙弥に自身を重ねていく自己認識は越後での生活から始まったことでしょう。
聖人には、「群生海(ぐんじようかい)」とか「群萌(ぐんもう)」とかという言葉があります。また、親鸞聖人の御遺言と言われてきた「御臨末(ごりんまつ)の御(ご)書(しょ)」には「あをくさ人」という言葉がのこされています。こうした言葉は、自分の外に人々を見ている限り生まれるはずがりません。結婚し、次々と子供を授かり、妻子を通して村人と生活を共にしていく中で生まれ出てきた感覚でありましょう。こうしたいのちに対する愛おしみがあってはじめて、「いし・かわら・つぶてのごとくなるわれら」〔『唯信鈔文意』五五三頁〕という共感も生まれてきたのでありましょうし、そうした者こそ如来の正機であるという確信を深めることが出来たと思います。弥陀の本願が「罪悪深重煩悩熾盛の衆生」を助けずんば止まぬのも、煩悩を許し罪を問わぬというのではなく、そうでしか有りえぬ衆生といういのちをこそ悲しまれるからであります。
「愚禿親鸞」の誕生
流罪は死罪に次ぐ重い刑であります。とはいっても、聖人は僧であり貴族でした。流された越後での生活は、牢獄に繋がれるようなものではありませんでした。伊豆に流された源頼朝は北条政子と結婚し、再起の時を待ちました。親鸞聖人は恵信尼と家庭生活をいとなみながら、念仏弾圧からもたらされた新しい経験をどのように受けとめていけばいいのか、如来へたずねる日々でなかったかと思います。
『歎異抄』には、流罪の記録の後に、「親鸞、僧儀を改めて、俗名を賜ふ。よつて僧にあらず俗にあらず、しかるあひだ、「禿(とく)」の字をもつて姓となして、… 流罪以後、愚禿(ぐとく)親鸞(しんらん)と書かしめたまふなり」〔聖典六四二頁〕とあります。法然上人のもとにおいて名(な)告(の)っていた「善信」の名をあらためて「愚禿親鸞」と名告りをあげるにいたるような、そんな歩みが流罪の日々であったのではないでしょうか。
『歎異抄』には、流罪の記録の後に、「親鸞、僧儀を改めて、俗名を賜ふ。よつて僧にあらず俗にあらず、しかるあひだ、「禿(とく)」の字をもつて姓となして、… 流罪以後、愚禿(ぐとく)親鸞(しんらん)と書かしめたまふなり」〔聖典六四二頁〕とあります。法然上人のもとにおいて名(な)告(の)っていた「善信」の名をあらためて「愚禿親鸞」と名告りをあげるにいたるような、そんな歩みが流罪の日々であったのではないでしょうか。