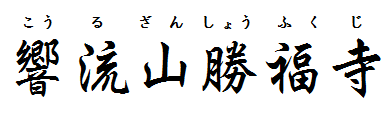響流山勝福寺 宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌・お待ち受け聞法会 (二〇一八年九月八日)
宗祖親鸞聖人のご生涯 ⑤ 藤谷知道
転法輪の旅
東国への旅立ち
建暦(けんりやく)元年(一二一一年)11月17日、朝廷は法然上人に死期が近づいたため急遽、法然上人を赦免(しやめん)することにしました。(尊い仏者を罪人として死なせてしまえば、その罰で地獄に堕とされるかもしれぬ、と怖れてたようです)。親鸞聖人もそれに併せて赦免されることになりました。承(しよう)元(げん)の法難によって越後に流罪になってから4年と9ヶ月の歳月が流れていました。聖人一家の喜びや、いかばかりであったことでしょう。
なのに、聖人は京に帰らず、なお越後にとどまったのです。しかも、その三年後に、越後を離れて向かった先は、京を遠く離れた東国でした。なぜ京に帰られなかったのか、なぜ東国に行かれたのか、聖人自身が何も語っていないため、謎に包まれたままであります。
親鸞聖人流罪の地は日本一の豪雪地帯であります。赦免の知らせが届いた時には、すでに雪で閉ざされていたことでありましょう。乳飲み子を抱えた聖人一家は春の到来を待ったのかも知れません。ところが年が明けるや、法然上人が1月25日に往生したとの知らせが届きました。法然上人はかねがね、「わが没後において、各住各居して、会わざるにしかじ」(「起請(きしよう) 没後二箇条事(もつごにかじようこと)」)と言い遺されていました。親鸞聖人は師の遺言に順ったのかも知れません。
建暦(けんりやく)元年(一二一一年)11月17日、朝廷は法然上人に死期が近づいたため急遽、法然上人を赦免(しやめん)することにしました。(尊い仏者を罪人として死なせてしまえば、その罰で地獄に堕とされるかもしれぬ、と怖れてたようです)。親鸞聖人もそれに併せて赦免されることになりました。承(しよう)元(げん)の法難によって越後に流罪になってから4年と9ヶ月の歳月が流れていました。聖人一家の喜びや、いかばかりであったことでしょう。
なのに、聖人は京に帰らず、なお越後にとどまったのです。しかも、その三年後に、越後を離れて向かった先は、京を遠く離れた東国でした。なぜ京に帰られなかったのか、なぜ東国に行かれたのか、聖人自身が何も語っていないため、謎に包まれたままであります。
親鸞聖人流罪の地は日本一の豪雪地帯であります。赦免の知らせが届いた時には、すでに雪で閉ざされていたことでありましょう。乳飲み子を抱えた聖人一家は春の到来を待ったのかも知れません。ところが年が明けるや、法然上人が1月25日に往生したとの知らせが届きました。法然上人はかねがね、「わが没後において、各住各居して、会わざるにしかじ」(「起請(きしよう) 没後二箇条事(もつごにかじようこと)」)と言い遺されていました。親鸞聖人は師の遺言に順ったのかも知れません。
なぜ東国を選ばれたのか
流罪を赦免されて三年、42歳になった親鸞聖人と33歳になった恵信尼は東国へ行くことを決断しました。聖人一家を招聘(しようへい)した人がいたのでしょうか。あるいは時機純熟(じきじゆんじゆく)して如来に命じられるまま東国へ向かったのでしょうか。それについて様々な見解が示されています。
よく言われるのが、『顕浄土真実教行証文類』を書きあげるため、教典のそろっていた東国へと行かれたという説です。下野(しもつけ)から常陸(ひたち)にかけては法然上人への帰依が深かった宇都宮一族が支配しており、聖人の落ち着くことになった稲田郷を含む笠間地方は、宇都宮一族の塩谷朝業(しおのやともなり)の次男の笠間時朝(かさまときとも)が領主でした。時朝は聖人が東国を離れた後ではありますが、建長七年(一二五五年)に鹿島神宮へ宋版一切経を奉納しています。その一切経が親鸞聖人在郷の時にすでにあったと考えられないか、というのです。
仏教民俗学の五(ご)来(らい) 重(しげる)氏は、聖人は善光寺の念仏聖(ひじり)たちと一緒に東国へ行った、と言われます。その証拠としてあげられるのが「安(あん)城(じょう)の御(ご)影(えい)」です。存覚の『袖(そで)日(にっ)記(き)』によれば、安城の御影は聖人が83歳のときに朝円という画工に書かせた寿(じゅ)像(ぞう)(存命中に描かれた絵)であります。ここに描かれている聖人は、僧とは思えぬ茜根(あかね)裏(うら)の下着を着ています。座っているのは狸皮の敷ものだし、前には猫皮の草履と猫皮を巻いた鹿杖(かせづえ)がおいてあります。他の高僧たちには見られぬ姿です。なぜこんな絵を描かせたのでしょうか。それは聖人自身も弟子たちも、遊行(ゆぎよう)する念仏聖であったからだ、と言うのです。
あるいは、聖人の高弟であった真仏、顕智が開いた専修寺(せんじゆじ)の御本尊が善光寺様式の一光三尊仏であることから、聖人を迎え入れた真仏たちは善光寺の勧(かん)進(じん)聖(ひじり)と考えられる、という説もあります。このことは『御伝鈔』の第八段〔聖典七三〇頁〕に出ている、絵師の定(じょう)禅(ぜん)法橋(ほつきよう) が親鸞聖人を見た途端、昨夜夢で見た「善光寺の本願御房」と「すこしもたがうところなし」と随喜した記事にも合致しています。
よく言われるのが、『顕浄土真実教行証文類』を書きあげるため、教典のそろっていた東国へと行かれたという説です。下野(しもつけ)から常陸(ひたち)にかけては法然上人への帰依が深かった宇都宮一族が支配しており、聖人の落ち着くことになった稲田郷を含む笠間地方は、宇都宮一族の塩谷朝業(しおのやともなり)の次男の笠間時朝(かさまときとも)が領主でした。時朝は聖人が東国を離れた後ではありますが、建長七年(一二五五年)に鹿島神宮へ宋版一切経を奉納しています。その一切経が親鸞聖人在郷の時にすでにあったと考えられないか、というのです。
仏教民俗学の五(ご)来(らい) 重(しげる)氏は、聖人は善光寺の念仏聖(ひじり)たちと一緒に東国へ行った、と言われます。その証拠としてあげられるのが「安(あん)城(じょう)の御(ご)影(えい)」です。存覚の『袖(そで)日(にっ)記(き)』によれば、安城の御影は聖人が83歳のときに朝円という画工に書かせた寿(じゅ)像(ぞう)(存命中に描かれた絵)であります。ここに描かれている聖人は、僧とは思えぬ茜根(あかね)裏(うら)の下着を着ています。座っているのは狸皮の敷ものだし、前には猫皮の草履と猫皮を巻いた鹿杖(かせづえ)がおいてあります。他の高僧たちには見られぬ姿です。なぜこんな絵を描かせたのでしょうか。それは聖人自身も弟子たちも、遊行(ゆぎよう)する念仏聖であったからだ、と言うのです。
あるいは、聖人の高弟であった真仏、顕智が開いた専修寺(せんじゆじ)の御本尊が善光寺様式の一光三尊仏であることから、聖人を迎え入れた真仏たちは善光寺の勧(かん)進(じん)聖(ひじり)と考えられる、という説もあります。このことは『御伝鈔』の第八段〔聖典七三〇頁〕に出ている、絵師の定(じょう)禅(ぜん)法橋(ほつきよう) が親鸞聖人を見た途端、昨夜夢で見た「善光寺の本願御房」と「すこしもたがうところなし」と随喜した記事にも合致しています。
東国はフロンティアであった
今井雅晴氏は、東国には法然上人に帰依する御家人(ごけにん)たちがたくさんいて、彼らが聖人一家を招聘するとともに、聖人にとっても、東国は新しい文化の胎動しているフロンティアとして魅力的であった、という説を出しています。それというのも、四百年間に亘って政治と文化の中心だった京は、いつしか朝廷や貴族たちが利権をめぐって権謀術策をめぐらす場となっており、南都北嶺の顕密仏教も人々の心を神仏の名で呪縛する呪術に成り下がっていました。旧習で窒息しそうになっていた京を離れてすべてを新しく創り始めようとした東国は、政治はもとより精神世界においてもフロンティアだったのです。
親鸞聖人の赴いた東国は当時、下(しもつけ)野(の)国(くに)宇都宮を本拠とする宇都宮頼綱(一一七二~一二五九)が支配していました。頼綱の妻は鎌倉幕府の生みの親、北条時政の娘であり、源頼朝と義兄弟となり、幕府の有力御家人でもありました。その頼綱は和歌にも秀で、京では『新古今和歌集』を編纂した藤原定家と親交を結ぶ文化人でありました。ちなみに「小倉百人一首」は、頼綱が京都の嵯峨野に建てた小倉山荘の襖用に定家に書いてもらったものです。
この頼綱は法然上人の弟子、証空に師事する念仏者でもありました。出家して蓮生房という法名を受けています。そして嘉禄(かろく)の法難(一二二七年)では、叡山の悪僧による大谷破却に先立ち、法然上人の遺骸を掘りかえして西山で荼(だ)毘(び)にふし葬り直しています。この頼綱は親鸞聖人と一つしか違いません。法然上人に帰依した彼が、自分の領地に来ている親鸞聖人の存在を知らなかったとは考えられません。 今井氏の説は新鮮に聞こえました。それというのも、流罪によって深まっていった思索は、親鸞聖人をして、「善信」に替わって「親鸞」を名告らせることになりました。そこにはきっと、信仰上の飛躍があったことでしょう。聖人は苦闘の果てで獲得した仏道を真新しい世界に訴えたくなった、と考えられないでしょうか。
釈尊も菩提樹下で悟りを開いた後、梵天の勧請を受けて説法を決意しましだが、初(しょ)転(てん)法(ほう)輪(りん)の地に選んだのはブッダガヤから二〇〇㌔離れたベナレス近郊のサールナート(鹿野苑)でありました。そこにはかつての仲間がいたのですが、なによりもそこが求道者の集まる場所だったからです。
あるいは明治のはじめ、清沢満之が真宗大学を東京にもっていこうとしたことも、東京に浩々洞(こうこうどう)を開いて若い真宗学徒と共に研鑽し、その成果を『精神界』に発表して世間に訴えようとしたことも、同じではないでしょうか。親鸞聖人も旧仏教のしがらみのない新天地で自分の獲得した信念を訴えようと思い立ったことでしょう。
いずれも魅力的な説であって、どれとも決めかねます。あるいはどれか一つでなく、幾つかの理由が複合して東国行きが決まったのかも知れません。ともかく理由はいかようにあれ、親鸞聖人は長い沈黙の時期を終えて、東国に向けて新しい一歩を踏み出したのです。
親鸞聖人の赴いた東国は当時、下(しもつけ)野(の)国(くに)宇都宮を本拠とする宇都宮頼綱(一一七二~一二五九)が支配していました。頼綱の妻は鎌倉幕府の生みの親、北条時政の娘であり、源頼朝と義兄弟となり、幕府の有力御家人でもありました。その頼綱は和歌にも秀で、京では『新古今和歌集』を編纂した藤原定家と親交を結ぶ文化人でありました。ちなみに「小倉百人一首」は、頼綱が京都の嵯峨野に建てた小倉山荘の襖用に定家に書いてもらったものです。
この頼綱は法然上人の弟子、証空に師事する念仏者でもありました。出家して蓮生房という法名を受けています。そして嘉禄(かろく)の法難(一二二七年)では、叡山の悪僧による大谷破却に先立ち、法然上人の遺骸を掘りかえして西山で荼(だ)毘(び)にふし葬り直しています。この頼綱は親鸞聖人と一つしか違いません。法然上人に帰依した彼が、自分の領地に来ている親鸞聖人の存在を知らなかったとは考えられません。 今井氏の説は新鮮に聞こえました。それというのも、流罪によって深まっていった思索は、親鸞聖人をして、「善信」に替わって「親鸞」を名告らせることになりました。そこにはきっと、信仰上の飛躍があったことでしょう。聖人は苦闘の果てで獲得した仏道を真新しい世界に訴えたくなった、と考えられないでしょうか。
釈尊も菩提樹下で悟りを開いた後、梵天の勧請を受けて説法を決意しましだが、初(しょ)転(てん)法(ほう)輪(りん)の地に選んだのはブッダガヤから二〇〇㌔離れたベナレス近郊のサールナート(鹿野苑)でありました。そこにはかつての仲間がいたのですが、なによりもそこが求道者の集まる場所だったからです。
あるいは明治のはじめ、清沢満之が真宗大学を東京にもっていこうとしたことも、東京に浩々洞(こうこうどう)を開いて若い真宗学徒と共に研鑽し、その成果を『精神界』に発表して世間に訴えようとしたことも、同じではないでしょうか。親鸞聖人も旧仏教のしがらみのない新天地で自分の獲得した信念を訴えようと思い立ったことでしょう。
いずれも魅力的な説であって、どれとも決めかねます。あるいはどれか一つでなく、幾つかの理由が複合して東国行きが決まったのかも知れません。ともかく理由はいかようにあれ、親鸞聖人は長い沈黙の時期を終えて、東国に向けて新しい一歩を踏み出したのです。
僧伽の成立
東国での生活
蓮如上人の孫にあたる顕誓という人が書いた『反故裏書(ほごのうらがき)』によれば、聖人一家はまず下妻の小島(茨城県下妻市)に草庵を結び、しばらく滞在した後、稲田(茨城県笠間市)に移ったようです。『御伝鈔』にはその様子を「聖人越後国より常陸国に越えて、笠間郡稲田郷という所に隠居したまう。幽栖(ゆうせい)を占むといえども、道(どう)俗(ぞく)跡(あと)をたずね、蓬戸(ほうこ)を閉ずといえども、貴賤(きせん)衢(ちまた)に溢る」〔聖典七三二頁〕と伝えています。
この間の親鸞聖人の伝道の足跡は『親鸞聖人門弟交名牒(きようみようちよう)』からおおよそ推測できます。そこに載っている弟子の数は、下野(しもつけ)国(栃木県)に真仏以下7名、常陸(ひたち)国(茨城県)に順信以下20名、下総(しもふさ)国(千葉県ほか)に性信以下3名、奥羽(おうう)両国(陸奥と出羽・現在の東北地方)に如信以下7名、武蔵(むさし)国(東京都・埼玉県・横浜市)に西念1名で、東国から奥羽にかけて38名の名が出ています。稲田を中心に、東国から奥羽までの広い範囲にわたって布教したことでありましょう。
ちなみに、それ以外の弟子は、越後国(新潟県)に覚善1名、遠江(とおとうみ)国(静岡県)に専海1名、洛中に尊蓮以下7名、あと所在不明1名で、いかに東国の門弟が多いかが分かります。
蓮如上人の孫にあたる顕誓という人が書いた『反故裏書(ほごのうらがき)』によれば、聖人一家はまず下妻の小島(茨城県下妻市)に草庵を結び、しばらく滞在した後、稲田(茨城県笠間市)に移ったようです。『御伝鈔』にはその様子を「聖人越後国より常陸国に越えて、笠間郡稲田郷という所に隠居したまう。幽栖(ゆうせい)を占むといえども、道(どう)俗(ぞく)跡(あと)をたずね、蓬戸(ほうこ)を閉ずといえども、貴賤(きせん)衢(ちまた)に溢る」〔聖典七三二頁〕と伝えています。
この間の親鸞聖人の伝道の足跡は『親鸞聖人門弟交名牒(きようみようちよう)』からおおよそ推測できます。そこに載っている弟子の数は、下野(しもつけ)国(栃木県)に真仏以下7名、常陸(ひたち)国(茨城県)に順信以下20名、下総(しもふさ)国(千葉県ほか)に性信以下3名、奥羽(おうう)両国(陸奥と出羽・現在の東北地方)に如信以下7名、武蔵(むさし)国(東京都・埼玉県・横浜市)に西念1名で、東国から奥羽にかけて38名の名が出ています。稲田を中心に、東国から奥羽までの広い範囲にわたって布教したことでありましょう。
ちなみに、それ以外の弟子は、越後国(新潟県)に覚善1名、遠江(とおとうみ)国(静岡県)に専海1名、洛中に尊蓮以下7名、あと所在不明1名で、いかに東国の門弟が多いかが分かります。
僧伽の成立
記憶が定かでないのですが、児玉暁洋先生が「仏法僧」の三宝について、「仏」は真理の人格的表現、「法」は真理の言語的表現、「僧」は真理の社会的表現と教えてくれたことがあります。まことに的確な指摘で、仏・法・僧の三宝を貫いているのは「真理」です。真理は真理にとどまらず、おのずから言葉となり人となり社会となって相(すがた)を現し、それによって「真理」が「真実」となるのです。
釈尊が真理を覚った「仏陀」のままで終われば、「仏教」とはならなかったでしょう。「転(てん)法(ぽう)輪(りん)」といわれる伝道布教により、仏法を信じ仏法を生きるひとびとの集団(教団)ができて「仏教」となったのです。
親鸞聖人の場合は、いかがでしょうか。法難と流罪を通して、如来の一人子としての「愚禿親鸞」が誕生し、「愚禿親鸞」がまことなるが故に、あたかも鉄が磁石に吸い寄せられるように、人々が聖人のまわりに集まって僧伽(初期真宗教団・原始東国教団)が生まれていきました。
釈尊が真理を覚った「仏陀」のままで終われば、「仏教」とはならなかったでしょう。「転(てん)法(ぽう)輪(りん)」といわれる伝道布教により、仏法を信じ仏法を生きるひとびとの集団(教団)ができて「仏教」となったのです。
親鸞聖人の場合は、いかがでしょうか。法難と流罪を通して、如来の一人子としての「愚禿親鸞」が誕生し、「愚禿親鸞」がまことなるが故に、あたかも鉄が磁石に吸い寄せられるように、人々が聖人のまわりに集まって僧伽(初期真宗教団・原始東国教団)が生まれていきました。
いし・かわら・つぶてのごとくなるわれらなり
では「愚禿親鸞」と名告るようになった親鸞聖人の教えとはどんなものであり、そこに生まれ出てきた念仏の僧伽とはどんなものだったのでしょうか。
『歎異抄』第十三章には、「うみかわに、あみをひき、つりをして、世をわたるものも、野やまに、ししをかり、とりをとりて、いのちをつぐともがらも、あきないをもし、田畠をつくりてすぐるひとも、ただおなじことなりと。さるべき業縁のもよおせば、いかなるふるまいもすべしとこそ、聖人はおおせそうらいし…」〔聖典六百三十四頁〕とあります。聖人の身の回りに漁師・猟師・商人・農民がいたことが判ります。
また『唯信鈔文意』には、「屠(と)は、よろずのいきたるものを、ころし、ほふるものなり。これは、りょうしというものなり。沽(こ)は、よろずのものを、うりかうものなり。これは、あき人なり。これらを下類というなり。… りょうし・あき人、さまざまのものは、みな、いし・かわら・つぶてのごとくなるわれらなり」〔聖典五五三頁〕というお言葉がでてきます。聖人在世の時代においては「りょうし・あき人、さまざまのもの」は価値のない「下類」であり「いし・かわら・つぶて」扱いをされていたのです。そうした人々と聖人の間には距離がありません。「われら」という言い方は、聖人が人々と同座していたことを示しています。覚如上人が、聖人の「つねの御持言」として伝えるように、「われはこれ賀古の教信沙弥(しやみ)の定(じよう)なり」〔『改邪鈔』六八〇頁〕というのが聖人が選び取られた位置であったのだと思います。
『歎異抄』第十三章には、「うみかわに、あみをひき、つりをして、世をわたるものも、野やまに、ししをかり、とりをとりて、いのちをつぐともがらも、あきないをもし、田畠をつくりてすぐるひとも、ただおなじことなりと。さるべき業縁のもよおせば、いかなるふるまいもすべしとこそ、聖人はおおせそうらいし…」〔聖典六百三十四頁〕とあります。聖人の身の回りに漁師・猟師・商人・農民がいたことが判ります。
また『唯信鈔文意』には、「屠(と)は、よろずのいきたるものを、ころし、ほふるものなり。これは、りょうしというものなり。沽(こ)は、よろずのものを、うりかうものなり。これは、あき人なり。これらを下類というなり。… りょうし・あき人、さまざまのものは、みな、いし・かわら・つぶてのごとくなるわれらなり」〔聖典五五三頁〕というお言葉がでてきます。聖人在世の時代においては「りょうし・あき人、さまざまのもの」は価値のない「下類」であり「いし・かわら・つぶて」扱いをされていたのです。そうした人々と聖人の間には距離がありません。「われら」という言い方は、聖人が人々と同座していたことを示しています。覚如上人が、聖人の「つねの御持言」として伝えるように、「われはこれ賀古の教信沙弥(しやみ)の定(じよう)なり」〔『改邪鈔』六八〇頁〕というのが聖人が選び取られた位置であったのだと思います。
罪悪深重煩悩熾盛の衆生
このように社会的身分についての自己規定を最底辺のところに置かれたのは、人間の本質を、社会的身分の上に見るのでなく、身(しん)口(く)意(い)の三(さん)業(ごう)のうち、ことに意(い)業(ごう)の上に見ていかれたからだと思っています。『歎異抄』第一章に「弥陀の本願には老少善悪のひとをえらばれず。ただ信心を要とすとしるべし。そのゆえは、罪悪深重煩悩熾盛の衆生をたすけんがための願にてまします」〔聖典六二六頁〕という教えが出てまいります。この世における身分やその時々の状況は、その人特有の固定的な本質(先天的な特質)ではなく、「さるべき業縁のもよおせばいかなるふるまいもすべ」〔聖典六三四頁〕き人間のたまたまたまわった姿(後天的な現象)に過ぎない、「人間」という存在の、その本質は「罪悪深重煩悩熾盛」というところにこそある、と見切ったのが親鸞聖人ではないでしょうか。
人間は悪を畏れる存在です。仏教に五(ご)怖畏(ふい)の教えというのがあります。生きていけるか(不(ふ)活(かつ)畏(い))、世間から悪口いわれていないか(悪(あく)名(みょう)畏(い))、死ぬのでないか(死畏)、死んだら恐ろしいところへ堕ちるのでないか(堕(だ)悪(あく)道(どう)畏(い))、この世は私の敵ばかりでないか(大(たい)衆(しゅう)威(い)徳(とく)畏(い))、こうした「畏れ」が人間をその根っこで突き動かしているというのです。人間にとって「悪人」という位置は存在の危機であります。だから人間は意識的にも無意識的にも、自己を護ろうとして、独善的に自己を「善」とするか、誰もがそうだと言って「悪」であることを中和しようとするか、酒を呑むなり気を紛らわすなりして「悪」を見まいとするか、哀れなぐらいなまでにジタバタしているのです。仏道を求めるといっても、それは「悪」からの逃避なのかもしれません。念仏申すといっても「さこそ悪人をたすけんという願、不思議にましますというとも、さすがよからんものをこそ、たすけたまわんずれ」〔『歎異抄』六三七頁〕と、自力のはからいに囚(とら)われてしまいます。それほど「悪」を畏れる心は根深いものがあります。
聖人の「つねのおおせ」は「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり。されば、そくばくの業をもちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ」〔聖典六四〇頁〕でありました。お経に説かれている阿弥陀仏の五劫思惟のご本願は、他人事ではなかった、この私を助けんがためでこそあった、という目覚めだけが、「地獄一定(いちじょう)」の「悪人」の私を引き受けて生きていくことを可能にするのです。
人間は悪を畏れる存在です。仏教に五(ご)怖畏(ふい)の教えというのがあります。生きていけるか(不(ふ)活(かつ)畏(い))、世間から悪口いわれていないか(悪(あく)名(みょう)畏(い))、死ぬのでないか(死畏)、死んだら恐ろしいところへ堕ちるのでないか(堕(だ)悪(あく)道(どう)畏(い))、この世は私の敵ばかりでないか(大(たい)衆(しゅう)威(い)徳(とく)畏(い))、こうした「畏れ」が人間をその根っこで突き動かしているというのです。人間にとって「悪人」という位置は存在の危機であります。だから人間は意識的にも無意識的にも、自己を護ろうとして、独善的に自己を「善」とするか、誰もがそうだと言って「悪」であることを中和しようとするか、酒を呑むなり気を紛らわすなりして「悪」を見まいとするか、哀れなぐらいなまでにジタバタしているのです。仏道を求めるといっても、それは「悪」からの逃避なのかもしれません。念仏申すといっても「さこそ悪人をたすけんという願、不思議にましますというとも、さすがよからんものをこそ、たすけたまわんずれ」〔『歎異抄』六三七頁〕と、自力のはからいに囚(とら)われてしまいます。それほど「悪」を畏れる心は根深いものがあります。
聖人の「つねのおおせ」は「弥陀の五劫思惟の願をよくよく案ずれば、ひとえに親鸞一人がためなりけり。されば、そくばくの業をもちける身にてありけるを、たすけんとおぼしめしたちける本願のかたじけなさよ」〔聖典六四〇頁〕でありました。お経に説かれている阿弥陀仏の五劫思惟のご本願は、他人事ではなかった、この私を助けんがためでこそあった、という目覚めだけが、「地獄一定(いちじょう)」の「悪人」の私を引き受けて生きていくことを可能にするのです。
御同朋・御同行
聖人は「親鸞は弟子一人(いちにん)ももたずそうろう」〔『歎異抄』六二八頁〕と言われました。なぜなら「わがはからいにて、ひとに念仏をもうさせそうらわばこそ、弟子にてもそうらわめ。ひとえに弥陀の御もよおしにあずかって、念仏もうしそうろうひとを、わが弟子ともうすこと、きわめたる荒(こう)涼(りょう)のことなり」〔『歎異抄』第六章・六二八頁〕との自覚に立たれていたからです。
それは、聖人が人々を単に同等に見たというよりも、「如来のもよおしにあずかった」人として上に仰いでいたと言うべきでないでしょうか。
それは、聖人が人々を単に同等に見たというよりも、「如来のもよおしにあずかった」人として上に仰いでいたと言うべきでないでしょうか。
よしあしの文字をもしらぬひとはみな まことのこころなりけるを
善悪の字しりがおは おおそらごとのかたちなり 〔聖典五一一頁〕
善悪の字しりがおは おおそらごとのかたちなり 〔聖典五一一頁〕
というご和讃や、
故法然聖人は、「浄土宗のひとは愚者になりて往生す」と候いしことを、たしかにうけたまわり候 いしうえに、ものもおぼえぬあさましき人々のまいりたるを御覧じては、往生必定すべしとてえませ たまいしをみまいらせ候いき。 〔『末燈鈔』六〇三頁〕
という思い出に窺えることは、いなかの人々に対する敬愛であります。蓮如上人はこうした親鸞聖人の姿勢を、
聖人は御同朋・御同行とこそかしずきておおせられけり。 〔『御文』第一帖第一通七六〇頁〕
と教えて下さっています。
聖人の生きられた世界は、如来の前に平等にひろがる「同朋」の世界でした。個人的な見解を許していただけるならば、親鸞聖人の僧伽は日本ではじめて実現した平等社会だったのです。士農工商の身分制度の撤廃(明治政府)や婦人参政権の獲得(戦後憲法)などがごく最近のことだったことを思えば、いかに革命的であったかわかると思います。後に蓮如上人の時代になって、武士の支配に対し一向一揆をおこし、ついには加賀を「百姓のもちたる国」とすることができたのも、親鸞聖人の開かれた「御同朋御同行」の精神から来ているといえると思います。
同じ浄土を願う念仏集団でありながら、時宗や浄土宗にはない「御同朋・御同行」の僧伽形成のエネルギーは、どこから湧き出てきたのか。それは聖人の信心が、自力無効の自覚に立つ徹底した他力主義であり、未来往生の夢想を破った現(げん)生(しょう)(正定聚)主義であったからだと思います。
東国に生まれた念仏の僧伽こそ、聖人の教えの証(あかし)だったのでした。
聖人の生きられた世界は、如来の前に平等にひろがる「同朋」の世界でした。個人的な見解を許していただけるならば、親鸞聖人の僧伽は日本ではじめて実現した平等社会だったのです。士農工商の身分制度の撤廃(明治政府)や婦人参政権の獲得(戦後憲法)などがごく最近のことだったことを思えば、いかに革命的であったかわかると思います。後に蓮如上人の時代になって、武士の支配に対し一向一揆をおこし、ついには加賀を「百姓のもちたる国」とすることができたのも、親鸞聖人の開かれた「御同朋御同行」の精神から来ているといえると思います。
同じ浄土を願う念仏集団でありながら、時宗や浄土宗にはない「御同朋・御同行」の僧伽形成のエネルギーは、どこから湧き出てきたのか。それは聖人の信心が、自力無効の自覚に立つ徹底した他力主義であり、未来往生の夢想を破った現(げん)生(しょう)(正定聚)主義であったからだと思います。
東国に生まれた念仏の僧伽こそ、聖人の教えの証(あかし)だったのでした。