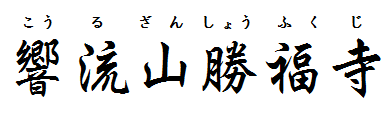二〇二二年五月四日
渡辺元義二十五回忌・シゲ子十三回忌法要記念法話
一如のいのち 藤谷知道
法事を勤める意味
今日は皆さんにとっては祖父(おじいちゃん)になる渡辺元義さんの二十五回忌と、祖母(おばあちゃん)になる渡辺シゲ子さんの十三回忌のご法事ということで、まずお経をあげさせていただきました。これからの時間は、お父さんの和義さんから、今日は子どもたちに仏教の教えを話して欲しいと言われておりますので、仏教とはどういう教えなのか、しばらくお話させていただきたいと思います。
ところで「法事」というと、死んだ人のためにお経をあげることのように思われがちですが、実は、もっと深い意味があります。「法事」という字を分解すると「法」の「事」となりますね。ここでいう「法」は「仏法」のことです。「仏法」とは「仏のあきらかにされた法=真理」という意味です。
ですから「法事」とは、お経を通して仏法を聞き、仏法に教えられて亡き人に深く出会っていく。亡き人に深く出会うことを通して、私が今ここに生きていることの尊さ、有り難さに目覚めていく。それが「法事」を勤める意味なんですね。
人間の中にある二つの心
みなさんの心の中に、こういう矛盾した心がありませんか。
一人でいたら淋しい。
二人でいたら煩わしい。
私の中にはこうした矛盾する二つの心があります。みなさんは、どうですか。今日は、人間にあるこうした矛盾する心について仏教の視点を通して考えてみようと思います。
私はながい間、一体どちらが私の本心なのかと思い煩ってきましたが、今は、どちらも私の本心だと思うようになりました。私の中には、「一人でいたら淋しい」と思う心と、「二人でいたら煩わしい」と思う心と、二つの心があるのですね。これは私個人にとどまることではなく、人間という在り方に必然する心のようです。
いのちの海
私は歳をとるにつれ、「一人でいたら淋しい」と思う心はいのちに根ざした心なんだと思うようになりました。
いのちは機械的に造ることができませんね。また、いのちは自分かってに生まれたものでもありませんね。いのちは他のいのちと深く繋がりあってこそ、はじめて存在できているのです。
まずなによりも、私たちが生きているこのいのちは、親から子へと受け継がれてきたいのちですね。金子みすずさんを見出しこの世に紹介された矢崎節夫さんが、「私が生きているこのいのちは、地球上に現れたはじめのいのち(アメーバ)から一度も死なずにリレーされてきたいのちなんだ」と話すのを聞いて、「あっと」驚き、「そうなのか!」と嬉しくなったことがあります。考えてみれば、まことにそうなんですね。私の父や祖父母はすでに死んでこの世にいませんが、私を産んでくれた時の父母は元気だったんです。
また、いのちはいのちでないもの、たとえば石ころのような無機物を食べて生きることはできません。私ども人間は、動物にしろ植物にしろ、必ず他のいのちをいただいて、はじめて生きることができるているのです。
このように、いのちは他のいのちと繋がってこそ存在できているのです。つまり、いのちは時間的にも空間的にもいのちの海に浮かんでいる存在なんですね。
孤独はいのちの危機
このように、いのちはその本質として、他のいのちと繋がってはじめて存在できているものです。だから、日々の生活において、他のいのちと繋がっていれば嬉しくなり、安心できるのです。反対に、他のいのちとの関係が切れた「一人ぼっち」の状態は淋しいし不安になります。
こんなこと、ありませんか。皆さん、けんかをしたら、どんな気持ちになりますか。嬉しいということはないですよね。夫婦げんかでも親子げんかでも、けんかをしたら心がささくれだちますよね。やっぱり心が通じ合ったときの方が嬉しいですね。
あるいは、幼い子どもたちは「おじいちゃん」とか「おばあちゃん」とか叫んで飛び込んできますよね。そして、手を取り「遊ぼう」と言うでしょう。自我意識が目ざめる前の子どもはいのちと一つになって生きているから、いのちの命ずるままに繋がりあいを求めているのですね。
このように「ひとりでいたら寂しい」という感情の元を探っていけば、いのちはその本質において他のいのちと繋がっているということがわかってきます。だから、他のいのちと繋がろうとするし、残念ながら繋がることできなかったら、つまりひとりぼっちを思い知られたら寂しく感じてしまうのです。
いのちの原点 ー 母と子 ー
いのちといのちの繋がり合いの原初形態は、母と子、です。それから次第に、父親、兄弟、祖父母から呼びかけられて、いのちの繋がりが拡がっていきます。それが家庭ですね。家庭の中では、自分は見捨てられない、しっかり抱きしめてくれる人がいる。だから嬉しい、だから安心なんですね。
幼い時、こうした家庭に恵まれた子は、いのちの根っこのところに、生きることの歓びとこの世にあることの安心とが育まれていくことでしょうし、幼い時に育まれた安心と歓びはその人の一生を内から力強く支えてくれます。逆に、暖かく包みとってくれる家庭に恵まれなかった子どもは、その生涯にわたって、いのちの根っこに不安と怒りを抱えて生きていかざるをえないことになるのではないでしょうか。
新しい繋がりを求めて
ところで、人間は成長していくにつれ、家庭を出て、新しい人間関係をつくっていかねばなりません。それがうまくできるか、できないか、これこそが人間にとって根源的な課題であり、最大の試練と言ってもいいと思います。
子どもをよくよく見ていたら「友だち」という言葉が子どもの生活におけるキーワードであることがわかります。友だち関係がうまくいっていると、子どもは生き生きしています。逆に、友だちがいないことは子どもにとっていのちの危機といってもいいくらいです。
このことは子どもだけのことではありません。実は、大人においても同じです。人間は家族なり、友人なり、自然なり、他者と心が通い合うことが最もいのちの自然な相(すがた)なのですね。孤独こそいのちにおける最大の危機です。
聞いて「あ!」っと思ったのですが、最近、イギリスでは「孤独担当大臣」が設置されたそうです。科学文明が進めば進むほど、孤独な人間が増えております。それは担当大臣を設置しなければならないほど、個人的にも社会的にも深刻な問題であるということでしょう。
自我意識
いのちが繋がりあいを求めるものなら、自分だけでなく、相手も繋がりあいを求めているに違いありません。求める者と求める者同士なら、そこには何の問題もないはずですね。なのに、なぜか、うまくいかない。なぜでしょうか。その原因は、繋がりあいたいという私の心の中に、困ったことに「自分の思い通りの形で」繋がりあいたいという心が隠れ潜んでいるからなんです。
つまり、いのちの自然な要求として繋がりあいたいという心が起こるとき、その心に重なるようにして、私と同じようにあなたもあってくれという要求が無意識のうちにおこっているのです。
たとえば、子どもが「パパ、遊ぼう」と言った時、「うん、遊ぼうか」と答えたら、子どもは大喜びしますよね。しかし、「今は、ダメ」と返事したら、子どもは「つまんない」と下をむくでしょう。そのように、自分の思い通りに相手がならないときの感情が「ひとりぼっちの寂しさ」なんです。
人間は一人ひとり違う心身、違う状況を生きています。(仏教ではそれを宿(しゅく)業(ごう)の身と言います)。たとえ一卵性双生児といえども、いつしか違う存在になっていきます。人間は本質的に孤独な存在なのです。だから、たとえ親子といえども、恋人といえども、いつも同じであることはできません。それがいのちの事実なのです。
それなのに、他に対して私と同じであることを要求する心がとめどもなく湧いてくる。時には、他と繋がりたいという欲求を満たすために相手に合わせようとすることもありますが、それは仕方なくしていることであって、それでは満足が得られません。結局は、私の思い通りにしたいという自我意識に打ち負けて、いつしか、相手に対し自分と同じようになることを要求し、その要求が満たされるかどうかで一喜一憂して生きているのです。
このように見てくると、他と繋がりあいたいといういのちの深い願いが、自分の思い通りにしたいという自我意識に呪縛されて、ゆがんだ形になっていることが判ってきます。
プーチン大統領によるウクライナ侵攻の秘密
例えば、今度のロシアによるウクライナ侵攻のもとには、「ロシアもウクライナも同じスバル民族でないか。なぜ兄貴分であるロシアの言うことをおまえは聞けないのか」という、プーチンひいてはロシア人の独りよがりな思いあがりがあるのです。ロシアによるウクライナ侵攻は、ロシアからすれば「善意」に基づく正義であり、ウクライナからすればとんでもない言いがかりであり、迷惑千万なことです。このように、個々人同士の間だけでなく、国家間においても、仲良くしよう、だから俺の言うことを聞け、ということが起こるのです。
これはプーチンのロシアだけのことでなく、戦前の日本がアジアの国々に押しつけた大東亜共栄圏構想がそれであり、アメリカを中心とした自由主義も中ソを中心とした共産主義運動も、同じ発想に基づいて、ひとりよがりな「善意」によって他国を侵略してきたのです。
絶望を超える道
いのちの要求も自我意識に搦(から)みとられたならば、「仲良くしよう」が「俺の言うことを聞いてくれ」となります。当然のことですが、その呼びかけは拒絶にあい、最初にあった仲良くしたいという願いは成就できず、宙に浮いたままになります。
「仲良くしたい」という思いが軽いときは「しかたない」とあきらめですむかもしれないが、恋人なり親子なり、「仲良くしたい」という思いが激しいときは、立ち上がれないほどの深い傷を負い、人生全体までも絶望してしまうことになります。
ところが、いかに深く絶望しても、人間は絶望の中にとどまっておれません。いつしかいのちの欲求に突き動かされて、また知らず識らずのうちに他者を求めはじめます。それがいのちというものです。いのちの要求に自我が絡まって、愛と絶望を一生繰り返しているのが人間ではないでしょうか。
一つになりたいといういのちの欲求と、この世に同じものは一つとしてないという絶望と、この矛盾は解けないのか。この矛盾の解決を求めて人間は生きてきました。これが人間に共通した苦しみであり、悲しみであります。そして、人間のあるところ、世界のどこにおいても、それをテーマに歌がつくられ、小説が書かれたりしてきたのです。
愛しても出会えず(すれ違い)、絶望しても絶望しきれず、死ぬまで愛と絶望の間を揺れ動く人間に、この悲しみを超える道を用意くださったのが仏教です。
一如の智慧
仏教に「一(いち)如(にょ)」という教えがあります。「一如」とはどういうことかというと「二(に)而(にして)不(ふ)二(に)(二にして、二にあらず)」ということです。
この世に同じものはありません。リンゴを一つ、二つと数えていって、たとえばリンゴが十個あるとか言いますが、実は、同じリンゴが十個あるのではありません。十個の違うリンゴがあるのです。
そのように同じものは二つとない、みんな違うということを「二」で表します。それに対し、同じであるということを「一」で表します。
話をリンゴに戻していうと、リンゴは一つ一つ違います。だから「二」です。しかし、リンゴの姿かたちは違っていても、リンゴということでは同じですね。そういう意味では「一」です。このように「二」にして「一」であることを「一如」といいます。
「一如」とは、現れ出ている姿は違っている(二である)けど、その本質においては一なんだということです。
例えば、この紙。こちら側が表とすれば、反対側は裏ですね。それでは表と裏との二つに分けられるかというと、実は分けられないのです。表と裏と分けようとして薄く、薄く切っていっても、かならず表と裏ができる。裏のない表もなければ、表のない裏もない。つまり、一枚の紙が表と裏という姿をとって存在しているのです。この場合、紙が「一」で、表・裏が「二」です。
同じように、一日に昼と夜とがあるけれど、昼だけということも夜だけということもない。昼と夜とで一日です。男と女、親と子、みんなそうです。現れている相は、男と女、表と裏、昼と夜、生と死、現れ方はいつも二つになっているけど根っこは同じ。それで二にして一、一にして二、と。表面は二つになっているけど根っこは一つに繋がっている。そういうのを一如というのです。これが仏教によって見いだされた一如の智惠です。
分別する知恵
しかし、人間の目から見ると「一如」ということに気づくことがなかなかできません。男と女は違いますよね。自分と他人は一緒とは思えないでしょう。私たちの目は違いの方にばかり向くようになっています。そうした人間の目を仏教では「分別知」と言います。
私が大学生のとき、友だちとヤップ島(現ミクロネシア共和国)にテントを担いで行ったことがあります。一週間ほどお世話になったロボマンさんのお家に着くと、たくさんの子どもがわーっと出てきました。聞くと、「みんな俺の子だ」というので、島の実力者ともなると奥さんもたくさんいるんだと思ったものです。
しかし、後になって分かったことですが、ヤップの言葉には、日本語で言うところの「甥」や「姪」にあたる言葉がなかったんですね。だから兄弟の子どももみな自分の子どもになる。アフリカには、数を数えるのに「1、2、3」までしかなく、後は「たくさん」でひとくくりする部族があると聞いたこともあります。
それに対し、文明が進むとどうなるかというと、日本語で言えば、兄弟の子は「甥」となり「姪」となる。中国語だと、自分の親より年上か年下かで「伯父(母)」「叔父(母)」と使い分けてくる。つまり文明が進むということは、どんどん小さく細分化してものごとを認識することができるようになることなんですね。
部分の集合は全体ではない
例えば昆虫だったら、幼い時は、「虫」の一語で昆虫をひとくくりしますね。それが次第に、あれはカブトムシ、これはトンボ、違いがわかってきます。さらに、学校で勉強するにしたがって、〇〇目〇〇科○○属○○種と、どんどん細分化して認識していくことになります。そのように細分化して認識していく能力が「頭がいい」こととされるんです。
でも、そうやって小さく切って分けていくということは、全体を見失っていくことでもあるのですね。たとえば、人間でいうと、人間の身体には頭と胴と手と足とがありますね。でも、頭と胴と手と足とが別々にあって、それを自動車のようにネジなんかでとめて出来あがったものではないですよね。自動車ならバラバラに解体して、また組み立て直すことができますが、人間の身体はバラバラにしたり組み立て直したりできません。
あるいは、頭と首と胴体の境目はどこですかといわれたら、答えられないでしょう。頭と首と胴体の境目はどこにもないですね。そのように、いのちは一つに繋がった全体としてある。全体としてあるのだけれど、頭と胴体と手と足が同じということでもない。それぞれ違って一つである。そういうのが「一如」という考え方だと思います。
いのちを傷つける罪 ー 分別知 ー
実は、全体としてあるいのちを部分部分に分けて認識していく「分別」は、その本質としていのちを傷つけることにつながっているのです。経験則でいうと、「頭がいい」と世間で言われている人の方が「頭が悪い」と言われている人より冷たい、ということがありませんか。寅さんみたいな人の方があたたかいということがあるでしょう。
知性、つまり分別で存在を理解していくことには冷たさがあります。子育てなんかにおいても、子どもの一部を見て、たとえば勉強ができるかできないかとかでもって、その子をいいとか悪いとかいうのはあぶないですね。言われた子どもは、自分の全体までもが切って捨てられたように感じてしまうことになります。
それだけではない。人間の目はその分別のうえに、さらに「自我意識」(自己中)という色メガネがかかっているんです。自己の経験、自己の関心、自己の欲求など、自己中心の色メガネを通してしかものを見ることができません。
ロシアによるウクライナ侵攻は、我々から見れば決して許されない暴挙なのに、ロシアの人から見れば自分たちはいいことをしていると思っているんですね。なぜそういうことがおこるかというと、それは無意識のうちに自我意識(エゴ)を通してものごとを見、考えているからです。
二つに引き裂かれたいのち
もう一度もとに戻って考えてみましょう。いのちはその本質として、独りでは不安定です。なぜなら、いのちはそのはじめ、母の胎内で暖かく護られて成長しました。それが、およそ十月十日後、母の胎内から切り離されてこの世に産み落とされのです。つまり、この世に生まれ出たということは、母との一体が引き裂かれ、母と子の二つにされたことなのです。一人にされた赤ちゃんは不安でしかたない。赤ちゃんの泣き声は自分を抱きしめてくれる母親を求める切ない声でありましょう。
いのちはこの世の最初の一歩において、一つであったものが二つに引き裂かれたという、深い深い傷を背負ったのです。だから、いのちは本能的にその傷を回復したいという欲求をもっている。つまり、他と繋がって一つになることを求めてやまない存在なのです。家族を求めるのも、友だちを求めるのも、恋人を求めるのも、いのちの根っこに、他と繋がり、一つになりたいという強い欲求があるからです。
ところが、そのように他を求める本能的要求が、他者と自分とを違った存在としか見えない分別知と、他者に自分と同じであれと要求してしまう自我意識とに呪縛されていたら、どうなるでしょうか。他者と一つになろうとすればするほど、傷つけ合い憎しみ合い、ついには、一つになることをあきらめ、絶望してしまうしかなくなるのです。
みんなちがって、みんないい
人間の一生においても、人類全体の歴史においても、人間は愛と挫折とをくりかえしてきました。この出口のない繰り返しを仏教では流転と言います。お釈迦さまはこの流転をを引き起こす原因に気づき、それを超える智慧を手に入れました。それが仏教の教えてくれる「一如の智慧」だと思います。
金子みすずさんに、「わたしと小鳥とすずと」という詩があります。
私が両手をひろげても
お空はちっとも飛べないが
飛べる小鳥は私のやうに
地面を速くは走れない
私がからだをゆすっても
きれいな音は出ないけど
あの鳴る鈴は私のやうに
たくさんな唄は知らないよ
鈴と、小鳥と、それから私
みんなちがって、みんないい
ここで謳われた「鈴と、小鳥と、それから私、みんなちがって、みんないい」という歓びこそ、「一如の智慧」によって切り開かれた世界です。
姿かたちはみんな違っているけれども、同じ一つのいのちを生きている。違ったままで、同じ。このことがわかる時、出会いを求めるいのちの要求が成就、満足できるのです。
存在をまるごと受け止める
金子みすずさんには「星とたんぽぽ」という詩もあります。
青いお空の底ふかく、
海の小石のそのように、
夜がくるまで沈んでる、
昼のお星は眼にみえぬ。
見えぬけれどもあるんだよ、
見えぬものでもあるんだよ。
散ってすがれたたんぽぽの、
瓦のすきに、だァまって、
春のくるまでかくれてる、
つよいその根は眼に見えぬ。
見えぬけれどもあるんだよ。
見えぬものでもあるんだよ。
目に見えない部分を感得できる心を養っているか。例えば、一つのものを食べるときでも、そこにいろんなもののおかげを感得できるか。そうした感性を失っていくとどうなるかというと、「美味しいか、美味しくないか」、「値段が高いか、安いか」、この二つでしかものを見れないようになる。
もし、「美味しいか、美味しくないか」「値段が高いか、安いか」だけでしかものを見れなくなると、それは食べ物にとどまらず、人間もそういうふうにしか見れなくなる。「役に立つか、立たんか」、「給料が高いか、安いか」、そういうふうにしか人を見れなくなる。
子育てにおいても、「お前がそこにおるだけで嬉しい」、「お前はそれでいいんだよ」と抱きしめることができなくなり、お金をどれだけ稼げる子になるかが大事になってしまう。それでは寂しい話ですね。
人間には、ついつい自我に縛られていのちの全体を見失いがちですが、それではいのちが満足しない。「俺か、おまえか」、「損か、得か」、そうしたものを超えた豊かさや深さを求める心が人間にはあるんです。それはいのちのおのずからなるはたらきであり、うずきであり、願いであります。
大いなる流れ
人間の知性を仏教では「分別知」ということをこれまで見てきました。分別知では、自分と他人が別物としか思えない。「自と他」が対立してしまう。分別知をはたらかせばはたらかせるほど、違いばかりが大きくなって、自他を貫く一なる部分が見えなくなる。この分別知に基づいて他と一つになろうとするから、結局は、傷つけ合うか、あきらめるか、の繰り返しに終わるということでした。
この「分別知」のもう一つの問題点が「生と死」の分別です。分別知では、生まれる前の私、死んだ後の私、など考えることができません。私は生まれ落ちてから死ぬまでが私であって、その前後には私はいないとしか思えません。だから分別知によればよるほど、父や母は他人に思え、子や孫も自分の思い通りにならなくなるにしたがって、赤の他人のように思えてきます。
はたして、そうでしょうか。あたりまえのことですが、バラの苗から菊の花は咲きません。馬から牛が生まれることもありません。バラの苗からはバラの花が咲き、馬からは馬が生まれるように、私は私以外の何者かから生まれ出たのではないのです。父や母が私となって、私はこの世に生まれ出た。ならば、父や母は私の内容ではないでしょうか。子や孫も私の分身でありましょう。父や母、子や孫に、眼に見える違いを超えて、そのなかに自分自身を感得する、それが一如の智慧であります。
自分の番を生きている
例えて言えば、駅館川の水が上流より流れてきて、ある瀬で沫がポッとできて、その沫がしばらく流れてパチンと割れたとしても、沫は割れたけど、なくなったわけではない。またもとの川に戻っただけ。私たちの一生もそのように姿かたちは変わっていきますが、いのちの流れは一緒なんです。
相田みつおさんは、
生まれ変わり死に変わり
永遠の過去のいのちを受け継いで
今、自分の番を生きている
それが、あなたのいのちです
それが、私のいのちです
と歌っています。
ところが、私たち人間の自我意識は他と分別した「自分」だけしか「自分」と思えませんので、自分が死んで無くなってしまうことはたとえようのない恐ろしさであり、とてもそれを受け入れることはできません。それは人間だけにある意識なんですね。他の生き物、草木や動物には死を恐れるということはないのではないでしょうか。
例えば、庭の水仙。今は花も咲きおえて、まもなく枯れていくわけですが、そのことを水仙は、人間のように「いやだ、いやだ」「こわい、こわい」と言って駄々をこねていません。私には、水仙はいのちが移ろいゆくことに対して満足して順っているように思えます。夏になるとしずかに枯れ、冬が来るとまた芽を出し、新しい花をつけていく。それは水仙だけでなく、いのちを生きるものすべてが生死するままに身をまかせ、それに満足しているのではないでしょうか。
人間もほかの動物や植物と同じように、いのちの流れを生きているのです。本当なら、自分の役割を果たし終えたら死んでいっても十分なはずです。でも、そうならない。なぜかというと、「私」という意識で生きているから。「私」は死を恐れるだけでなく、病気になることも、年をとることも、いやでいやで仕方ない。「私」という意識はいのちの自然に背いている意識なんですね。
ですから、そうした「私」という意識の呪縛から解き放たれてみれば、和義さん、末子さんからあなたたちへ、そのあなたたちからあなたたちの子どもたちへと、いのちは順番に流れていっているのですね。あるのは一人一人の役割であって、私という意識は蜃気楼のようなもの。あるのは大いなるいのちの流れであって、それを仏教の言葉で「無量寿」というのだと思います。
『安心決定鈔』
お渡しした資料を見て下さい。そこに『安(あん)心(じん)決定(けつじょう)鈔(しょう)』という書物の言葉が引用されています。これは誰が書いたのかわかっていません。しかし、浄土真宗の中興の祖と言われている蓮(れん)如(にょ)上人は、
『安心決定鈔』のこと、四十余年が間、御覧候へども、御覧じ飽かぬと仰せられ候ふ。また金(こがね)を掘り出すやうなる聖教なりと仰せられ候ふ。
(『御(ご)一(いち)代(だい)記(き)聞(きき)書(がき)(二四九)』 )
とおっしゃられました。その『安心決定抄』に、
しらざるときのいのちも、阿弥陀の御いのちなりけれども、いとけなきときはしらず、すこしこざかしく自力になりて、「わがいのち」とおもいたらんおり、善(ぜん)知(ち)識(しき)「もとの阿弥陀のいのちへ帰せよ」とおしうるをききて、帰命(きみょう)無(む)量(りょう)寿(じゅ)覚(かく)しつれば、「わがいのちすなわち無量寿なり」と信ずるなり。
という言葉が出てきます。
わがいのちすなわち無量寿なり
「しらざるときのいのちも」ということは、気がつかなくても、ということです。「阿弥陀の御いのちなりけれども」、「阿弥陀」というのは無量寿なるいのち、永遠のいのちということですね。「阿弥陀の御いのちなりけれども」というのは、私のいのち、あなたのいのちと限るのでなく、いのちは大いなるいのち、阿弥陀のいのちなんだ、というのですね。「いとけなきときはしらず」とは、幼いときは何も分からないけれど、「すこしこざかしく自力になりて」、知恵がつくに順って「自力になりて」というのは、自分を中心にしてものを考えるようになるということですね。そうすると「わがいのちとおもいたらんおり」、知恵がつき自力になると、「私のいのち」と思うようになるのですね。そのとき善知識(善き師)から「もとの阿弥陀のいのちへ帰せよとおしうるをききて」、つまり善き先生に出会って、先生から「そのいのちはお前のいのちか。阿弥陀のいのちじゃないのか」と教えられ、「もとの阿弥陀のいのちへ帰せよ」の教えのまま「帰命無量寿覚」すれば、つまり「南無阿弥陀仏」と永遠のいのちに帰命すれば、「わがいのちすなわち無量寿なりと信ずるなり」、このいのちは阿弥陀のいのちなんだ。私のものじゃないんだ。みんなに広がっている大いなるいのちなんだと信ずることができたというのです。
私どもの恩師である、故・信国淳先生(大谷専修学院長・大分県宇佐市元重の来覚寺住職)は、こういう教えを受けて、
われら 皆共に安んじて
いのちに立たむ
いのちすなわち
念仏往生の道なればなり
と詠まれました。また、死の直前の講義で
汝、無量寿に帰れ
無量寿に帰って
無量寿を生きよ
と獅子吼されました。
浄土こそいのちの真実
今、ロシアがウクライナに戦争をしかけました。アメリカでは、トランプ旋風が吹き荒れ、国が二分してしまいました。中国も独りよがりな中華思想でもって世界の覇者を目指してます。日本においても、勝ち組・負け組だの、正規・非正規だの、分断が進み競争が激しくなるばかりです。平和な世界は遠ざかり、恐ろしい世の到来が予感されてなりません。
こうした現実を見ていると、くらい気持ちになりますね。お浄土と言われても遠い夢のようにしか感じられないかもしれません。でも、私は思うんです。いくら現実が地獄化していようとも、あるいは、現実が地獄的であろうとも、それは自己中心的な人間の煩悩が造り出した現実であって、いのちの真実ではないと。
目に見えるものだけではない。目に見えるものよりもっと深い世界がある。本当は、自分たち一人一人を支えたい。そういう世界にあっては、みんなそれぞれがそれぞれに生かされている。そこでは、上下がない。若者も年寄りも男も女もそれぞれがそれぞれの役を果たす。走るのが速くても遅くても、算数が速くできても遅くてもどっちが上ということはない。それぞれみんなが輝く一如のいのちの世界こそが喜びであって、それを浄土というのです。勝った負けたの世界にいたら最後は地獄・餓鬼・畜生の三悪道に堕ちてしまいます。