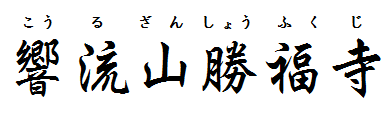関東から京都まで十余か国もの境を越えて、「ただ念仏一つ」と聞いてきた往生極楽の道が間違っていないか?という命がけの疑念を抱えて聖人のもとへやって来られた人々を前にして、「親鸞におきては、ただ念仏して、弥陀に助けられまいらすべしと、よきひとのおおせをかぶりて、信ずるほかに別の子細なきなり」と語り出されたお言葉。それに続く「念仏は、まことに浄土にうまるるたねにてやはんべるらん、また地獄におつべき業にてやはんべるらん。総じてもって存知せざるなり」というお言葉。さらに「たとい、法然上人にすかされまいらせて、念仏して地獄におちたりとも、さらに後悔すべからずそうろう」とおっしゃって、「いずれの行もおよびがたき身なれば、とても地獄は一定すみかぞかし」と続く聖人のお言葉に、関東の人々は身の疲れも忘れて姿勢を正し、涙したのではなかったか。そして聖人が、よき人の仰せを仰いでっている大地の思いも及ばなかった深さに、高上がって迷っている自身を思い知らされたのではなかったか。
「親鸞におきては、ただ念仏して弥陀に助けられまいらすべしと、よきひとのおおせをかぶりて、信ずるほかに別の子細なきなり」という言葉を支えているしずかな力強い信心が私達の上に成り立つのは容易ではない。だから聖人なき後の関東の人々が、慈信坊の言葉によって動揺していったことは他人事とは思えない。それを聖人は、「慈信坊がもうすことによりて、ひとびとの日ごろの信のたじろぎおうておわしましそうろうも、詮ずるところは、ひとびとの信心のまことならぬことのあらわれてそうろう。よきことにてそうろう」とおっしゃっている。
化身土巻には、「信不具足」について、「一つには道あることを信ず、二つには得者を信ず。この人の信心、ただ道あることを信じて、すべて得道の人あることを信ぜず」とある。念仏が往生浄土の道であると信ずることができるのは、現にその道に立つて歩いている人がいるという事実に出遇ったからである。関東の人々も、この二つを具した信心に生きていたのであろうが、身近に聖人がおられなくなって、慈信坊の話に動揺し、聖人への信までもがぐらついてしまったのだった。親鸞聖人は、法然上人の説かれる念仏より他に、地獄一定の自身の助かる道はないと、本願に帰命されたのであった。だから、「弥陀の本願まことにおわしまさば・・・」と続けられている。本願のまことへの信によって、道への信も得道の人への信も成り立っている。
私の場合は、自身を生かしそれに満ち足りていく道が念仏にあると教えてくださった先生を縁として、お念仏を申すようになったのだが、念仏が何なのか、助けられねばならない自身とは何なのか、自覚してはいなかった。ただ聞法を続けていくことによって、現実の自身とはどういう者であるか、それを親鸞聖人の自証のお言葉によって、いよいよ深く知らされつつある。そしてそれは自身を知る深い痛み・悲しみであると同時に、自身に出遇う深い喜びでもある。曠劫来の身に具わっている罪業性と無明性、この苦悩の身に本願の念仏が届けられている。「道を信じ」「得道の人を信ず」という信心の我(責任主体)を賜ったことで、この身を今の時代社会において共に生きていく生活が、愚拙ながらも開かれてきていることに感謝したい。
南無阿弥陀仏