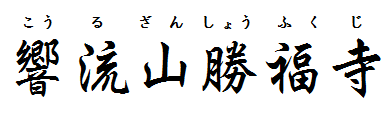(出雲路暢良先生三十三回忌法話)
先生に迎えられて(3)
藤谷純子
いつわりなき光を仰ぐ
この「いつわりなき光」とはどういう光なのかということを考えながらいた時に、この度、先生のこういう文章に出会いました。
臘扇とは、
十二月の扇、これは清沢先生の最後の名のりですよね、役に立たないもの、要らんものという意味です。
臘扇とは、単に自己の価値無きことを歎かれた名ではなくして、自己に価値を見いだすことによって生きようとすること、相対的価値に生きようとすることそのものが無意味であり、妄念妄想に過ぎないことを自覚せられた御名であった。否、先生は、相対的価値に生きんとすることそのものの無意味であることを照らし出した光を、仰いでおいでになるのである。この光によってあらしめられてある、ありのままの自己をいただいておいでになるのである。相対の世界を一歩ぬきん出て、絶対の天地に逍遥しておいでになるのである。臘扇とは、生きる理由を自己の価値に持とうとすることを、根源的な罪、謗法の罪として自覚せられた先生の懺悔であった。かくして先生にあびせかけられた誹謗擯斥陵辱は、
清沢先生は世間においていろんな改革運動をしてきたけれども、次々と失敗され、そして結核のもう治らない身を、自分の父親を連れて西方寺という養子先のお寺に帰られることになったのですね。
初めは、住職として迎えるには日本一の者でなければならんということで、東大出の立派な先生だということで選ばれ入寺されたと聞いておりますけれど、最後は二畳くらいの部屋に隔離されて寝食するという、そういう生活を余儀なくされたんですね。
総代さん方から「もう出ていってもらおうではないか」と、そういう話し合いがあったとも聞いています。その時、一人の総代さんが、「みんな仏法に御縁をもちながら、因縁ということがわからないのか。御縁あって来ていただいた先生なんだ。そういう人を追い出すことはできるもんではないんだ」と、そういうかたちで総代さん方を説得してくださったようにありますね。それでも、痰ツボを抱え血痰を吐きながら御法話したり、お参りに行ったりすると、「もう来んでいい」という誹謗擯斥を受けながら、でもその誹謗擯斥が――、
かくして先生にあびせかけられた誹謗擯斥陵辱は、先生に真の自己を発見せしめて、臘扇の自覚を開かしめたのであったが、この自覚が逆にまた、先生に、その誹謗擯斥陵辱をそのまま如来の顕現として仰いでいく道を開いたのである。「黙忍堂」とは、単に忍び難きを忍ぶの語ではなくして、万感交々の自己現前の境遇をそのまま無限他力の賦与としていただかれた先生の御名であった。
ここには、およそ無理解で無礼きわまる誹謗擯斥陵辱のただ中において、その誹謗擯斥陵辱に対して、あるいは憤りあるいは卑下することそのことの、さらに徹底的には、誹謗擯斥陵辱を邪悪とみることそのことの根底に横たわる誹謗正法の罪を自覚し、無価値なものを 無価値なままにあらしめたもう如来に息吹き返して、許多の誹謗擯斥陵辱のただ中に、虚心平気に生きておいでになる一人の清澤先生が厳存したもうばかりである。
(『出雲路暢良選集』第一巻「臘扇記聞思録」一六四、一六五頁)
こういうところにですね、「いつわりなき光」に照らされつつ光を仰ぐという、そういうことが先生から教えられるような思いがしております。
先生もまた本当にまだ若い、――先生が亡くなられたのは六十二歳ですもんね。だからまだまだやることも多く、また皆さん方からもようやく住職として「頼もしい住職になってほしい」というか、ついて行きたいという気持ちのご門徒さん方が大勢いる中に、「自分が最低の住職であった」という言葉を先生は手紙の中に書かれています。
先生は、長く私たち学生の相手になって,時間を割いてくださいました。先生は家庭も顧みず、お寺もお父さんに任せて顧みず、ご門徒さん方からの不平不満というか、願いというか、そういうものを振り払って生きてこられました。
それがようやく、ご門徒の願いに応えていける時が来たと思ったら、ずっと引きずってこられた結核の病がひどくなるばかりでした。そういう中で先生はあの「寂光の中で」(『出雲路暢良選集第5巻』)という文章を書かれ、自分の気持ちは本当に寂かな光の中にいるような気がします、安んじて生き死にを受け止めていきます、と。そういうお手紙が残されて、選集に載せられています。
先生は清沢先生を本当に大きな教えとして、自分自身を生死貫いて全うしていかれたんですね。
あるお話の中で、「死によって何が失われますか?」「死によって失われるものなどありませんよ」と、先生はきちっとおっしゃっていましたね。そういう言葉もまた響いてまいります。
寺に生まれた者への恵み――呼ばれる者となって生きる
この度、香さんが住職になられたことを、先生はお聞きになって、どんな思いでいらっしゃるでしょうか。先生が住職になられた時、先生は、専光寺というこの聞法道場の「柱の一本一本、境内の石ころの一つ一つにまで」自分を育て、自分を養って、「念仏成仏」という道に「押し出してくださった」人々のお陰があるんだ、ということを書かれておりますね。(『出雲路暢良選集第5巻』)
そこに、「無名の先輩のおろかにして真摯な聞法の道念のおかげでありました」。――たぶんご門徒さま方をいっているのだと思います。「おろかにして真摯な聞法の道念のおかげでありました」と。お念仏の教えを聞かせてもらって、苦労多い人生をしっかり生きていこうという、そういう「おろかにして真摯な」、真面目な道を慕っていく気持ち、そういう方々がお寺には集うていてくださっているんだ。お寺に足を運ぶ方々の、身を運ぶ方々の、心の底にですね、表には現れないこともあるでしょうけれども、お寺に対する深い願い、期待、自分の人生への深い願いがあって、そういう方々の「おろかにして真摯な」道を願っていく「道念」、道を念う気持ちに自分は支えられてここまで来たのでした、ということが先生にはありましたね。
こういう先生のお姿を通しながら、今、私もですね、お寺に嫁いでもう四十年になってしまってですね、いよいよ終わりに近づいたようなことですけれども、先生はお寺に生まれたということに、自分が「念仏成仏」の仏道を歩むという身にさせていただいたということに、大きな恵みをいただいておられましたね。
若い人から「お寺は風景である」と言われましたけれども、先生は、外に向かって呼ぶのじゃない、呼ばれる者となっていく、問われる者となっていく、促される者となっていく、そういう身になって生きられました。
現実問題から問われて――「農村問題研究会」
ある時、先生が金沢の香林坊とか片町とかで、冤罪を訴えるビラを配っている姿を見たことがあります。先生もこういうことをなさるんだと思ってですね、街の人混みの中に立って一人一人に配っておられました。
この度、ここへ来る前に、まだ読んだことのない本を読もうと思って、農村問題研究会(金沢大学社会教育研究室農村問題研究会)の発行した『明日をきずく』(家の光協会、一九六八年)を読みました。
先生は金沢大学の社会教育研究室に所属していた三十代から農村問題研究会に関わっておられました。戦後の新しい農業を模索する中で、農業従事者が家や土地に縛られ、農村共同体に埋没しているあり方を問い、新しい農民像を求めていく話し合いを繰り返しておられました。
その中で先生が追求してたのは、農業生産を高めるとか、そういう現実的な経済問題ももちろんありましたよ。でも自分が農業をやっているということで、本当に満ち足りていく、そういうものが生まれる農業への信念というか、そういう事はどうなんだという、主体性を問いかけている先生の言葉がありましたね。
それから、農業というのは保守的なところがあって、なかなか新しいところに飛び出していかない。そういう保守性をお寺が培ってきたろうって責められてもおられましたね。
三十三年も経ってしまったことから、私もですね、本当に呼びかけられる身になる、促される身になる、現実問題から問われる身になる、そういう身になるということのお育てを、先生は亡くなっておられませんので、偽りなき光の中に厳存しておられる先生の叱咤激励を受けながら、この道を歩んでまいりたいと思っております。(続く)
(二〇二二年三月二七日、専光寺にて)